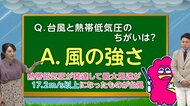地域の課題解決を、市民から寄付された資金で支援しようと、県内で初めてとなる市民ファンドの設立に向けて、準備が進んでいます。
8月19日、宮崎市で、「みやざき市民ファンド」の設立に向けた、会議が行われていました。
「若い人たちの支援というのも、ひとつ大きな目的としてあるんですけど、災害は県内どこでも一緒なので」
去年10月、宮崎大学地域資源創成学部の根岸裕孝教授、NPO法人宮崎文化本舗の石田達也理事長などが中心となって、設立準備委員会が発足しました。
市民ファンドとは、市民や企業などから寄付を集め、その資金を、地域の課題解決に取り組む人や団体に助成する仕組みです。
(宮崎大学地域資源創成学部根岸裕孝教授)
「行政からのお金だけではなくて、やはり市民・地域の皆さんの思い、なんとかしたいという気持ちが、お金という形で解決に使われていくと。このしかけをつくることが大切だと思っている」
みやざき市民ファンドが掲げる役割は、大きく2つ。
「若者の支援」と「大規模災害発生時の迅速な被災者支援」です。
(宮崎大学地域資源創成学部根岸裕孝教授)
「最近は災害が多くて、それに対する支援というものが、どうしても行政経由だと時間がかかったり、本当に必要なものが手当てされないとかありうる中で、身近なところでお金が手当てされていくと」
市民ファンド設立には、財団法人の登記を行うための資本金300万円が必要で、現在、クラウドファンディングや募金箱などで、寄付を募っています。
この日は、日南市の道の駅酒谷に置いてあった募金箱が、設立準備委員会に渡されました。
「大切な寄付です。よろしくお願いします」
「ありがとうございます。頑張ります」
「活用してください」
(道の駅酒谷日高茂信社長)
「色々な災害、いまいつでも起こりうる水害、そういったことに対して、即対応ができると思うので、そういったところを、市民目線でどういった使い方ができるか、そして良い活用の仕方、そういったところが一緒になって考えられるといいなと」
設立準備委員会によりますと、市民ファンド設立のための寄付金は、8月20日時点で、300万円のうちおよそ290万円が集まっていて、8月31日まで寄付を募っています。
また、実際に災害時の被災者支援などに使われる助成金の資金についても、9月1日から寄付を募るということです。
設立準備委員会によりますと、去年1月の能登半島地震では、石川県の市民ファンドが発災直後から寄付を集め、6500万円以上を、迅速に、被災地の緊急支援や復旧・復興活動などへの助成に、活用したということです。
ここまで、市民ファンドの話題についてお伝えしました。