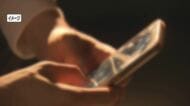原爆投下後の長崎で救援活動に当たった男性。長野県の旧四賀村(現在は松本市)で村長を務めた中島学さんは、当時15歳の少年航空兵として長崎に赴きましたが、目に映ったものは「生き地獄だった」と振り返ります。自らの体験を若い世代に伝えたいという95歳の証言です。
8月1日から全国公開中の映画「長崎ー閃光の影でー」。実際の手記をもとに原爆投下後の長崎を看護学生だった少女たちの視点から描いた作品です。
映画で描かれたのと同じ頃、廃虚と化した街に足を踏み入れた少年がいました。
旧四賀村の村長だった中島学さん95歳。当時15歳で、傷ついた人々の救出にあたりました。
中島学さん(95):
「がれきを少しずつ手で片付けて段々、段々深くしてって、『今、助けてやるからな』と言って。その惨めな凄惨な状況がね、目に入るわけですね」
現在は松本市となった旧中川村の農家に生まれた中島さんは1944(昭和19)年、14歳で海軍特別年少兵に志願します。
中島さん:
「家が貧乏で、松本の旧制中学へやることはできないってことで、進学できないとすれば、いろんな選択の中でも当時、特別年少兵が非常にクローズアップされてきれいなポスターもいっぱいあって、それに憧れて航空隊へ志願したわけです」
厳しい訓練を経て終戦の年の1945(昭和20)年6月に配属されたのは、長崎の20キロほど北にある大村市の海軍航空基地でした。間もなく迎えた初の実戦では、上官から最新鋭の戦闘機「紫電改」の操縦席の後ろに座って敵機を見張るよう命じられます。
中島さん:
「でも戦果をあげることができなくて、逆に被弾して私が額をちょっと負傷したり、左手の肉を持っていかれたですね。それで目の中に血が入るものですから、『班長、目が見えません』って」
額や左手に破片を受けたものの、幸い大事には至りませんでした。
そして「運命の日」。
基地の壕にいる内に湿ってしまった服を乾かそうと外に出た中島さんは、南へ向かう機影を目撃します。それは第一目標の小倉への原爆投下を視界が悪いために断念し、第二目標の長崎へ向かうB29でした。
中島さん:
「ゆっくり大村上空を通って、それで長崎に消えていって」
1945(昭和20)年8月9日午前11時2分、原爆投下ー。
中島さん:
「十数秒間、青白い閃光がピカーッと光ったんですね。それからちょっと間をおいてものすごい爆発音が鳴った」
広島に続く2発目の原子爆弾がもたらした熱線と爆風で長崎の街は壊滅。その年だけで7万人以上が犠牲となりました。
中島さんの部隊は3日後の8月12日に救援に赴きますがー。
中島さん:
「かつての長崎を見てますから、われわれ唖然としちゃって。惨めなね、建物が全部崩れる。木造なら理解できるが、鉄筋コンクリートでも何でも全部崩れちゃうんです」
被害の状況から、中島さんが活動したのは原爆が投下され、最も被害の大きかった浦上地区周辺だったとみられます。
中島さん:
「命令としては、既に死んでる人は一切見てはいけないと。『助けてくれ』って蚊の鳴くような声ががれきの下から聞こえるから、『今助けるからな、頑張れ』ってがれきを1個1個手でどかして、頭が出てくれば『さぁ、頑張れよ』って、脇の下に手をかけて引っ張り出してあげて。道具とか何にも無いわけでジャッキも無ければ何にも無い。とにかく全てが手です」
中島さんは、急きょ仕立てられた「救援列車」に負傷者を運び、被害の少なかった諫早や大村の駅まで送り届けました。
そのホームではー。
中島さん:
「被爆した人は『水くれ、水くれ』って叫ぶんです。かわいそうにね。水を与えるとあっという間に亡くなっちゃうわけです。水を飲むと重傷の方は大体10分か15分で息絶えるわけです。さっきまで叫んでた人が静かになったなと思えばもう息絶える。生き地獄という言葉があるが、これだろうなと思いましたね。まさに地獄です」
がれきの山と化した街で忘れられない光景があるといいます。
中島さん:
「一番凄惨に感じたのは、長崎市から標高で100メートルぐらい上がった山の中腹に、立派な中学校があったんです。その中学が鉄骨が数本残っただけです。全部潰れちゃいました」
爆心地の周辺には国民学校や中学校、女学校があり、児童の9割が犠牲となった学校もありました。
中島さん:
「あれはかわいそうでしたね。思い出せば本当にね、かわいそう。戦争はダメですね、本当にね。かわいそう」
3日後の8月15日、戦争は終わりました。9月になってふるさとに戻った中島さんを見て、家族は驚愕します。情報不足のため新聞などで被害が過大に伝えられていたからです。
中島さん:
「あの長崎にいたから生きて帰るはずがない、私は完全に死んだってみんな思っていたんです。おやじがつかまえてみたら『幽霊は冷たいはずだが温かいぞ』って。『学は生きて帰ってきた』と。そこからはもう本当に劇的なものでした」
長崎で「地獄」を見た中島さん。放射線の影響もあったのかは判りませんが、生きる目的を失い、4年間何もする気になれず死んだような日々を送りました。
中島さん:
「ふるさとへは帰ったが俺は何のために生きているんだと。中島学はこれでいいのかってことを次第に考え始める」
20歳になった中島さんは農家を継いだ後、農協の指導員となってふるさとのために力を尽くします。1963(昭和38)年には多額の負債を抱えていた養鶏農家を救おうと組合を設立。松本地域で最大の養鶏場に育てました。その後、村会議員を経て1991(平成3)年から14年間、松本市と合併する前の四賀村の村長を務めました。
精力的に働いて来た中島さんですが、いつも心の中には「戦争」や「長崎」がありました。在職中に核兵器の廃絶と平和の実現を目指す村の宣言をしたほか、地元の小中学生に自分の戦争体験を語ってきました。
今も「あの日」の記憶は心に深く刻まれています。
中島さん:
「時々、夢に見るんですよ。そうするとうなされますよね。『今、助けてやるから』なんて叫んで、家内に『何言ってたんだ』なんてね。夜中に結局、思い出して叫んでいるそうです」
8月9日、長崎への原爆投下から80年が経ちました。中島さんも、いつか「戦争」がなくなることを願い続けています。
中島さん:
「もう本当に何もないです、戦争は。ただ破壊だけで、その破壊の中に尊い人命がどんどん失われていくという、人の幸せってものを全部奪っちゃうわけですから、これは絶対許されないわけですね」
「いろいろと困難な状況が出てくる。それはもう世の中当たり前です。だけど、とことん話し合いで乗り切って解決して、決して戦争ってものに持ってかないことを若い人たちの英知でやってもらわないと」