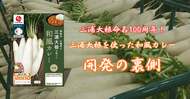旭川家具工業協同組合は、2025年大阪・関西万博の「Co-Design Challengeプログラム」での「椅子」の提供を通じて、地域の家具産業の発展と品質向上をめざす。同組合では、1990年から3年ごとに「国際家具デザインコンペティション旭川」(IFDA)を開催するなど、デザイン意識を高め、国際的な視点を取り入れた活動を展開するとともに、地域材の利用率を向上させ、持続可能な素材と製法の研究に力を入れている。また、家具製作のプロセスを実際に見学・体験し、地域の森林資源と製造技術の連携を深く理解する機会となる体験企画も万博期間内に北海道旭川市で行う予定だ。そのプロジェクトについて、3回のシリーズ企画で迫る。

※シリーズ記事は、「Co-Design Challengeプログラム」のホームページに公開しています。各記事は、取材時点の情報のため、プロジェクトの進捗や開発状況によって当時から変更となった点などが含まれます。
木製家具が育んだデザイン都市。旭川家具の魅力を世界へ発信 Vol.1

旭川家具工業協同組合理事長藤田哲也さん
日本の森林率は経済協力開発機構(OECD)加盟国の中で3番目であり、世界有数の森林大国である。なかでも北海道は、日本の森林面積の22%を占める。その豊かな森林を生かした木工家具のまち旭川は、日本の5大家具産地の一つに数えられている。Co-Design Challengeでは、北海道産材を使った旭川家具の椅子を万博会場に提供し、国内外からの来場者にデザイン性と高い技術力を体感してもらう予定だ。その歴史をひもとくと、北海道産材の良質さに気付かせてくれたのは、ヨーロッパの木工家具だった。
北海道大雪山系――。厳しい自然環境で生育するナラは銘木として、北海道オークと呼ばれる。山上ではマイナス40℃、夏には30℃近くになる環境の変化は、冬と夏の成長スピードの違いを生み、比重が高く目が細かい、強度のある木材が育つ。しかし戦後、ナラは鉄道の枕木や薪に使われ、旭川では家具材としてはあまり扱われていなかった。
1962年、旭川市の海外派遣技術研修制度により、製造技術習得のため西ドイツに3人の木工青年が派遣された。その一人であった長原實が立ち寄った港町にうずたかく積まれた木材には『OTARU』と焼き印があった。旭川の大雪山連峰周辺で伐採した木材が小樽港から輸出されていた。
旭川家具工業協同組合理事長の藤田哲也は、「彼は衝撃を受けたに違いない。自分が育った地域から輸出された木材が、素晴らしいデザインと技術により、世界で高級家具として売られている。その実態を知った長原實は、西ドイツで3年半修行を積み、『木材を生かすデザインと技術で世界に並ぶ仕事がしたい』という思いで帰国後の1968年に作った会社がカンディハウスです」と、藤田が現在会長を務めるカンディハウス誕生と密接に関わる旭川家具の歴史を語る。
この研修の成果は、良質な北海道材を生かすものづくりへ向かう旭川家具にとって、大きな転機となった。1965年の第10回全国優良家具展では、旭川家具が最高賞「内閣総理大臣賞」を受賞。1967年にスペインで開催された、23歳以下の技術者が参加する技能五輪国際大会の家具部門に日本代表として旭川の家具職人が挑み、世界第2位を獲得。旭川家具の技術力は世界で高く評価されることになった。2024年9月にフランスで行われた同大会の日本代表も旭川の家具職人で、実に9大会連続で旭川から選出されている。
「北海道の良質な木材と世界に認められた高い技術。その技術力があるからこそ再現できるデザイン力が旭川家具の魅力です。デザインに関しても、世界を意識した積極的な取り組みをしているので、Co-Design Challengeに参加してみてはどうかと我々の活動を知る方が声を掛けてくださった」。藤田が言う、世界に先駆けたデザインの取り組みとは。


旭川家具の技術やデザイン、歴史が学べる、旭川デザインセンター2階
「ADC MUSEUM」
木製家具が育んだデザイン都市。旭川家具の魅力を世界へ発信 Vol.2

万博会場へ提供予定の「 IFDA 」出品作から生まれた製品
1990年に旭川市開基100年記念事業の一環として「国際家具デザインコンペティション旭川(IFDA)」は開催された。IFDAは3年に1度開催され、2024年に12回目を迎えた。世界中から木製家具のアイデアを募り、優れたデザインを追求するこの取り組みは、家具デザイナーの登竜門となっている。2024年6月の審査会では2025大阪・関西万博で会場デザインプロデューサーを務める建築家・藤本壮介氏をはじめアメリカ、ヨーロッパなどの著名デザイナー5人が審査を行った。ここまでの12回の開催で、計1万点を超える応募があり、デザイナーと旭川家具工業協同組合のメーカーなどが契約し、製品化も行っている。
「2024年は、世界38の国と地域から655点のデザインが集まりました。旭川のように、34年という長きにわたり、木製家具のデザインコンペを続けている国や地域は他にはない。Co-Design Challengeでは過去の受賞作などから、旭川家具の魅力が伝えられる椅子5脚を万博会場に提供する予定です」と藤田は言う。
また旭川市では、家具だけではなく、建築や機械金属、食や観光などの地場産業の魅力をものづくりツアーやワークショップなどで体感してもらうデザインイベント「あさひかわデザインウィーク」を2015年から開催している。デザインウィークの期間中には、旭川家具工業協同組合の主催で、旭川家具の産地展「Meet up Furniture Asahikawa」を開催しており、家具職人が技術力を競う木工技能競技大会やオープンファクトリーなど多彩なイベントを行っている。「オープンファクトリーでは、童心に返って、楽しく木工の世界を体験してもらっています。塗装されていない白木にペーパーをかけて、オイル塗装して仕上げるという経験が、あまりないんですよね。木製スプーンを削って磨いて、完成をどの時点にするのかは人それぞれ。ものづくりを擬似体験していただけます」と藤田はほほ笑む。2025年は万博期間中の6月に開催を予定しており、旭川と万博会場の連携や相互誘客も期待される。
旭川市は2019年、ユネスコデザイン都市に認定された。2024年10月現在で、世界49都市、国内では神戸、名古屋についで3都市目となる。「Co-Design Challengeを通じて、旭川の良質な素材、世界クラスのデザイン力、最高の技術力など、旭川の強みを世界中の方々に見ていただきたいし、また旭川に来て実際に体験してほしい」と藤田は優しい曲線を描く木製家具にそっと手を添えた。

旭川デザインセンターでの木工体験ワークショップ、木のスプーンづくりの様子

部品の組み立ての様子(カンディハウス工場)
木製家具が育んだデザイン都市。旭川家具の魅力を世界へ発信 Vol.3

万博会場に提供される5脚の椅子
「家具の聖地」と呼ばれる旭川。デザインを武器に時代を牽引してきた原動力は、30年以上にわたって作り手とデザイナーをつないで新しい風を吹きこんできたIFDAの存在だ。万博に提供する5脚の椅子は、IFDAの入賞作などからカンディハウスが北海道産広葉樹を使って製品化したもの。「デザインとものづくりが融合した世界にも例のないスタイルを見ていただきたい」。藤田は万博への思いを語る。
旭川在住の下里修平がデザインした2021年の入選作「フラン リビング イージーチェアー」もその一つだ。「美しいポテンシャルのあるデザイン」に注目が集まったが、藤田が「このままでは製品化が難しい。一緒にデザインをやり直そう」と提案して取り組んだ作品だ。当初は頭が出るくらいの小さな背もたれだったが、座る人を包み込むような背もたれにし、座面も体勢を自由に変えられるような広いものに変更することで「自分だけの居場所が作れる」椅子にブラッシュアップ。ユーザーの評価も高くウッドデザイン賞2023では林野庁長官賞に選ばれた。
「なにこれ、とびっくりさせたい」というのが「KINA LUX(キナ ラックス)」だ。2017年の「IFDA記念制作展」にニュージーランドのデザイナーが出品したもので「KINA」とはマオリ語でウニを意味する。特徴的な網目模様はウニの殻にインスパイアされたと言いアート要素も強いが、大人が3人座れる強度も確保して、オットマン(足乗せソファ)などのスツールとしても使える。複雑な網目の形状のデザインを家具で表現できるのはカンディハウスが得意とする成型合板とCNC加工の技術だ。薄い板を重ねて型を作りプレス加工することで多様な曲面にも対応し、コンピュータ制御の加工機械が複雑な網目を削り出す。デザイナーのチャレンジングな要求を職人たちのこまやかな感性と高い技術力が支えてきた。
体験企画では、旭川家具工業協同組合が中心となり2025年6月25日(水)から29日(日)まで「Meet up Furniture Asahikawa」を開催する。家具以外の建築、機械金属、食品などの団体も参加する地域のデザインイベント「あさひかわデザインウィーク」の期間中に行われ、20か所の工場を見学できるオープンファクトリーなどを実施。旭川デザインセンターでは木工体験のワークショップもある。藤田は「多くの工場はショールームも併設しており、ものづくりの現場を体感してほしい」と話す。良質な木材に恵まれた北の大地で生まれる卓抜したデザイン。旭川家具は万博を舞台に一層の輝きを増す。

座る人を包み込むような背もたれの「フラン リビング イージーチェアー」

「KINA LUX」の特徴的な網目のデザイン
Co-Design Challengeとは?
Co-Design Challengeプログラムは、大阪・関西万博を契機に、様々な「これからの日本のくらし(まち)」 を改めて考え、多彩なプレイヤーとの共創により新たなモノを万博で実現するプロジェクトです。
万博という機会を活用し、物品やサービスを新たに開発することを通じて、現在の社会課題の解決や万博が目指す未来社会の実現を目指します。
Co-Design Challengeプログラムは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が設置したデザイン視点から大阪・関西万博で実装すべき未来社会の姿を検討する委員会「Expo Outcome Design Committee(以下、「EODC」)」監修のもと生まれたプログラムです。
※EODCでの検討の結果はEODCレポートをご覧ください
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ