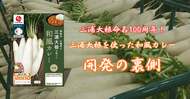株式会社折兼は、2025年大阪・関西万博の「Co-Design Challengeプログラム」で、「未利用木竹材を活用した森林・地域を元気にするごみ箱」を提供する。多様な事業者や地場産業と連携し、木や竹を活用して山の手入れを進めることにより、森林再生や地域活性化を図るとともに循環型社会の実現をめざしている。また、今回のごみ箱の原材料の生産地である徳島県那賀町を舞台に、環境省の自然共生サイトにも選定された山林でのアクティビティー、工場見学、杉製のSUPボード体験など森林や自然を楽しみながら学ぶ「森林まるごと体験ツアー」を企画している。そのプロジェクトについて、3回のシリーズ企画で迫る。

※シリーズ記事は、「Co-Design Challengeプログラム」のホームページに公開しています。各記事は、取材時点の情報のため、プロジェクトの進捗や開発状況によって当時から変更となった点などが含まれます。
木粉が生む「森林・地域を元気にするごみ箱」。木と生きる町からの発信 Vol.1

試作品の「森林・地域を元気にするごみ箱」
徳島県南部に位置し、9割以上を森林が占める那賀(なか)町。人口7,000人余りと、5町村合併後も過疎化・高齢化が進むこの町から万博に送り出すのは、未利用の県産木竹材を活用した「森林・地域を元気にするごみ箱」だ。木々を粉砕した「木粉(もくふん)」を樹脂加工したもので、様々な商品への応用が見込まれ大きな可能性を秘める。「林業はカッコいいぞ」。「清流と森のナカ」から熱いメッセージを発信する。
木粉を製造するのは創業10年を迎えた「那賀ウッド」だ。副社長の庄野洋平は隣接する阿南市のタケノコ農家に生まれ、竹林を遊び場に育った。かつては全国1位のタケノコの生産量を誇り、多くを水煮に加工していた阿南市だが、中国から格安の品が入るにつれて生産量は減少し、後継者不足もあり放置竹林が増えていくようになった。手入れが行き届き、日の光が土壌にまで差し込んでいた美しい竹林。間伐を怠り、荒れ放題になると、竹が密集し下草も生えなくなる。そうなると根が浅い竹は大雨などで流れやすく、土砂崩れなどの災害の原因になる。そんな状況を目の当たりにしてきた庄野にとって、循環型社会実現のために木や竹の活用を目指すのは自然な流れだった。
「森林・地域を元気にするごみ箱」は、那賀ウッドとパートナーを組んできた「パナソニック プロダクションエンジニアリング」がペレット化、「テラモト」が製造を担当するなど計4社が参画し、食品包装資材専門商社の「折兼」が代表企業として取りまとめることで、Co-Design Challengeへの応募に道が開けた。
眼下に清流が流れ、周囲を豊かな自然が取り囲む広々とした土地に那賀ウッドの工場がある。原木の丸太が積まれ、工場横には機械で割られた薪(まき)や製材端材が乾燥のために無造作に置かれている。工場内に運ばれた木片は、手作業でコンベヤーに投入され、粉砕ラインを通っていく。いくつかの工程を経て機械から吐き出されてくるのは、木の香りを残したさらさらの木粉だ。ノコギリで切った後にでる「おが粉」よりさらに細かく、「きな粉」のようだとも例えられる。
那賀ウッドの独自のノウハウで加工される木粉。出所のしっかりした徳島県産の未利用木材を使い、前処理、粉砕加工、保管管理を徹底して行うことで、ばらつきのない安定した品質を生む。解体材は一切使っていないため粘着剤や防腐剤などの不純物の混入もない。「地域の木を少しも無駄にすることなく使い尽くす」。庄野のこだわりが、徳島の林業に希望の道を開く。

破砕機で未利用材を粉砕する工程

「森林・地域を元気にするごみ箱」を作るための原料「木粉」
(那賀ウッド 取締役副社長 庄野 洋平さん)
木粉が生む「森林・地域を元気にするごみ箱」。木と生きる町からの発信 Vol.2

那賀ウッド 取締役副社長 庄野 洋平さん
「いい“いなか”」を掲げる那賀町。林業の持続的発展のためには6次産業化への取り組みが欠かせない。庄野は「木粉」に活路を見いだす。まず機能性に優れている。吸水、消臭、断熱など自然木の良さがそのまま生きている。さらに混ぜたり成分を抽出したりすることで、様々な商品への活用が可能だ。すでに食器やウッドレザーとして商品化もされている。
万博へ6個提供する予定のごみ箱は、県産の竹や杉で作った木粉を樹脂と合わせて成形する。木粉の原材料となる竹や杉の未利用木材は、活用が進まずに廃棄されることもある。廃棄されるものを収集するごみ箱を地域の未利用木材から作ることで、ごみや資源の有効活用を考えるきっかけになればという思いが込められている。試作品は、幅24cm高さ28cmで一見樹脂製にしか見えないが、徳島の木の良さをたっぷりと練り込む。木粉の配合量を少しでも多くできないかと最終調整に入る。また配色や杉のイラストなど、デザイン面でも存在をアピールできないかと議論を重ねている。
木粉工場見学などの体験企画を予定しているが、人気を呼びそうなのが、自然を遊び尽くす「森林まるごと体験ツアー」だ。「エイト日本技術開発」が中心となってプランを練る。ここでしか楽しめないのが杉製のパドルボードを使ったSUP体験だ。波の少ない川口ダム調整池でパドルを漕(こ)いで進む。杉製ボードは、地元で手作りしたもので、長さ3mと4mの2本を用意した。美しい木目で優しい手触りだが、重量感も半端ではない。3mで40㎏、4mで80㎏。ただし水に浮かべてしまえば木の浮力もあり重さを感じることなく、安定感のある乗り心地が楽しめる。「木を使ったボードを作ることで、山と川、さらに海のつながりも伝えたかった」と庄野は話す。SUPを楽しんだ後は、そばにある「もみじ川温泉」で疲れた体を癒やすこともできる。
子どもたちは、町の木をふんだんに使った「木育」発信の場「那賀町山のおもちゃ美術館」でたっぷり遊べる。「けんだまひろば」や「すみやきごや」など、ここでしか体験できないおもちゃが用意され、多世代でも十分に楽しめる。ほかにも環境省の自然共生サイトに選定された山林でのトレッキングや、春にはタケノコ狩りと、四季それぞれの自然を味わってもらえる楽しさ満載のツアーになる。大手旅行会社からも「こんな魅力があるなんて知らなかった」と声が上がったほどで、庄野は発信されないままになっている地元の良さを改めて認識した。
万博への参加は町民にとっても大きな自信になるはずだ。何より若者に林業の魅力に目を向けてもらいたい。「木と生きる町」として地域が守ってきた価値ある資源に世界が目を向けてくれるきっかけにつなげたい。万博は大きな飛躍の舞台となる。

徳島県那賀町の森林

体験企画の訪問先のひとつ「山のおもちゃ美術館」
木粉が生む「森林・地域を元気にするごみ箱」。木と生きる町からの発信 Vol.3

「森林・地域を元気にするごみ箱」。右は杉の木粉、左は竹粉を使用
※ごみ箱のペイントなど、一部画像処理を行っています
未利用の徳島県産木竹材を余す所なく使った「木粉」から生まれる「ごみ箱」。「森林再生、地域活性化」の旗印のもと、代表企業の折兼と新たに旅行会社JTBが加わり、協力企業5社の力を結集してデザイン、成形などの開発に知恵を絞ってきた。コーディネーター的な役割を果たす折兼の服部貞典は「通常つながることのない会社が、Co-Design Challengeを機会に手を結び、一緒になって新しいものを作ることができた」と言う。庄野も振り返る。「折兼を中心にチームが一丸となった。単独ではたどり着けなかった」
庄野がこだわった木粉の配合量も、目標をほぼ達成し、半分近くまで混ぜ込むことができた。安定した形状を確保するため、樹脂との配合割合の微妙な調整が続いたが、今後の木粉利用5割以上達成も視野に入ってきた。
デザインでも大きな進展があった。木粉を混ぜ込むことで素材を流し込む際にムラが出来るが、「これも自然素材を使っているからの表情。一点ものの味わいを楽しんでもらおう」と積極的に活用することにした。ダークブラウンのグラデーションの色合いをいかしながら、杉と竹のシルエットをイラストにあしらう。とはいえ高さ28cmのごみ箱。万博で存在をアピールするための次の一手はないものか。丸太の台座にごみ箱を固定すれば、という案が出た。台座は高さ30cmほど。どっしりとした台座の上にごみ箱を固定すれば、杉や竹のシルエットが丸太から生えてきているようにも見える。高さもちょうどいい具合になり、見栄えが格段に増した。
ごみ袋も植物由来30%のものを使い、ごみ箱のデザインが隠れないようにかぶせ方にも工夫を凝らすつもりだ。環境に優しい素材で作り上げたごみ箱。「ごみを捨てる前に本当に不要なのか、気づきのきっかけになれば」。庄野は期待する。
「自然のテーマパーク」と言える豊かな自然に恵まれた徳島県那賀町などを存分に楽しんでもらおうと春、夏、秋と予定される体験企画も細部を詰める。JTBと目指すのは、地域の魅力を生かして旅行者を呼び込む「着地型観光」だ。地元の人が慣れ親しんできた日常の自然や風景は、外部の目を通せば「非日常ですごくいい」という付加価値を生む。竹林にデッキやテーブルなどの眺望スペースを整備すれば、持続可能な観光にもつなげられる。
静かな森林と清流に包まれる那賀町。大事に守られてきた地域の宝は、まだまだ隠れた魅力を秘める。「動くことによって可能性が広がる」。庄野の実感だ。ごみ箱で地域を元気にする。挑戦を重ねながら林業の未来、那賀の未来へと一歩ずつ歩みを進めていく。

万博会場へ計6個提供される「森林・地域を元気にするごみ箱」(ペイント前)

夏の体験企画のひとつ「SUP体験」の様子
Co-Design Challengeとは?
Co-Design Challengeプログラムは、大阪・関西万博を契機に、様々な「これからの日本のくらし(まち)」 を改めて考え、多彩なプレイヤーとの共創により新たなモノを万博で実現するプロジェクトです。
万博という機会を活用し、物品やサービスを新たに開発することを通じて、現在の社会課題の解決や万博が目指す未来社会の実現を目指します。
Co-Design Challengeプログラムは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が設置したデザイン視点から大阪・関西万博で実装すべき未来社会の姿を検討する委員会「Expo Outcome Design Committee(以下、「EODC」)」監修のもと生まれたプログラムです。
※EODCでの検討の結果はEODCレポートをご覧ください
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ