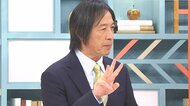「寒波到来」と言われた日の午後、犬の散歩に出かけた。風は冷たかったが、陽射しがある中を歩いていたら、急に身体が重く感じ、頭がぼーっとしてきた。
帰宅後、体調は回復したが、ふと夏の熱中症を思い出した。寒さがもたらす症状はあるのだろうか?

天気と体との関係を長年にわたって研究し、日本初の「気象病外来・天気痛外来」を開設した、佐藤純医師に話を聞いた。
■10月まで暑かった!秋が短く「寒冷順化」できていないかも
佐藤純医師:寒い季節を元気に過ごすには、体を寒さに慣らし強くする「寒冷順化」が必要です。例年なら徐々に寒さに慣れ、体が冬仕様になっていきます。
ところがこの冬は、去年10月まで夏日を何度も記録するなど秋が短く、11月に急に寒くなりました。急激な気温の変化によって「寒冷順化」がうまくいかず、体調不良を感じている人は多いのではないでしょうか。
「寒冷順化」ができていないと自律神経が乱れ、疲労感や倦怠感、冷え性、頭痛といった症状を引き起こします。
顔に冷たい空気があたって三叉神経(さんさしんけい 顔全体に分布し、顔の感覚を脳に伝える神経)が刺激された時に、めまいや倦怠感を感じるといったことも起こってきます。
また、疲労により体力が低下して、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなってしまうのです。
■「寒冷順化」のため外出するなら「3つの首」の保護を
佐藤純医師:「寒冷順化」のポイントの1つは「外出」。寒さに慣れるため、積極的に外に出て下さい。

佐藤純医師:その際、「首」「手首」「足首」を、マフラーや手袋、レッグウォーマーなどで保護しましょう。
「3つの首」の皮膚のすぐ下に動脈が通っていますから、ここを保護することで寒さを感じにくくなります。
また、急に寒い所に出るのはよくありません。暖かい部屋から寒い外に出る時は、暖房を切って少し体を寒さに慣れさせてからにしましょう。
■「つま先立ち」は立派な筋トレ 筋肉量増加を
佐藤純医師:2つめは「筋肉量を増やす」。筋肉はそれ自体が発熱しますから、筋肉量が増えれば寒さに強い体になります。

佐藤純医師:特に下半身の筋肉を意識して下さい。下半身は筋肉が多いので鍛えやすく、また、ふくらはぎの筋肉を動かすと、ポンプ作用で全身の血流がよくなり体が温まる効果もあります。
筋肉トレーニングというと、スクワットや腕立て伏せなどがありますが、取り組みやすい方法としては「つま先立ち」が良いでしょう。
家事をしながら、歩きながら、など出来る時に行って下さい。体力のない方は、テーブルに両手をつきながらでも大丈夫です。
軽い運動を毎日続けて筋肉を鍛えましょう。
■湯船で温まったら「膝下に水」でふくらはぎの「ポンプ作用活性化」
佐藤純医師:ふくらはぎのポンプ作用を活発化させるには「湯船で温まった後、膝から下に水をかける」のも効果的です。
皮膚を冷やすことで血管が収縮し、血流を保つことが出来るのです。血管が開きっぱなしだと、水分がたまって冷えてしまいます。
「冷たい水だとつらい…」という場合は、ぬるま湯でも大丈夫です。無理のないようにやってみて下さい。
寒さに強いか弱いかは体質によることもありますが、「寒さに強い体」はつくることができます。
ご自身の体力や体調の様子を見ながら、ポイントを押さえ「寒冷順化」を上手にしていきましょう。(佐藤純医師)
(関西テレビ 2025年1月24日)