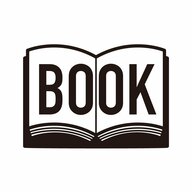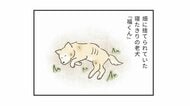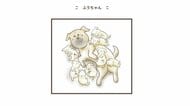その玉泉院丸には、現在は尾山神社の境内になっている金谷出丸側の出入口として、大型の櫓門である鼠多門が構えられていた。

金沢城のほかの建造物と同様、腰壁には海鼠壁が採用されていたが、ここだけは並べられた平瓦の目地が、白漆喰ではなく黒漆喰で印象深かった。
この門が、金谷出丸とのあいだを結ぶ鼠多門橋と一緒に、令和2年(2020)に復元された。
点から線、線から面へ
このように金沢城の復元整備は、櫓や門などの「点」だけに焦点を当てたものではなく、点と点を結んだ「線」、さらには線で囲んだ「面」をも整備している。
精密に復元された「点」は、最大の大名であった前田家の、美意識に裏打ちされた威信をいまに伝える。同時にこれらが、訪れた人の視線を「線」および「面」へと誘導する。
導かれた側はこの城郭の散策を、テーマパークを訪れたように楽しみながら、その規模や構造を把握する。結果として、城域がくまなく意味ある空間となっていく。価値ある復元である。
令和6年(2024)の能登半島地震では被害に遭ったが、現在も、藩主の住まいであり政務の場でもあった二の丸御殿の復元に向けて、整備が進められている。
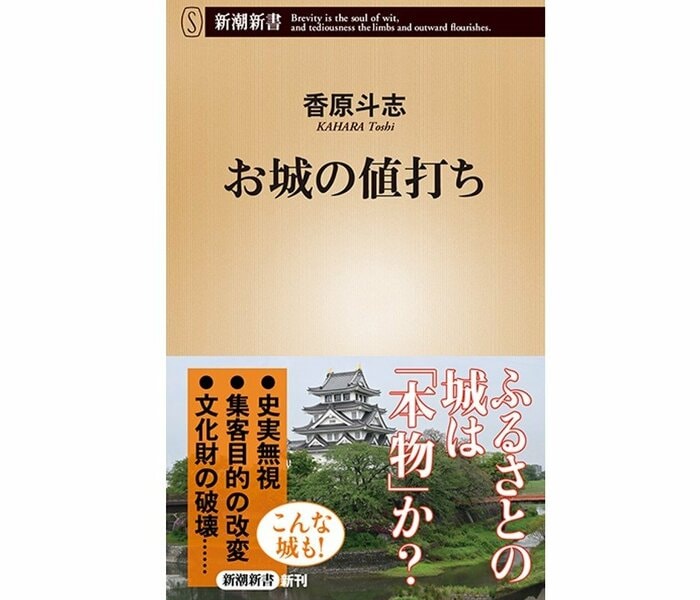
香原斗志
歴史評論家、音楽評論家。日本古代史から近世史まで、幅広く執筆活動を行う。主な著書に『教養としての日本の城』など。