東京・丸の内で、パラアスリートをガイドに迎え、参加者が近距離モビリティで街を巡り、イルミネーションを体験するイベントが開始された。移動中、普段は意識しない障害を感じ、都市設計の課題や工夫が浮き彫りになった。
イルミネーション体験で得た発見を街づくりに
幻想的な光に包まれる、東京・丸の内の目抜き通りには、多くの人で賑わう街を、別の視点から眺める人たちの姿があった。

5日に行われたのは、空間デザインを手掛ける乃村工藝社・大丸有エリアマネジメント協会が企画した、イルミネーションと対話がテーマの体験ツアー「Bright “Taiwa”Tour(丸の内仲通り、行幸通り)」だ。

3回目となる今回のポイントは、「視点の違い」で、現役のパラアスリートがガイド役になり、丸の内で働く参加者が近距離モビリティに乗って、あとをついて行く。
しかし、こんな場面も見られた。
ガイド:
(イルミネーション)見ています?
参加者:
ちょっと今、見ていなかったです。ぶつかりそうで、上を見上げる余裕が…。
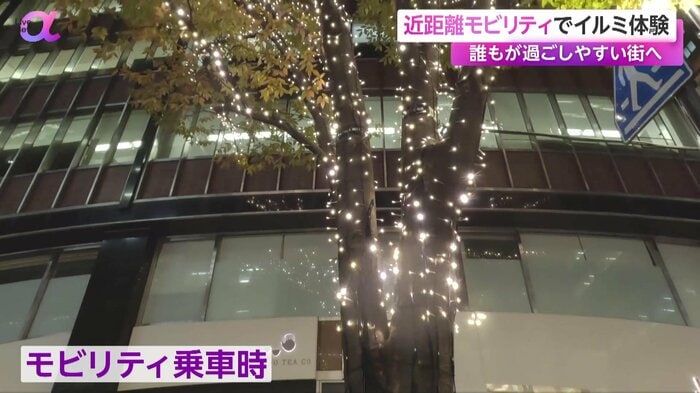
モビリティに乗った状態だと、目線が少し低くなり、街路樹に近づくと、大きく上を向かなければイルミネーションが見えない。記者も実際に乗ってみると、こんな“気づき”が…。
濱辺くるみ記者:
スムーズに段差を越えた感覚はあるが、普段踏み越える時より、衝撃を感じました。

「普段はあまり気にかけないものでも、障害やハードルになる」こうした発見も、実際に体験をしないと得られないものだ。

参加者:
点字ブロックが(通過するのは)めちゃめちゃ大変ですね。
ガイド:
そうなんですよ。

参加者:
(商品が)見えない。高すぎて見えない。腕の力で上がるにしても、力がなくてちょっと見えないです。

一通り街を巡ったあとは、参加者全員が集まり、意見交換を行い、さまざまな“気づき”を共有した。
参加者:
イルミネーションがどういう風につけられているのか、普通に写真を撮っていたら、土や床に近いところは見ないので、すごいそれが楽しかった。

ガイド役のパラアスリート・西崎哲男さん:
長いこと生活しているので、(ハードルと)あまり感じなくはなっているが、気にしながら(生活)してもらえると、声を掛けやすくなるのかなと。

近距離モビリティの新たな可能性や、今後のまちづくりを考える意味も込められた、今回のイベント。主催者は、こうした出会いと対話から、新たなまちづくりの形が生まれると期待している。
乃村工藝社 プランナー・齊藤佑輔さん:
(今後は) 聴覚だったり味覚だったり、さまざまな感覚があると思うが、一部分をピックアップして、新しい体験を作っていきたい。
今回は車椅子だが、そういうハンディキャップをある方も楽しめる、居心地よい空間を、まちづくりとしてやっていきたい。
高齢者が「出かけたい」健康的に笑顔で暮らせる街へ
「Live News α」では、コミュニティデザイナーで、studio-L代表の山崎亮さんに話を聞いた。
堤礼実キャスター:
いつもとは違う視点で輝く街を見てみると、色々な気付きがありそうですね。

コミュニティデザイナー・山崎亮さん:
今回の取り組みは、「これからの都市のあり方」を体感できる機会になると思います。何しろ、移動しやすい条件を整え、美しいイルミネーションが来訪者を迎える。
車椅子や近距離モビリティの移動体験を通じて、相互理解を深める対話が生まれたりもします。
自分が高齢になった際に、都市のあり方に思いを馳せることにもつながると思います。どれも素晴らしい体験になると思います。
堤キャスター:
これまでとは違う、住みやすさなどを考える機会になりそうですね。
コミュニティデザイナー・山崎亮さん:
高度経済成長期以降、日本は「団塊の世代」という若者を想定して、若い人を対象として街を整備してきました。
その若者が現在は高齢者になっていて、高齢者の人口は、今後数十年、多いままだろうと言われています。したがって、今後の都市再開発は、高齢者の利用を想定して進める必要があります。
堤キャスター:
具体的には、どんな課題があるのでしょうか。
コミュニティデザイナー・山崎亮さん:
高齢者は、自分と環境との間に、障害を感じやすくなります。それも複合的な障害を感じることが多くなります。
その結果、外出を避けるようになり、体力が低下してしまう。人と会う機会も減り、笑顔になる回数も減ることになります。
「健康で長生きする人を支える都市」を実現するためには、まず、「出かけたい」と思えるような街に変えていく必要があります。
誰もが愉しめる街をつくる対話と行動の重要性
堤キャスター:
出かけたくなる街づくりでは、どんなことが鍵になるのでしょうか。

コミュニティデザイナー・山崎亮さん:
都市で、「愉しい出来事」が起きていることが大切だと思います。今回は企業が「愉しい出来事」を用意してくれたということになりますが、今後は市民自らが、それを生み出していけたらいいなと思います。
さらに、「愉しい出来事」に、誰もがアクセスできる移動条件を整えて、多くの人の外出機会を創出することが求められるでしょう。そのためには、引き続き「さまざまな人達の対話」が重要になると思います。
堤キャスター:
人の気持ちに寄り添い、そして、同じ視点で同じ経験をする機会は、なかなか得られないものだと思います。こうした体験での気付きを大切にして、それを日々の生活に活かしていきたいですね。
(「Live News α」12月5日放送分より)




