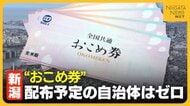2004年10月23日に発生した中越地震。最大震度7を観測し、68人が犠牲となった地震から20年が経った。甚大な被害を受けた被災地では20年前、復興に向け、様々な決断を迫られた。全村避難を選択した旧山古志村では、7割の住民が故郷に戻った。彼らは当時の選択についてどのように感じているのか、住民の今を取材した。
中越地震で約2200人の村民全員が避難
長岡市山古志地区竹沢集落で店を構え、50年以上になる「理容ほしの」。

店を営む星野吟二さんとサツ子さん夫婦の元には、毎日、地域の人が集まり、世間話に笑顔がこぼれる。
そんな店の中で吟二さんが見せてくれたのは、理容師にとって命だと話すハサミだ。「宝物として避難所に持っていった」と吟二さんは20年前を振り返る。

山古志にとって忘れることのない20年前…
2004年10月23日に発生した中越地震。最大震度7を観測し、68人が死亡、住宅被害は12万1495棟に上った。
旧山古志村では約2200人の村民全員が、すでに合併することが決まっていた長岡市に避難。

被害の大きさにより、避難生活が長期化する中、いち早く立ち上がったのが星野さん夫婦だった。
地震の3年後には7割の住民が帰村
地震から2カ月後になんとか無事だったハサミを使い、仮設住宅内に住民が無料で利用できる理容店をオープンした星野さん夫妻。
髪の毛を切りながら「みんなが少しでもいい気分でお正月を迎えられたら」と笑みも見せていた。

そして地震から1年…。
「みんなが帰ってくれば、明るい村になるよう努力したい」復興への誓いの中、星野さんは一番に集落に戻り、再び店のサインポールを回し始めた。

その星野さんに続くように地震から3年後には、旧山古志村の住民の7割にあたる約1400人が戻ってきた。
不安や怒りも…村長と住民による“交換ノート”
当時の住民の心情を垣間見ることができる資料が残されている。長島忠美村長と避難生活を送っていた住民による交換ノートだ。
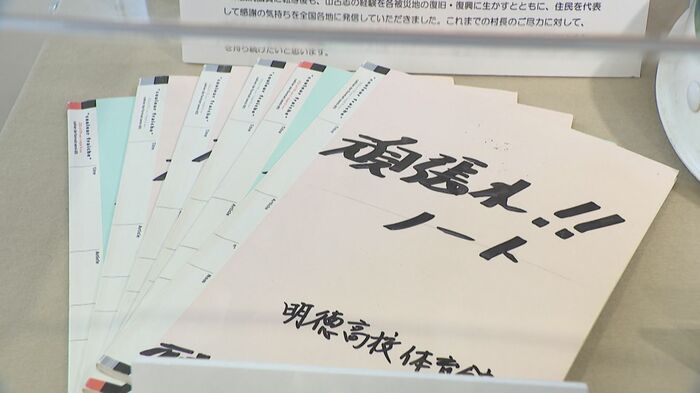
そこに記されていたのは、不安ややり場のない怒りなどを書きつづった住民の言葉とリーダーとしての苦悩。
地震発生直後に前例のない全村避難をした山古志村。どんな生活が待っているのか多くの住民が不安を抱えていた。
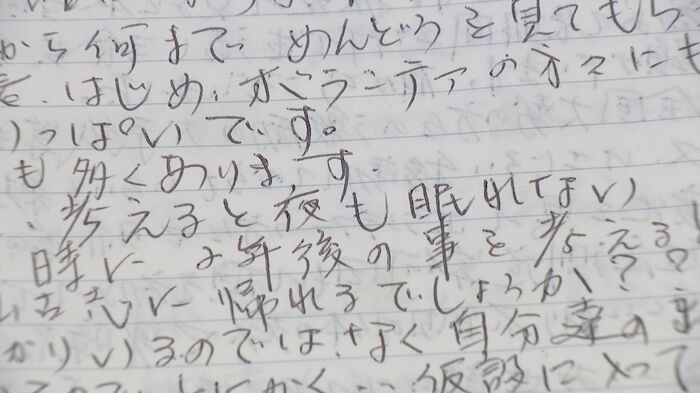
そうした中、長島村長は避難から約10日後…バラバラに避難所に散らばっていた住民たちを集落ごとに再編した。地域のコミュニティを維持し、少しでも不安を取り除くための対応だ。
その避難所に置かれ、当初は不安の言葉が目立ったノートも集落の仲間と支え合いながら同じ時間を重ねる中でふるさとへの思いを募らせていく住民の様子が伺える。
山古志の復旧・復興目指す中…“村を出る”議論も
長島村長は毎日欠かさずノートを確認し、住民と気持ちを合わせるよう一つ一つメッセージを返した。
そして、長島村長は「私たちはあのふるさとを愛しています。そして、先祖から受け継いだあの地に帰りたいと願っています」と決意を語っていた。

その後、仮設住宅に入っても何度も話し合いを重ねた住民たちは「帰ろう山古志へ」というキャッチフレーズの下、山での生活を取り戻すことを目指した。
一方で、長島村長とともに復興業務にあたった元山古志村幹部の青木勝さんには同時に「ある懸念」もよぎっていたという。
「“帰ろう山古志”でそれはやりますよ。だけど、山古志に金をかけるのももったいないから、みんな出ればいいという議論が当時からあった。我々が一番恐れたのは、そういう議論が主流になったら山古志の復旧・復興はないという、ジレンマみたいなものはずっとあった」
地震から20年…迷いながらも下した決断に「悔いはない」
あれから20年…今年発生した能登半島地震でも中山間地の復興のあり方が問われる中、山古志の人口は約720人と地震前と比べ、3分の1に減っている。

この日、竹沢集落では恒例の夏祭りが開かれ、神輿が地域を回った。
参加する住民は年々減っているものの、地震をきっかけに毎年、ボランティアとして訪れている東京の学生が今年も参加。
学生は「近隣同士のつながりがすごく残っている。一人ひとりのパワーがすごくある地域だと思ったし、来てよかった」と話す。

復興を遂げた地域に魅力を見出し、様々な形で関わる人がいる。そして今、住民からはふるさとに戻った選択を後悔する言葉は聞こえてこない。
星野サツ子さんは「ここでしか生きる術を知らなかったのもあるかしれない。ここだったらなんとか生活できるなと。なるようにしかならない。そう思っているだけ。自分の考えでしたことには悔いがない」と話し、吟二さんも「かえって地震後は団結力が強くなったのではないか。前向きになって、一日一日を楽しみながら過ごしている」と語った。

山古志で暮らす住民には20年前、迷いながらも最終的に自分たち自身で考え、決断したからこその思いがあった。
(NST新潟総合テレビ)