G7広島サミットでも焦点の一つになったAI(人工知能)。その活用がいろいろな場面で議論されている中、東洋大学の情報連携学部(INIAD)は、OpenAI社の「GPT-4」(チャットGPT)を活用した教育システムを開発し、新学期から全学年で導入している。
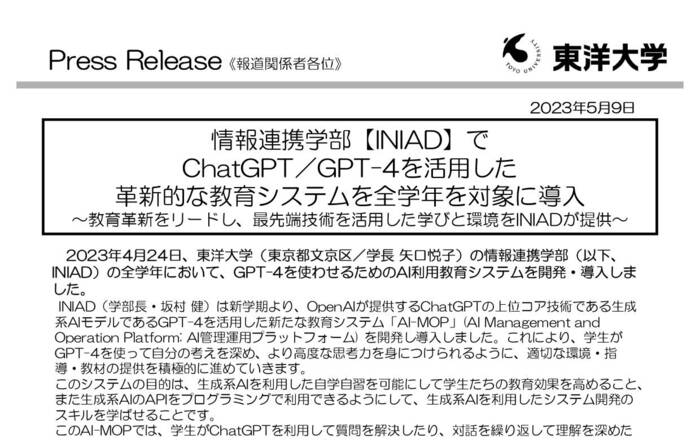
「GPT-4」へのアクセスは、学生と教職員の全員が連絡などに普段から使っているコミュニケーションツール「Slack」に設けたボットを通じて行われる。学生はAIとの対話を繰り返して理解を深め、研究や課題に取り組むことができるという。
このシステムでは、個人や部門単位でのAIの利用量などの管理が可能で、また通信内容はOpenAIのサーバーで保管されない(学習にも利用されない)そうだ。さらに、今後登場する新たな生成系AIも同じように取り込めるとのことだ。

AIを使用前提で課題提示。その代わりAIとの対話ログを提出
質問したらAIが答えてくれるのであれば、簡単にレポートなども完成でき、便利そうだ。そんな生成系AIについては、一部からは文章力や思考力への影響を懸念する声もあるが、東洋大ではどんな課題をだしてAIを活用しているのか? なぜ自由に使える環境まで用意したのか?
INIADの坂村健学部長に聞いた。
――学生が生成系AIを使うことを認めるだけでなく、自由に使える環境を学校側が用意したのはなぜ?
大きく分けて3つの理由があります。
1. 学生間のAIアクセスの格差を解消すること。
ChatGPTは、GPT-4、GPT-3.5-turbo、GPT-3の3つのAIモデルを選んで使えます。
無課金ではGPT-3.5モデルしか使用できず、有料モデルを使えるかどうかで回答の質が大きく変わるため、単に利用を認めるだけでは、課金した学生とそうでない学生の間で不公平が生じる可能性があります。
そのため、INIADでは、全員が課金しなくても同じ有料モデルを使用できるようにするための環境整備を行いました。
2. 学生にAIを使った課題を出しやすくすること。
例えば、学生が書くレポートの課題は、コンピュータ関係だけでなく、INIADで教養として教えている哲学のレポートが含まれます。
去年の哲学の課題をGPT-3.5に与えた場合、学生の半数以上の出来でしたが、GPT-3.5-tarboでは上位20%、GPT-4ではほぼ最高レベルの評価になりました。
AIの利用が個人的に可能な状況であれば、誰でも課金すればAIを利用することができます。AIの利用が禁止されている場合でも、使いたい人は隠れて利用することになり、そうなると「正直者が損をする」ということになります。
そこで、むしろ「AIを使用する前提で課題を提示する。その代わりに、AIとの対話ログを提出してください」という方針に切り替えました。このため、対話ログを簡単かつ確実に課題提出できる機能も必要であり、この機能も本システムで実現されています。
3. 利用を管理できるようにすること。
GPTの利用料はトークン(料金の単位)の消費量によって変わります。特にプログラミングでAPIを使う場合、APIを呼び出す部分が無限ループしていたりすると、気づかないうちに数十万円の出費になってしまった例も聞いています。
本システムを通じての対話では、トークンを浪費しないように使用する方法を学ぶことができます。毎回の対話で消費するトークン数が表示され、学生、教員、職員、研究室などにそれぞれIDとアカウントが与えられ、最大利用トークンの制限をそれぞれの必要に応じる形でかけています。
――学生にGPT-4を使用させることに反対意見はなかった?
INIADのポリシーは、新しいことを否定から入らないことです。そのため、「カリキュラムや教材の書き換えや課題を考えるのが大変だ。急いで始めないと」というような声はありましたが、反対意見はまったくありませんでした。
――AIを安全に使うための対策は?
OpenAIの規約で、将来の学習に使わないしログも取らないとしているAPIのみを使うので、学生の設定にかかわらずプライバシー上の問題はなくなっています。あとは、上にも書いたトークン利用料の制限に対応しているという点です。
また、何らかの形で望ましくない利用をするアカウントは、発見したら対話ログを確認して凍結することも可能です。
「なぜ人を殺してはいけないのか」AIと対話する課題も
――AIを活用するこれからは大学での「課題」はどのようなものになる?
レポート課題の例として、実際に学生に出したものが下記です。
1. 「なぜ人を殺してはいけないのか」について、GPTと4回以上のやり取りをして、課題に関係するユニークな検討を行い、その討論過程の対話ログを提出せよ。
2. 現代のコンピュータの設計は多くの「階層化」が必須となっています。その必要性を、具体的な階層を例に、より深く理解できる説明文をGPTと3回以上対話してまとめ上げて、その過程の対話ログを提出してください。
3. GPTにハルシネーション(編集部注:AIがもっともらしいウソをつくこと)を起こさせそうな質問を5つ考えて入力し、その質問と実際の答えの対話ログと、ハルシネーションが起きた理由の考察をまとめて提出せよ。
課題は基本的にAIを使わせ、対話ログを出させます。すると、最終的な回答よりも、むしろどのようにしてその回答にたどりつくかの、聞き方や対話の仕方に学生により大きな差が出て、個人の能力を見ることができます。
「AIを使わない優秀な学生」はいない
――楽してAIに書かかせたレポートはどう見抜く?
上記のように「AIとともにレポートを書く」ことが大前提なので、特に「AIが書いたレポートを見抜く」ようなことはしません。
――AIを使わない優秀な学生が圧倒的不利になるのでは?
INIADでは「AIを使うように」と全員に指導しているので「AIを使わない優秀な学生」というのはいません。金銭的な理由などで「AIを使えない」学生もいないように今回の環境を提供してますし、さらに優秀な学生ほどAIを使うことに積極的です。
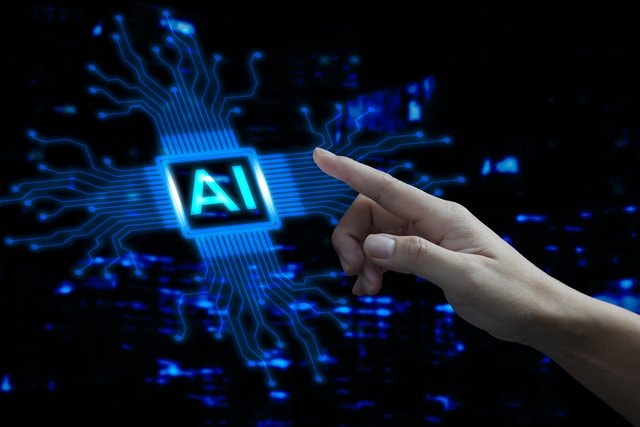
AIを使えばどんな問題も簡単!…と思っていた人も、課題を見たらそう簡単にはいかないことが分かっただろう。今後はAIモデルを増やす予定だということだが、学生にはAIを上手に活用して勉学に励んでほしい。






