アメリカに憧れたヴィム・ヴェンダース監督。しかし、ハリウッドのシステムに馴染めずアメリカに別れを告げ、恋した場所は日本。東京で一番好きな場所はパチンコ店だと言う。そこに禅的なつながりを感じるそうだ。
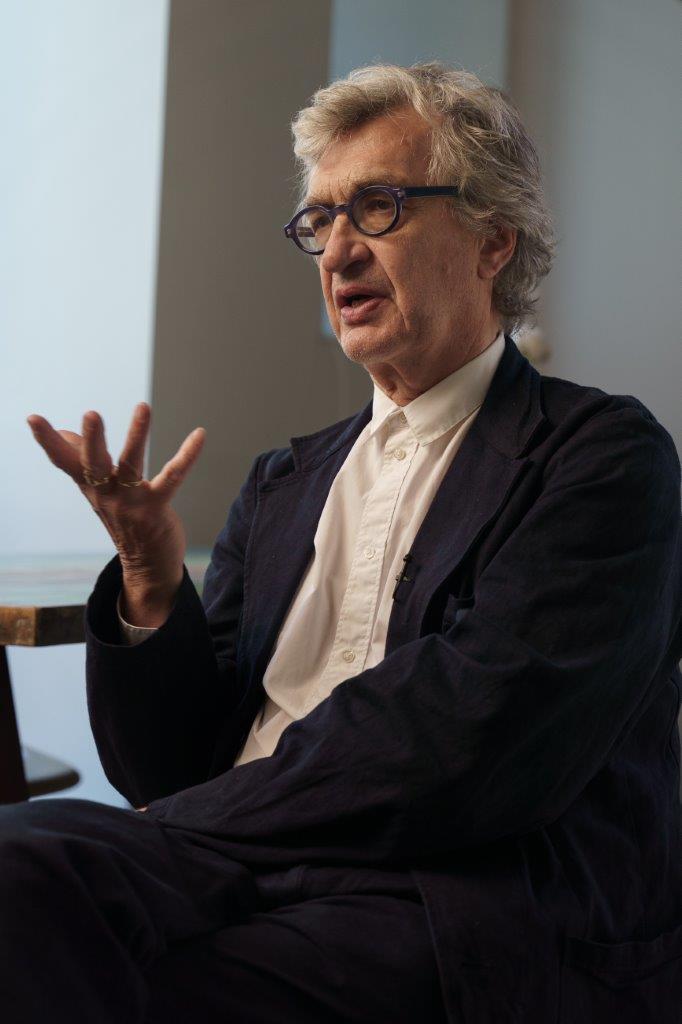
パチンコは禅、映画館であり教会でもある
ヴェンダース監督が敬愛する小津安二郎。敬愛するあまりオマージュとして作ったのが『東京画』である。小津映画の常連、笠智衆さんなどとの出会いを通じて、現代の東京の画(イメージ)に小津的なるものを投影しようと試みている。ヴェンダース監督は自身によるナレーションの中で「無、空虚が現代を支配する」と日本を評しているが、それはパチンコ店のことだと明かしてくれた。

ヴィム・ヴェンダース(以下、WW):
パチンコには中毒的に、はまっていました。実は、結構勝っていたんですよ。左右に座っているお客さんが「この外人、なんで勝っているんだ」とすごく驚いていました。
パチンコと私は禅のようにつながっているように思えました。パチンコ店は自分の抱えているストレスや社会での立場を忘れさせてくれる場所です。大音量の音楽に囲まれ普段の生活から隔離されています。そこに存在するのは自分自身と機械だけ。日常から解放されリラックスするという意味では、誰しもそういう場所が必要だと思います。
禅という言葉を使いましたが、日本に来ないと分からないことで、海外の人の目には不思議な光景ですよね。暴力的な音の洪水、点滅する光の刺激。本当にカオスです。そんな中でなぜリラックスした状態に達することができるのか。私にとっては、ある意味、神の賜物と感じたものです。

WW:
またパチンコ店は、映画館や教会に近いと思います。社会的な場所として、いつも混み合っています。人々は密に寄り添い、同じものを信じ、同じ作業をする共通の場所ですね。
今回日本に来て、気づいたのですが、パチンコ店は減っていますよね。コロナ禍でソーシャルディスタンスを守るため、お客さんが減ったせいかと思いますが。
実は何軒かパチンコ店に立ち寄ってみました。パチンコ台の機械はどれも目新しくて、取りあえず試しにやってみましたが、あまり入りませんでした。パチンコへの執着は消えたかもしれません。

戦後(太平洋戦争のこと)日本でパチンコが大流行した時代、小津は『お茶漬の味』(1952年公開 松竹作品)を世に送り出した。そして、主人公にパチンコ玉を打つことの幸福感を語らせている。それを何度も見たヴェンダース監督は小津の心に追随し、パチンコに病みつきになったのではないか(パチンコ店店主を演じるのが笠智衆さん)。
ベトナム戦争終結(1975年)後、挫折と苦悩に苛まれるアメリカが世界の盟主ではなくなった1980年代。ヴェンダース監督の興味の対象が日本にシフトした当時の心境を聞いてみた。
日本は居心地が良い
WW:
あの頃、東京に来ることは、私にとって未来に向かって来るイメージでした。日本の前はアメリカが世界の未来を象徴していたと思うのです。アメリカにも何年か住みましたが、日本に通うようになって未来を考える場所がアメリカから日本にシフトしていきました。
日本に来ることは先進的な場所に来ることだと思っていましたが、一つの例としては機材、カメラというものがあります。当時はまだデジタルはなかったですが、ハイスペックなアナログ、アナログHiエイトなど、他では手に入らないものが日本にはありました。だから、80年代、90年代は2年おきに日本に戻ってきてチェックしていたのです。

WW:
またテクノロジーという意味だけでなく、日常生活においても、ある種ユートピア的なところが日本にはありました。
それは、コモングッド(common good)と言われるものです(筆者註:社会の構成員全員が共有する価値観で、他の人に対する義務でもある。自分の利益にならなくても、みんなの利益のために自発的に守るべきものがコモングッド。一番近い日本語は「良識」「公益」)。
アメリカ、ヨーロッパでは他人のためではなく、自分のために行動するという意識が勝っていますが、日本人は他人を思いやって行動しています。それは電車とかレストランなどの公共の場所で見受けられ、私はとても居心地が良い社会がそこにあると思いました。
そのことは2011年に来日した時にも思いました。ピナ・バウシュ(筆者註:ドイツ人舞踏家・振付家)のドキュメンタリー映画上映のために来日した時です。上映会で福島にも行きましたが、東日本大震災でショックを受けているにも関わらず人々は他人を思いやることを最優先にしていました。連帯して乗り越えようという態度が感じられました。これが他の国なら、人々の間に対立構造が生まれたことでしょう。
私は3週間前(9月下旬)に東京に帰ってきました。皆さんが日常的にマスクをしているということで社会は変わったように見えますが、他人を思いやることは変わっていません。コロナを他人に移さないためにマスクをする。規律正しく清潔で、居心地が良い場所だと私は再確認しています。
トイレが禅になる日
パチンコの話に戻ると、パチンコは日本を描く際に欠かせない存在として国内外の映画に映し出されてきた。松田優作さんがハリウッド進出を果たした『ブラック・レイン』(1989年)、ソフィア・コッポラ監督の『ロスト・イン・トランスレーション』(2003年)など枚挙にいとまがない。
現在、ヴェンダース監督は東京・渋谷区内に設置された公共トイレが舞台の映画を製作中である(タイトル未定、2023年公開予定)。トイレに思いをはせる監督はこう語る。

WW:
日本ではトイレの文化が非常に深いところにあると思います。使う以上に、そこは休むところであり、リラックスするところ。そして非常に綺麗です。ヨーロッパの(公共)トイレは苦痛でしかありません。ロンドン、パリ、ベルリンのトイレに行ってみて下さい。極めて不快です。
トイレは誰もが行くところですが、他人を思いやる場所であり、禅的なことを感じます。
私の新しい“中毒”は、公共トイレの美しさなのです。

パチンコに代わり、東京を描く存在としてトイレが海外の映像作品に登場する日も近いかもしれない、と筆者は思う。
拙稿ではヴェンダース監督との対話を通じ、禅的なるもの、小津的なるものを少しだけ探求してみた。アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズの考え方の根底には禅があったことは有名な話だが、ビートルズも一時期、東洋哲学に傾倒していた。いわゆるオリエンタリズムというものは、実際のところ、西洋の芸術家たちの心にどう響いているのだろうか。
ヴェンダース監督の『東京画』では、笠智衆さんが小津の墓をお参りする姿を見ることができる。そこは禅寺の円覚寺。墓石には「無」の一文字が刻まれている。
「無が現代を支配する」と語ったヴェンダース監督が初めて日本に来たのは1977年。そのときの思い出を聞いてみた。

WW:
ゲーテ・インスティトゥートによるドイツ映画回顧展での来日です。数日間、自分の時間がありました。北鎌倉で初めて小津の墓をお参りし、何かを感じました。大阪にも1日いました。それでまた少しは知ることができました。その後は、とにかく日本に帰りたいという気持ちでした。

大の親日家であるヴェンダース監督。初来日の瞬間から、日本人の他人を思いやる気持ちに惹きつけられていたのだと思う。輪廻、無常といった東洋的コンセプトと重なる「無」の神髄はこれからのヴェンダース作品にどう映し出されるのか。楽しみである。
ヴェンダース監督と共に世界文化賞を受賞したジュリオ・パオリーニさん(絵画部門)、アイ・ウェイウェイさん(彫刻部門)、妹島和世さん+西沢立衛さん/SANAA(建築部門)、クリスチャン・ツィメルマンさん(音楽部門)の皆さんをフィーチャーした特別番組が放送予定である。
「第33回高松宮殿下記念世界文化賞」
11月16日 24:30-25:00フジテレビ(関東ローカル)
12月3日 16:25-16:55 BSフジ
また監督の受賞を祝い「ヴィム・ヴェンダース 第33回高松宮殿下記念世界文化賞 受賞記念Blu-ray上映会」(主催:記念上映実行委員会)がこれから来年にかけて全国で開催予定である。





