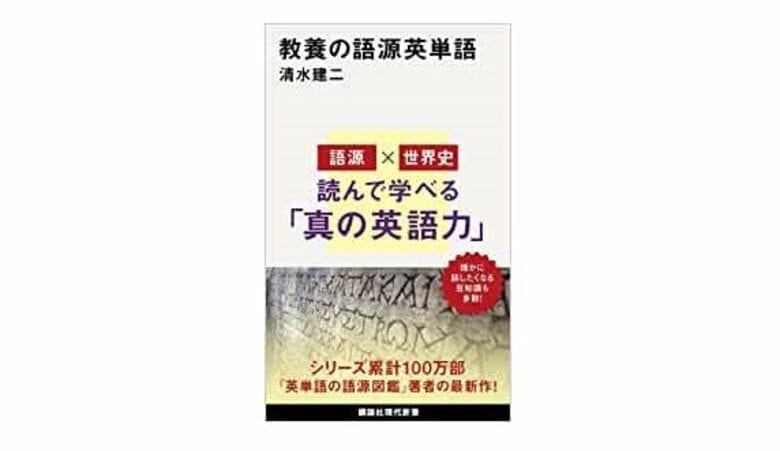インドには古代から伝わる「チャトランガ」と呼ばれるボードゲームがある。2人制と4人制があるが、前者は欧米の「チェス」の原型で、ルールも見た目もよく似ている。
マス目はともに8×8の64マス。駒は立体のフィギュアで敵・味方が色分けされている。
たとえばチェスのナイトは騎士を表すが、駒は馬の頭部をかたどっている。「チャトランガ」にもアシュワ(馬)という駒があり、動き方のルールが全く同じなのである。駒(馬)の現在地から2マス前進、その左右両隣のどちらかのマスに移動。これを上下左右合わせて8か所に一回だけ移動可能なのである。
将棋をする人なら、桂馬(これにも馬という字が使われている!)と同じと思うはずだ。桂馬は前にだけしか進めないが、将棋もまた「チャトランガ」の末裔なのである。
インドから日本に伝わる間に、当然中国や朝鮮半島を経由してきたが、いずれの国でも、駒を敵・味方で色分けすることに変わりはなかった。
ところが日本に到達するや、日本人は捕獲した相手の駒を自分の手駒として使うことを思いついたのである。そのため敵・味方の駒の色分けは都合が悪い。そこで漢字と五角形の頭の鈍角が示す方向で、駒の所属を見分けるようにしたのである。
この工夫だけで、将棋はチェスと比較してはるかに複雑なゲームに進化することになった。オリジナルな創造という「特許的才能」には欠けるが、舶来のものに創意工夫を凝らして、その文物に磨きをかけるという日本人の「実用新案的才能」は、すでにこの時代から発揮されていたのである。
この相手の駒を自陣の兵として使うといった発想は、周りを異民族に囲まれた地域ではなかなか思い浮かばなかっただろう。彼らは敵と味方を峻烈に色で分けるという環境下で生活していたのである。
一方、日本は周りを海に囲まれ、それほど異民族に対する警戒感を持つ必要はなかったし、むしろ古代から技術を持った渡来人を優遇してきた。有史以来、日本が外国勢力に占領されたのは「マッカーサーの2000日」だけなのである。ある意味、恵まれた国である。
英単語の語源を学ぶ
さて今回の取り上げるのは『教養の語源英単語』(清水建二 著・講談社)である。
「チェス←チャトランガ→将棋」と同じように、インド・イギリス・日本を結ぶ線を英単語を通じて面白いように浮かび上がらせてくれている。
たとえば「ドナー」(donor)という英単語がある。臓器移植手術を行う際に、臓器を提供する人の意味で、いまでは日本語になったといっていい単語だが、本来は「寄贈者・施主」という意味だった。
そしてこの「ドナー」という単語は、「横町の若だんな」のあの「旦那」と語源が一緒なのである。古代インドの文章語であるサンスクリット語で僧侶への「布施・施し」のdana(ダーナ)が共通の語源で、西に伝播して最後にイギリスで「donor」となり、日本には仏教用語として中国経由で入ってきた。
元々は語源通りに「お布施をする人」の意味だったが、やがて商家の主人を意味するようになったのである。「旦那」はローマ字表記すると「danna」。「donor」に似ていることがよく分かる。
余談だが、「旦那様はドナー」というタイトルの中国のラブコメディがある。内容もタイトルと一致しているようだ。日本語翻訳者がこのことを知っていて、このタイトルにしたのならクリーンヒットだし、偶然ならまさに奇跡的だ。ちなみに原題は「奈何BOSS要娶我」(「なぜボスは私を娶(めと)る必要があるの?」というほどの意味か)英語タイトルは「Well-intended Love」で「ドナー」も「旦那」も出てこない。
インド・ヨーロッパ祖語
さて、仏教の伝播とともに「旦那」が日本に入ってきたのはわかるが、なぜ仏教国でもないイギリスに伝わったかというと、実は言語学的に英語とインドの言語はともにインド・ヨーロッパ語族と呼ばれる系統に属しているからである。
この語族は英語・ドイツ語・フランス語などのヨーロッパの大半の言語とペルシャ語やヒンディー語などの西アジアから南アジアにかけての広大な言語地図を構成する。(ちなみに日本語はアルタイ語族説をはじめ様々な語族との関係が指摘されていて、確定できていない。「孤立語」の可能性もある)
さらに言語学者たちは、インド・ヨーロッパ祖語(印欧祖語)というべきものをウクライナから南ロシア(いま世界中が固唾を飲んで見守っている地帯だ)の人々が話し、それが次第に方言として民族ごとに分離し、現在の言語地図になったのではないかと考えを持つようになった。ただ印欧祖語はあくまでも仮説であって、現在は否定的な研究者が多いようである。
しかし、著者の清水氏は「『バベルの塔』の話を全く荒唐無稽な話として片付けることはできない」として可能性に含みを残している。
「バベルの塔」の話とは、旧約聖書の創世記に描かれたものだ。人々が天にも届くバベルの塔を建造しはじめ、それを見た神が人々の傲慢さに怒り、人間が同じ言葉を話しているから作業がはかどり大建築が可能になったとして、互いに相手の言葉が分からないようにした上で、人々を各地に散らしたという神話である。
もし「バベルの塔」の話がある程度の事実を含んでいるのだとすると、人類は共通の言葉を話していた時代のことを数千年にわたり語り継いだことになるが、それはそれでロマンを感じさせる仮説ではある。
2000余りの英単語の由来と歴史的背景
さて、この本のキャッチコピーは「語源 × 世界史 読んで学べる『真の英語力』」である。英単語の語彙増強を目指すことを考えて書かれた本だ。
だが各章のタイトルを見てみると、「英語の歴史とその変遷」「ギリシア神話の世界観」「古代人の宗教観と世界観」「古代国家の社会制度」と、何やら西洋史の本、しかもかなり大部の書籍のように思える。
しかしこれは300ページ余りの新書なのである。そのコンパクトな中に、2000余りの英単語の由来と歴史的背景が記されている。とりわけ、ギリシア神話をはじめとする古代の神話から生成した単語が多いのが目につく。
また言葉は歴史を伝える「化石」のようなところがある。たとえばノルマンコンクエスト(1066年 フランス北部のノルマン公がイギリスを征服した戦い)以降、英語に数多くのフランス語が流入し、これによって動物名とその動物の肉を表す単語が分離した。
豚/豚肉(pig,swine/pork)、牛/牛肉(cow,bull,ox/beef)、羊/羊肉(sheep/mutton)などで、後者の食べる肉を表すのはいずれもフランス語の借用だ。つまりイギリス人が飼育した家畜をフランス人が食べるという構造が示されているのである。これは支配層・被支配層が作り上げた言葉の二重構造の典型とされている。
こういったことが簡潔にして要を得た文章で記述されていて、単なる英単語集としてではなく、歴史書として読んでも実に面白く読める一冊なのである。
【執筆:赤井三尋(作家)】