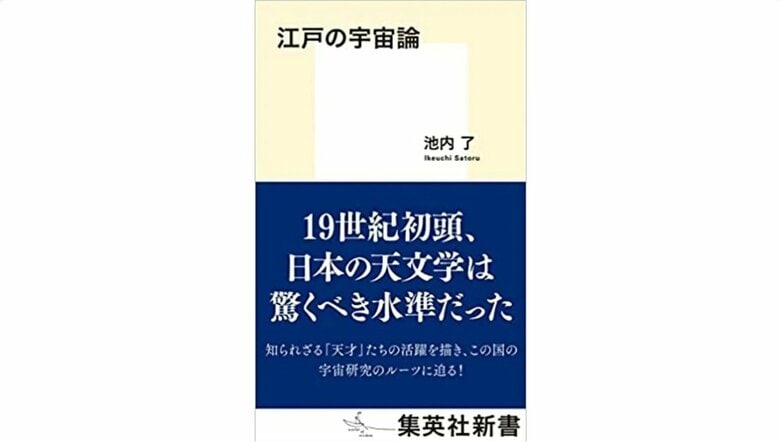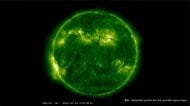江戸時代の一般的な庶民は、この世界(宇宙)をどのように考えていたのだろうか。大地や海が無限に続いていると考え、無限は考えてもわからないので、そこで思考停止していた可能性が高い。あるいは、僧侶などの知識人は仏教に基づく「須弥山」世界を思い描き、儒者もまた朱子学の理論から林羅山のように地球は平らで、太陽が沈んでは出る宇宙を考えていたようだ。いうまでもなく、いずれも科学的根拠はない。
ところが、である。今回紹介する『江戸の宇宙論』(池内了 著 ・集英社新書 )を読めば、江戸時代も後期に入ると、地動説を十全に理解したうえで、さらに独自の宇宙観を提示した人々がいたことにちょっとした感銘を受けるだろう。
元・オランダ語通訳の宇宙論学者
池内了氏は「泡宇宙論」など科学の最先端を研究する宇宙物理学者だが、一般向け科学書も数多く書いている人で、物理学と人文科学の橋渡し的な著作が多いのが特徴だ。広範な知識がなければできることではない。
著者が選んだ江戸期の「宇宙論学者」は3人。司馬江漢(しばこうかん)と志筑忠雄(しづきただお)と山片蟠桃(やまがたばんとう)である。このうち、絵師として有名な司馬江漢はすでに『司馬江漢「江戸のダヴィンチ」の型破り人生』(集英社新書)にまとめられていて、今回の本はあとの2人について記したものである。
1人目は志筑忠雄。本職は「長崎通詞」、オランダ語の通訳であった。当然、蘭語に堪能でヨーロッパの最先端の科学などにも最初に接することの有利さもあるが、著者のいうように何が重要かを見分ける選択眼がなければ、ただの通訳者で終わってしまう。そして志筑忠雄がいまに名を残しているのは、その選択眼と恵まれた出自があってのことだった。
志筑忠雄は長崎に生まれ、オランダ通詞の志筑家に養子入りしたが、「口舌不得手」を理由にかなり若くして通詞を辞職し、それ以降は蘭学の研究・翻訳に没頭した人だった。忠雄の実家、中野家は三井越後屋(三越の前身)の長崎出張所長を務めていて、長崎での越後屋の反物の扱いを一手に引き受けていたというのだから、彼にはそれが許される経済的環境があった。
宇宙論にかかわる志筑の業績は、ニュートン力学の教科書のオランダ語訳を翻訳した『暦象新書』である。この分野での本邦初の書籍ということもあって、志筑はさまざまな物理用語を作り出している。日本にそういった概念がなかったのだから他に手だてがない。引力・求心力・遠心力・重力、そして真空も彼の造語である。また、天動説・地動説も志筑の造語だが、これは日本独自の言い方で、ヨーロッパでは太陽中心説(Heliocentrism)という。面白いのは以下のくだりである。
「よく読めば志筑は地動説に旗を上げているのだが、それでは幕府や当時の人々の常識である儒教思想に基づく天動説に歯向かうことになるので、トーンを弱めて曖昧な表現に終始している」
コペルニクスやガリレオのように、志筑もまた、科学の真実をはっきりと表明することができなかった。権力の権威を損ねる行為に対して下される制裁は、ヨーロッパでも徳川幕府下でも同じだったのである。
さて、この宇宙論学者が池内氏を驚かせたのは、志筑本人の自説である「混沌分判図説」である。これは太陽系形成についての考察で、物質の塊の収縮が遠心力で止まるが、外部から降り注ぐ物質でさらに重力(求心力)が強まって、いっそう収縮する過程を述べている。著者はこの説に対して、
「太陽系のみならず、銀河系の形成に適用できるアイデアであり、宇宙の構造が万有引力の下で進化していくことを具体的に描いたという点で画期的」
と絶賛し、その物理学的センスが印象的だと述べる。
「豪商の番頭」の宇宙論
もう1人の山片蟠桃も経済的に非常に恵まれていた人だった。播磨国(兵庫・高砂市)の人だが、米問屋から大名貸しするほどにまでなった、大坂(大阪)の豪商「升屋」の番頭だったのである。
しかもただの番頭ではない。升屋の創業当時から蟠桃の実家である長谷川家と協力関係があり、蟠桃はその多大な貢献から升屋から一代限りの「親類並」に取り立てられ、主家の山片姓を名乗ることが許されたのである。
蟠桃という名は、本職の「番頭」にひっかけたものだが、和歌山や福島で栽培されている桃の種名である。桃好きの中国でも別格の存在であるらしく、不老不死など多くの伝説が残っている。
蟠桃は志筑の『暦象新書』も読んでおり、地動説が正しいと考えたようだ。
「地動説のことを言っておきたい。自分のいる地球が動くのだから、家屋が崩れ、棚の上にあるものは落ちてくるはずと思うだろうが、そうではない」
としている。
もちろん『暦象新書』を読んでいるので慣性の法則を知っていたし、地球より大きい太陽や木星、土星が動くと考えるのはおかしいと主張している。
また、蟠桃は大坂の医者で天文学者でもあった麻田剛立から天文学を教わり、「ソングラス(サングラス)で太陽を詳しく観る」など天体観測をし、望遠鏡で月の表面を観察して「さまざまな模様が見えるのは山谷河海で、そこに世界がある」と記している。そこから論理を組み立てていって、次のように結論づけている。
「地球に人民・草木があることから推定すると、他の天体であっても、多かれ少なかれ地球に似ていると考えられ、どこにも土や湿気があるだろう。(略)すると当然虫が生まれ、虫がいれば魚介・禽獣が誕生することになろう。こう考えると人民も必然的に生まれる」
これは、現代の私たちとほぼ同じ考えではないだろうか。宇宙人はいるが(地球人もまた宇宙人だが)、あまりにも遠すぎて接触できないという考えだ。
太陽系から最も近い恒星、ケンタウルス座アルファ星ですら約4.37光年の距離があり、光速が秒速約30万キロということを考えれば、遭遇するのは不可能だろう。電波で通信することは可能だが、往復で9年近くかかる。そして今のところ、宇宙から意味のある電波(搬送波といって電波に音声や画像を乗せたもの)は受信されていない。それでも、気が遠くなりそうな大きさの宇宙であれば地球に似た環境の惑星があり、そういった太陽系以外の惑星も最近では見つかり始めている。ただそういった意味のある電波を受信したとしても、「ET(地球外知的生命)発見後の行動に関する議定書」というのがあって、国連などの機関がどう対応するか決めるまで、勝手に返事をしてはいけないことになっている。究極の安全保障策だといえそうである。
さて、著者は江戸時代の2人の「宇宙論学者」を紹介してくれたが、面白いのはその宇宙に対する考え方だけではない。
池内氏は彼らの宇宙論以外に、彼らがいた世界、つまりオランダ通詞や豪商の世界も実にきめ細やかに描写してくれている。
たとえば、『蘭学事始』や『解体新書』を著した杉田玄白は、通詞を「ただ暗記している言葉を使って通弁するだけ」と通詞を格下扱いしたり、山片蟠桃を扱った数章でも、江戸期の米相場や大名貸しの仕組みなどが実にわかり易く描かれたりしているのである。
江戸時代も晩期に入ると、これもまた裕福な商家の当主だった伊能忠敬が隠居後に江戸に出て、徳川幕府天文方の高橋至時の弟子となり、天文学や測量を熱心に学んだ。31歳の師匠に50歳の弟子である。知ってのとおり伊能忠敬のその熱意はやがて、日本全国を測量して回って完成させた『大日本沿海輿地全図』に結実することになる。
そう考えると、江戸時代のアマチュア天文学者は実に大したものではないかと思えてくるのである。
【執筆:赤井三尋(作家)】