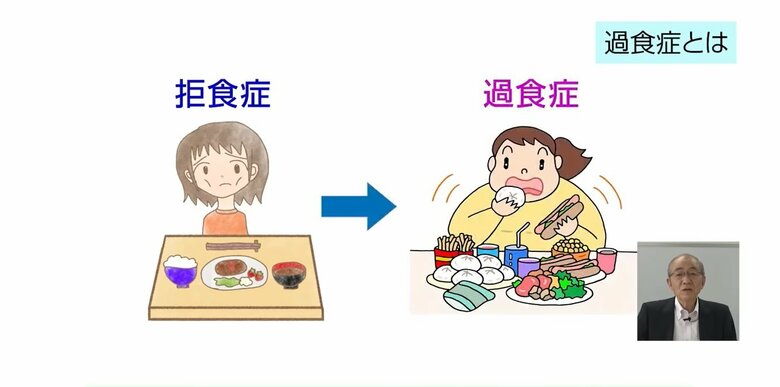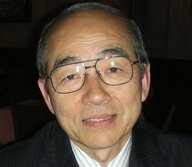シリーズ「名医のいる相談室」では、各分野の専門医が病気の予防法や対処法など健康に関する悩みをわかりやすく解説。
今回は心療内科の専門医、埼玉社会保険病院(現・JCHO埼玉メディカルセンター)名誉院長で日本摂食障害学会功労会員の鈴木裕也医師が、過食症について解説。拒食症から始まって過食症に移行する仕組み、精神的に不安定となり盗癖や強迫神経症を引き起こす場合もあり、困難を伴う過食症の治療や家族のサポートについても解説する。

過食症とは
過食症は、まず「摂食障害」という大きな病名がありまして、その中で「過食症」と「拒食症」に分かれています。
通常は拒食症から始まって、2~3年で過食症に移行するのが一番あるパターンです。
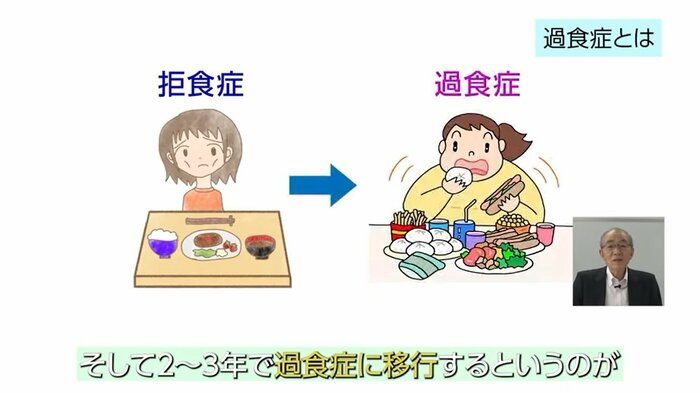
拒食症と過食症はもともと全く同じ病気で、症状が途中から「拒食」から「過食」に移行する疾患です。
最初は拒食症で始まって、食事を減らして痩せていく。自分の目的とするような体重まで痩せて、その間は落ち着いていますが、体の方が栄養分を要求しますし、脳に食欲をコントロールする場所があり、そこが「もっと食べなさい」という命令を出すようになります。
そうするとお腹が空いてついつい食べてしまう。そしてそれがきっかけで食欲が止まらなくなり、どんどん食べてしまう。
ただ、太りたくないということでジレンマに陥り、精神状態も混乱して、仕方なく食べるけど吐いたり、下剤をかけたりするようになります。

そういう状況が続くと非常に気持ちが不安定になり、もっと別の症状、例えば物を盗むとか、人付き合いができなくなり引きこもってしまうなどの色々な症状がでます。
また、強迫神経症といって何かを徹底的にしないと気が済まない、心配になる。出かけるときに鍵を閉めたかなともう一回確かめに行って、またもう少し行くと「さっき鍵を閉めに行って開けちゃったんじゃないか」といろいろなことで何度も何度も同じことを繰り返す。

それから手が汚れたら、一生懸命手を洗う、徹底的に何度も何度も手を洗ってカサカサになってしまう。こういった普通の人ではなかなか見られない、本人も嫌なんだけどそういう行動に出てしまうようないろいろな症状が出てくるので、過食症になると患者さんは非常に苦しむ状態に陥ります。
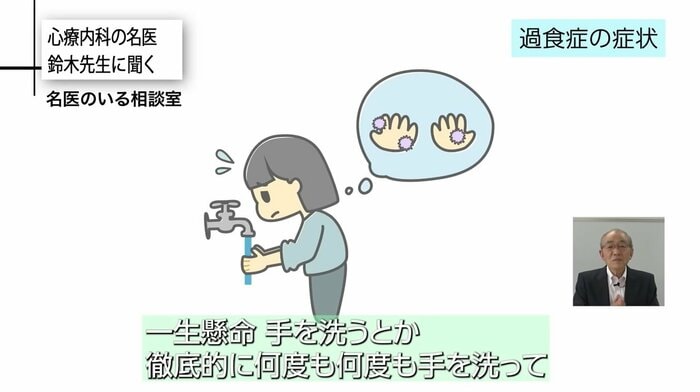
摂食障害になるきっかけと原因
最初は拒食症から始まり、2~3年で過食症に移行することが多いです。拒食症になると「痩せたい」ということになり、この痩せたいという気持ちはどこから来るのか?
この病気になりやすい年齢は、15~16歳から17~18歳ぐらいまでが多いです。
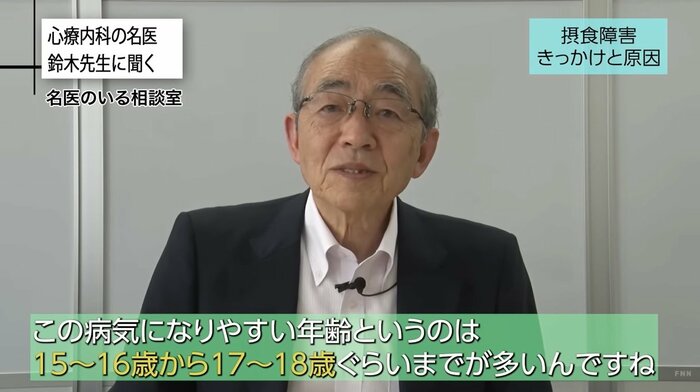
18歳、19歳になるともう大人です。15~18歳ぐらいまでは大人になる準備期間です。
そこでしくじりやストレス、いじめなどいろんなことがあると、このままでは社会に出て行けないと自信を失って大体9~10歳ぐらいの体重まで落として、思春期前、初潮前の体重に戻る。大人扱いされない、みんなから守ってもらえる年齢の体重にして、そういう姿で社会に復帰するというのが拒食症の痩せたいという願望です。
また、女の子のスポーツ選手の場合、体重制限のあるアイススケートやマラソンなどどんどん食べて筋力を付けてしまうと具合の悪いスポーツは空腹との戦いになります。

空腹を我慢しながら第一線の選手は厳しい練習をするので、その苦しみに耐えかねて、困ったな、もっとみんなにわかってほしい、守って欲しいという気持ちになって病気になってしまう。
モデルも厳しい食事制限の辛さによって社会から逃げる、守ってもらえる体重に戻ることが多いです。
真面目な女の子ほど摂食障害になりやすい
摂食障害は圧倒的に女の子が多いです。
学校の成績も良く、要求されたことを真面目に実行しようとするような良い子がなりやすいと言われています。また、色々な人と出会って色々な人付き合いの仕方を学びながら育った子は摂食障害になりにくいです。

子供の頃からたくさん遊んで、年齢相当の付き合いを広めて抵抗力をつけていく。
いろんな人に会って育った子は摂食障害にならない。そういう機会を失って勉強だけ一生懸命した子は、社会に出た時になかなかうまく行かないことが多いというのも原因の一つです。
日本でどのくらい患者さんがいるかというのは、全くわかっていません。
この病気を治す人が少ないことと、患者さんも受診しないことで、実際にどれくらい患者さんがいるかはわかっていません。ただ昔よりは増えています。社会がどんどん複雑になり、助け合う社会ではなくなって、競争し合う社会になったことが大きな原因だと言われています。
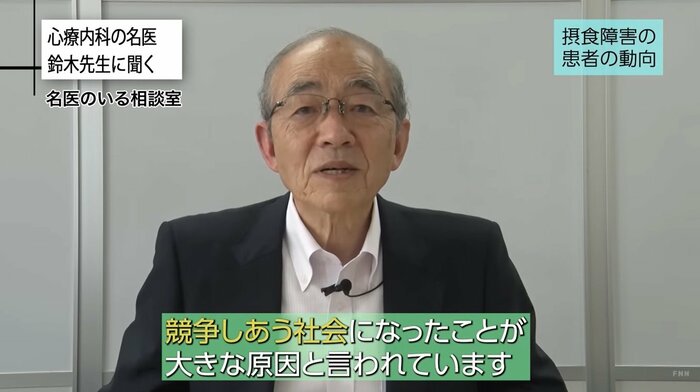
摂食障害にとって、コロナ禍の生活は大変良くないです。
生まれて小さい頃から大人になるという時のお付き合いが減る。小学生は今やっとマスクをつけて出掛けていますが、あまり友達と遊ばない。

もう少し高学年になると、ズームなど画面による授業になってしまい、人との付き合いが減ってしまい社会に出て行くための準備ができない。

学校で習う知識だけを詰め込んでも社会では活動できないということで、コロナ禍は患者数も増えますし、治療に当たっても人との付き合いの練習ができないということで、困難を感じているのが現状です。
過食症の治療
過食症の治療は薬が無いので、あくまでもカウンセリング、お話しです。大変治療に困難を伴う疾患ですが、根気よく話を聞いて、指導して、そして年月がかかります。2年、3年、5年、10年。30年、40年付き合っている患者さんもいます。
本人が成長しても暦がまた進んでしまうので、その暦の年齢にふさわしい自分にならないと自信を持って社会に出られないわけですので、長い付き合いで良い主治医を見付けて自分の内面を育てていく。
あと、家族療法というのもあります。本人がいくら頑張っても家族が理解してあげないと、食べたり、吐いたり、下剤をかけたりといった姿を見ると家族もつい叱ってしまう。
そうじゃなくて「辛いんだね」「大変だね」「もう少し我慢して頑張ろうね」といった声かけが大事。あくまでもサポートすることが治療上は必要です。
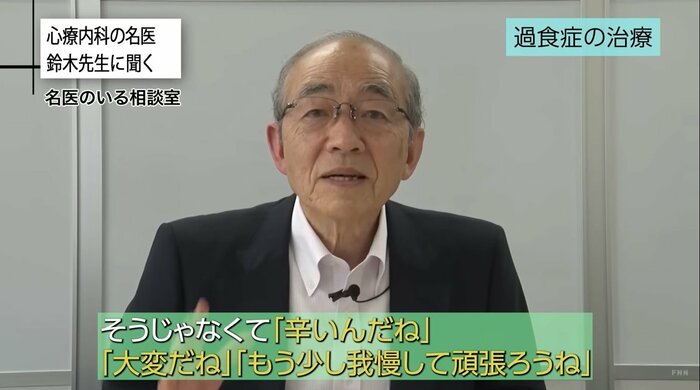
また、家族会といって、親だけを集めたり、親子を集めて教育をしている人もいるので、そういったのを利用するのも良いと思います。