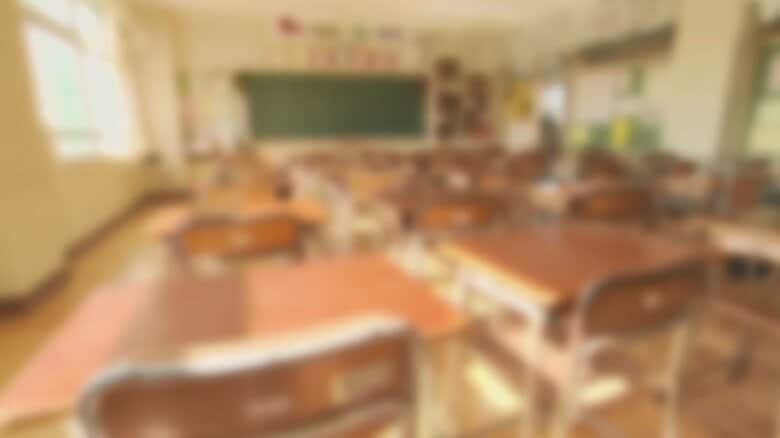いじめの認知件数は大幅に減少
文部科学省は、13日、2020年度の児童生徒の問題行動等について、全国の小・中・高校などの調査結果を発表した。いじめの認知件数は51万7163件で、過去最多だった前年度より9万5333件減った。

内訳は、小学校が42万897件、中学校が8万877件、高校が1万3126件、特別支援学校が2263件。いじめの重大事態は514件で、前年度の723件からは減ったものの、「引き続き憂慮すべき状況」とされている。
いじめの認知件数が減少した理由として、コロナの影響で、生活環境が変化し、子どもの間で”物理的”な距離が広がったことや、グループ活動や学校行事、部活動などで、様々な行動が制限されたことなどが挙げられている。
自殺した児童・生徒数は過去最多
一方、小・中・高校から報告があった自殺した児童・生徒の数は415人で、調査開始以来、最も多かったことが分かった。前年度の317人から大幅に増え、過去最多だった1979年度の380人も大きく上回った。
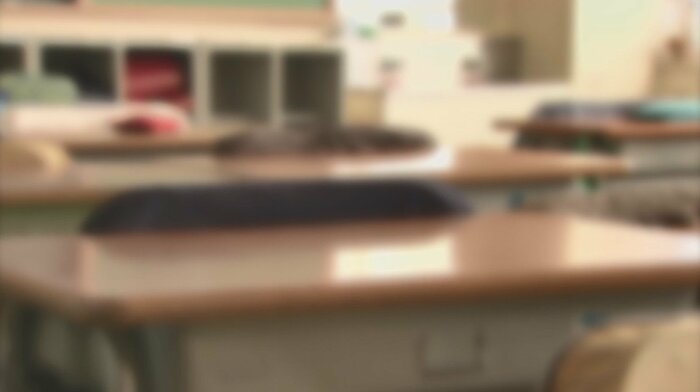
自殺の要因としては、これまで同様、「家庭不和」「父母等の叱責」「学業等不振」「進路問題」などが挙げられるが、「コロナの影響で増幅したと考えられる」という。文科省は、自殺予防教育などを徹底する方針だ。
新型コロナの影響は”長期欠席”にも
今回、文科省は、長期欠席とコロナの影響ついても初めて調査した。「感染回避」を理由に30日以上登校しなかった児童・生徒は3万287人にのぼった。小学校は1万4238人、中学校は6667人、高校は9382人だった。

小・中学校の不登校児童・生徒数は19万6127人と8年連続で増加。このうちおよそ55%は90日以上欠席していて、憂慮すべき状況だ。
コロナ禍で、学校生活に様々な制限がある中、友人関係を築くことが難しいなど、”登校する意欲”が湧きにくい状況にあったことなどが背景として考えられている。また生活リズムの乱れなども要因として指摘されている。