アジア外交攻勢が目立った3月
3月12日の日米豪印首脳テレビ会議(Quad)を皮切りに、ブリンケン国務長官とオースティン国防長官の訪日及び訪韓、オースティン国防長官の訪印、そしてアンカレッジにおける米中接触など、バイデン政権のアジア外交攻勢が目立った3月中旬だった。その後も、ヨーロッパに対して積極外交を展開したが、主要議題は中国だった。最大の懸案である新型コロナ・ウィルスをめぐる状況はまだ予断を許さないものの、ワクチン配給の見通しがたち、バイデン政権の公約でもあった国際主義の復権に向けて一気に舵を切ったといえる。
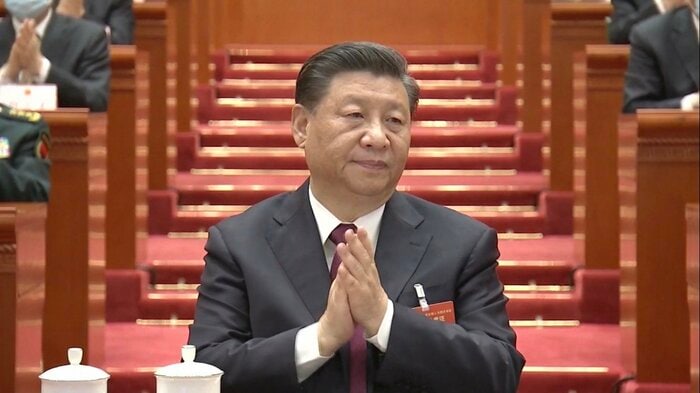
これは、2009年にオバマ政権が発足した時、米中関係をG2的な発想の上に構築しようと試みたことが日本側の記憶にはっきりと残っていたからだ。このオバマ政権による試みは早い段階で頓挫し、対中政策の見直しが行われるものの、この時の記憶が日本側の意識の中に刷り込まれてしまった形だ。バイデン外交は「オバマ2.0」になるに違いない、そうした疑念だ。
「シェイプ可能」だった対中認識の変化
対して、トランプ政権の対中政策は明白にタフだった。その基本姿勢は、政権高官によって繰り返し表明され、これまでの曖昧さが一切払拭されたかのようだった。トランプ政権以前のアメリカの対中政策は、中国の台頭にある程度影響を与えることができるということが前提になっていた。中国は、「シェイプ可能(望ましい方向につくり変える)」だという発想だ。しかし、トランプ政権は対中政策を「大国間競争」の文脈で捉え直し、中国を望ましい方向に導いていくという発想は放棄され、問題領域を特定し、徹底的に圧力をかけていくという方針に舵を切った。

この対中シフトはトランプ政権に固有のものというよりも、アメリカ人の意識の中で中国の存在が大きく変わったことの結果でもある。それは、1970年代初頭以来の、対中関与政策の挫折でもあった。それは、中国を国際社会に引き出すという姿勢で関与していけば、中国もいずれは「こっち側」にきて、「責任あるステークホルダー」になるという期待をもはや持てなくなったということである。
この対中認識の変化は超党派的なものであった。なにか単一のトリガー・イベントがあったわけではないが、この変化は2010年代半ばあたりからはっきりと確認できるようになった。しかし、その傾向的変化を躊躇なく受け入れたのがトランプ政権であったことも否定できないだろう。
対中政策に対する日本の懸念
バイデン政権になれば、認識レベルでは中国について厳しい評価を持ちつつも、実際にはまた曖昧な立場に回帰してしまうのではないか、それが日本のバイデン政権の対中政策に対する懸念だった。政権が発足してもその懸念は消えなかった。気候変動問題特使に任命されたジョン・ケリー元国務長官が中国との協調を模索するのではないか。国務長官、国防長官に任命されたブリンケンやオースティンは、「アジア・ハンド(アジア通)」ではなく、これがバイデン外交の問題意識を反映しているのではないか。これらの懸念が消えることはなかなかなかった。
この雰囲気がリセットされたのが、民主党随一のアジア・ハンド、カート・キャンベル元国務次官補が新設されたインド太平洋政策調整官ポストに任命されたあたりの頃である。日本では、キャンベルが政権入りしたから大丈夫だとの反応が目立ったが、そもそもキャンベルを調整官に任命したこと自体が、バイデン政権がもともと対中政策をどこにもっていこうとしていたのかを示していたとみるべきだろう。キャンベルは、ここ数年、一貫して中国に対してタフな政策を提示していた。
中国との「長期的な戦略的競争」
現在、バイデン政権は、中国との「長期的な戦略的競争」を前提にした対中戦略を組み立てようとしている。キャンベルはその取り組みを「複数の政権にまたがって遂行されるもの(multi-administration effort)」と述べている。その全容はまだ見えてこないが、方向性ははっきりとしている。それは意外に日本にとって厳しいものかもしれない。しかし、それは想定されていた、中国に対する「甘さ」に起因するものではない。
日本にとって、トランプ政権はある意味楽だった。アメリカが前面に立ち、とにかく中国との対決を推し進めていく。そこに前述したように曖昧なメッセージはなかった。トランプ政権は、日本が苦手な価値の領域にはあまり踏み込まず、中国との関係を力と力の対決として捉えた。日本にとっては、アメリカの方が日本より少々タフなくらいが、都合がいい。トランプ政権下における日米中の距離感はまさにそのような感じだった。
しかし、バイデン政権の対中政策は違う。まず、確認しておかなければならないのは、バイデン政権は中国との「長期的な戦略的競争」は避けられないと考えている点だ。まさにキャンベルの発言がそのことを確認している。しかし、アメリカ国民が場合によっては、今世紀中葉まで続くかもしれない競争に立ち向かう気持ちの準備ができているかといえば、それはできていないだろう。むしろ、長期的な対外介入に疲れ切っているというのが現状だ。トランプの「アメリカ・ファースト」が、多くのアメリカ人の気分と共振した所以である。
「ミドルクラス外交」とは?
そうだとすると、この「長期的な戦略的競争」を続けるためには、これがアメリカのみの戦いではないこと、価値観を共有する国々との共同の取り組みだということをとにかく強調する必要がある。バイデン政権は、アメリカの対外政策を語るとき、それがアメリカのミドルクラスにとって説得的なものでなければならないということを一貫して強調する。
ブリンケン国務長官が行った外交演説は「アメリカ人民のための対外政策」(3月3日)と題され、ジェイク・サリヴァン安全保障担当大統領補佐官は、カーネギー国際平和財団のプロジェクト、「アメリカの対外政策をミドルクラスのためのものにする」のメンバーでもあった。「ミドルクラス外交」は、バイデン外交の重要な軸であることは間違いない。では、果たしてミドルクラス外交とは何か?それを、対中政策に当てはめるとどういうことが言えるのか。

「ミドルクラス外交」とは平たくいえば、孤立主義的な衝動を回避しつつアメリカの「ミドルクラス」にも説得的な外交のかたちを模索するということであろう。戦略コミュニティが、専門的用語を駆使して組み立てた政策を、アメリカのミドルクラスにとっても説得的なものに組み替え、説明するということだ。そして、そうすることがアメリカの国際主義を維持するためには必要不可欠であるという発想に根ざしている。
それは、アメリカが国際的な責務を引き受けることに対する疑念が高まるなか、中国との「長い戦略的な競争」を引き受けるには、それが何もアメリカが単独で引き受ける責任ではなく、むしろ、多くの同盟国やパートナーたちと共にアメリカが参加する取り組みだということを強調する枠組みが必要だという認識だ。
政権発足後、早い段階で、QUAD首脳会合が行われ、日韓との2+2が実施され、菅総理の早期訪米が実現するであろう背景には、こうした構図を際立たせる必要があるためでもある。無論、同盟国やパートナーとの協調行動を重視するバイデン政権として、一緒に組む相手の意見を聴取し、あえて地域を訪れアメリカの立場の説明をしにきたということでもあろう。しかし、それは同時に、ミドルクラス外交を成立させるための、必要不可欠なパーツでもある。
「対等なパートナー」としての日本の責任
しかし、そうだとすると、日本はもはやアメリカが主導する枠組みについていくか、それに乗っかっていれば事足りるという状況ではなくなったということを示している。日本が、中国との「長い戦略的な競争」で何を引き受けるのか、それを今まで以上に積極的に示さなければいけなくなったということだ。これに答えられなければ、日米同盟は厳しい局面に立たされる。

バイデン政権は、同盟国として「対等なパートナー」であることを求めてくるだろう。日本は、これまでそれを希求しつつも、避けてきたところがある。だが、現今の安全保障環境下で、それを避けることはできないだろう。しかし、「対等なパートナー」は当然のことながら、より大きな責任を引き受けることでもある。「対等なパートナー」は、アメリカの後をついていくのではなく、常に併走し、時として先に踏み込まなければならないだろう。
つまり、バイデン政権の日本にとっての「キツさ」は、それが中国に対して「弱腰」になることではなく、むしろ日本が何ができるのかをよりはっきりと示さなければならなくなるだろうという意味での「キツさ」だ。トランプ大統領のことを一部の日本のトランプ支持者たちは、「おやびん」と呼んでいた。トランプ時代は、ある意味、「おやびん」の後をついていけば良かった。それは戦後日本のアメリカに対する「甘え」の構図でもあった。しかし、バイデン政権はこの「甘え」を許容してはくれないだろう。その意味でバイデン政権は日本にとってキツい。
【執筆:慶應義塾大学総合政策学部教授 中山俊宏】





