余力無し、なんとかやりくりしているところ
「今、余力が無いところを医療機関と都が協力して、なんとかやりくりしているというところ」
東京都は12月24日夕方、新型コロナウイルスのモニタリング会議を開いた。
会議では感染状況、医療体制とも先週すでに最も深刻な警戒レベルに引き上げられているが、東京都医師会の猪口正孝副会長からはさらに厳しい分析が出された。
「医療提供体制の深刻な機能不全や保健所業務への大きな支障の発生が予想される」

感染状況は、新規感染者の7日間平均が先週の513人から大幅に増え617人となり、「通常の医療が圧迫される深刻な状況になっている」との分析が示された。
このままでは1日あたりの感染者が2週間後は888人、1月21日には1279人になるという。それに伴い、2週間後までに新たに重症者が114人増える、とも。
通常の医療が圧迫される深刻な状況
「通常の医療が圧迫される深刻な状況となっており、新規陽性者数が爆発的に増加する前に最大限の感染拡大防止策をただちに実行する必要があります」
国立国際医療研究センターの大曲貴夫センター長からも、いかに医療現場が“崖っぷち”の厳しい状況であるかが伝えられた。
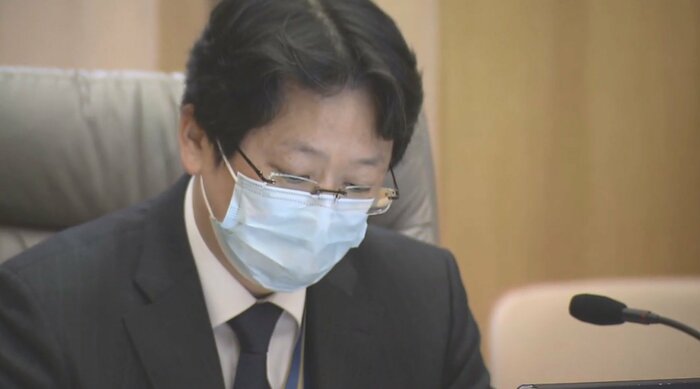
小児患者の受け入れ調整も難航
また、入院者数は2000人を超え、21日にはこれまでで最多の2154人に。医療機関の受け入れ体制が逼迫し、保健所が東京都に入院調整を頼む件数も1日200件に達するということで、特に透析患者や子供、小児患者の受け入れ調整が難航しているという。
そして、保健所業務も逼迫している。
今週の保健所別届出数は、都内保健所の約6割となる20保健所で100人を超え、6保健所で200人を超えている。
その一方で、人々が活発に動いていることがわかるのが、“どこで感染したか分からない”接触歴不明者の割合だ。
20代から50代は6割以上が接触歴不明、60代でも5割を超えている。
小池知事“お願い”のもどかしさ
「買い物、通院等を除いては、外出はぜひとも自粛をお願いいたします。やむを得ず外出する時は、マスクをして三密を回避してください。帰宅時には手洗いを徹底してください。特に高齢者・基礎疾患がある皆様には、外出の自粛、会食への参加は厳に慎んで頂きたい」
小池知事はこのように述べ、事業者に対しては飲食店などへの来年1月11日までの時短要請や、できる限り出勤しなくていいようにテレワーク、時差出勤、休暇の分散取得を呼びかけた。
しかし、結局は「お願い」でしかない。そのもどかしさが伝わってくる、たたみかけるような口調だった。
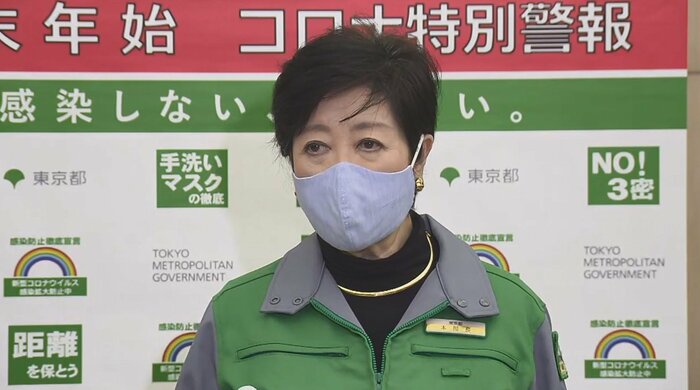
時短前倒しで本末転倒か
そんな中、現在は午後10時までとしている飲食店の時短要請を前倒し、午後9時や午後8時にすべき、という政府側。しかし、都庁内からは次のような声が上がった。
「閉店時間を早めるほど、協力する店は減る」
「12月18日から1月11日まで、時短の期間を延長するとともに、街灯を消し、強いメッセージを発するなど、様々な取り組みを行う中で人の流れを抑えていくというのが都の考え方」
つまり、時短要請を厳しくしすぎて協力してくれる店が減ったら本末転倒で意味が無い、ということだ。
また、第1波や第2波の時のように1カ所で大規模クラスターが発生、というような状況なら、業種や地域などへの集中的な対策で効果が見られるが、現在のように感染経路もクラスターの場所も様々な場合は、広く全体的に人流を減らしていくべき、ということもあるのかもしれない。

国の特措法改正は「年末年始休んでないで」
「今夜は静かにおうちでサイレントナイト」
クリスマス、年末年始の外出自粛、帰省の自粛、ステイホームを改めて求めた小池知事。それとともに国に対しては、要請を実効力あるものにするために特措法の改正も改めて強く求めた。
「(特措法は)ちゃんと効果が出る方法でないと意味ないと思います。ただ、その罰則についてもいろいろなやり方があろうと思いますが、まず、持つものを持った上で進めることが抑止力になるということもあるんですね。これは防衛と同じことなんです。だからそういった形で、しっかりとした特措法にしていただきたい」
さらに、国に対応を急ぐよう念押しの発言もあった。
「年末年始休んでないで、しっかりそっちの方をやってほしいという思いです」
(執筆:フジテレビ都庁担当・小川美那記者)





