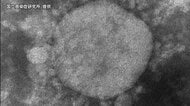菅政権の看板政策である「デジタル改革」。学校教育のデジタル化では1人1台端末やオンライン授業、デジタル教科書に注目が集まりがちだが、忘れてはいけないのが学校のコロナ感染対策のデジタル化だ。現状と課題を取材した。
隣の学校の感染状況が分からないシステム
「本当は教室で入力できるようにしたいのですが、職員室に戻らないと出来ないのです」
こう語るのは都内にある公立小学校の副校長だ。
この学校では教員が毎日、校務を支援するシステム「校務支援システム」に児童の欠席状況を入力する。入力は中休みの午前10時半頃までに行うことになっている。しかし忙しい先生たちは、ネットの通じる職員室に戻って入力できないこともあり、学校全体の欠席状況が判明するのは夕方になることもよくあるという。
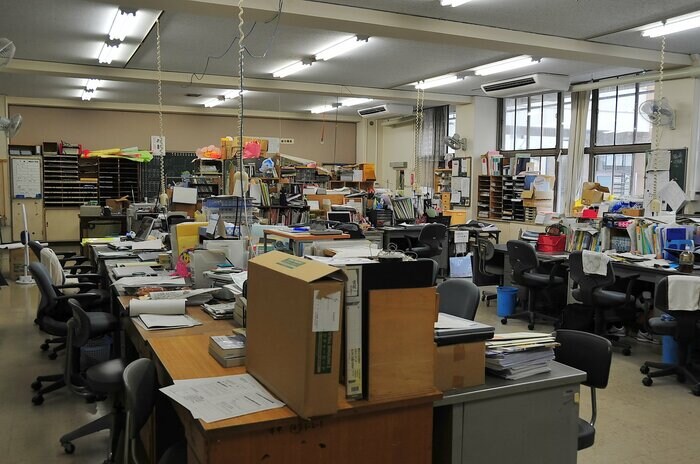
一方学校が気になる近隣地域の感染状況をこのシステムでは把握できない。
「システムは市で統一されていて、こちらで欠席状況を入力すれば教育委員会も見られるようになっています。ですから市教委にいちいち報告する必要はありません。ただ、たとえば隣の学校の欠席状況がどうなっているのか見ようとしても、このシステムでは権限が無いので見られません。だから近隣の学校に直接聞くしかありません」(副校長)
国の感染症情報システムの加入率は約6割
現在全国の小中学校の感染状況を把握するためにあるのが「学校等欠席者・感染症情報システム(以下感染症情報システム)」だ。しかしこのシステムに加入する小学校は約66%、中学校は約60%程度となっている。
さらに問題なのは、そもそもこのシステムが前述の小学校が使っているような校務支援システムと連携していないことだ。
だから学校側は「ただでさえ忙しいのに入力の2度手間は避けたい」(教育関係者)ので、感染症情報システムへの加入に躊躇するのだ。
こうした状況に危機感を募らせた文科省は、来年度予算の概算要求に感染症情報システムの加入率向上と各学校の校務支援システムとの連携事業費として22億円を盛り込んだ。
「感染症情報システムに加入すると、自分の地域の感染状況をマッピングしてみることができます。いまは校務支援システムと連携していないので、2回入力しないといけないのですが、データ連携が可能になれば入力も1度ですみます」(文科省担当者)
この事業ではまず、各自治体の校務支援システムの入力項目やデータ形式などを感染症情報システムに連携できるよう改修し、データ移行のための連携サーバーを構築する。
これによって学校は児童生徒の欠席状況を一度入力すれば、感染症で欠席する児童生徒の発生状況を全国単位でリアルタイムに把握できるようになるのだ。

学校の健康診断結果をいつどこでも確認へ
また文科省では、児童生徒の健康診断情報をPHR(=個人健康情報)に活用するための調査研究費2億円を概算要求に盛り込んだ。
具体的には学校で行う健康診断結果を校務支援システムに入力し、各家庭がマイナポータルなどを通じて閲覧できるようにする。これにより児童生徒の健康状態をいつでもどこでも本人や家族が確認できるようになり、感染症が疑われる場合にもデータを使って医療関係者との正確なコミュニケーションが可能になる。
ただこうした事業を進める際に問題となるのが、校務支援システムのメーカーが自治体ごとに様々で互換性がないことだ。
「メーカー間に連携性がないので、情報をシステム間で転送することができません。たとえば児童生徒の転校や進学の際、成績や健康診断情報を転校・進学先に渡しますが、データで転送できないので紙にプリントアウトして渡すことになります。これはほぼすべての教育情報においてそうで、紙でしかやり取りできないだけでなく、紙の様式自体も統一化されていないのです」(文科省担当者)
感染症対策こそ教育デジタル化の1丁目1番地
各学校で眠っている児童生徒の健康データを本人に還元したり、地域の感染状況をマッピングして国の感染症対策に活かすのは初めての取り組みとなる。これらの事業は今後の学校教育デジタル化の「1丁目1番地」ともいえるものだ。
「自治体の中にはなぜそんなことをしなくてはいけないのか、教育委員会に電話とファックスでやっているからそれでいいという批判や不満もあると思います。しかしこの事業に関して先日オンライン説明会を行ったところ、約5千人の教育関係者が参加し、機運は高まっていると思います」(文科省担当者)
児童生徒の命と健康を守るためにも、躊躇することなく教育現場のデジタル化はすすめるべきである。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】