灼熱の甲子園 止まっていた針が再び動いた

灼熱の太陽に照らされたアルプス席。応援団の声は涙でかすれ、選手たちは互いに抱き合いながら肩を震わせていた。
「ずっと止まっていた甲子園の時計の針が、また動き出した」
須江航監督は、選手たちの1年間の努力をそう言葉に込めて称えた。
敗北の悔しさの中であっても、この一言は確かに選手たちを支え、多くの人の心を打った。
勝って当たり前という重圧
2年ぶりの聖地でベスト16に進んだ仙台育英学園硬式野球部。
だが、ここに至るまでの道のりは、決して平坦ではなかった。

2022年、深紅の大優勝旗を白河の関の向こうへ初めて運び、東北の夢を現実に変えた仙台育英。翌年も決勝進出。
しかしその栄光は後輩たちにとって、憧れであると同時に「重荷」でもあった。
「仙台育英に入れば甲子園に行ける」
そんな考えで入学した選手は少なくない。だが現実は甘くなかった。
2024年には、春夏ともに甲子園を逃す屈辱を味わった。
秋の東北大会でも準々決勝で敗れ、新チームでのセンバツ出場を逃した。

キャプテンの佐々木義恭(3年)は語る。
「自然に甲子園に行けると思っていた。でも、そうじゃない。自分たちで積み上げていかなきゃいけない」
名門に漂っていた慢心と惰性を、彼の言葉が打ち破っていった。
冬の誓い「自分たちの勝ち方」を探して
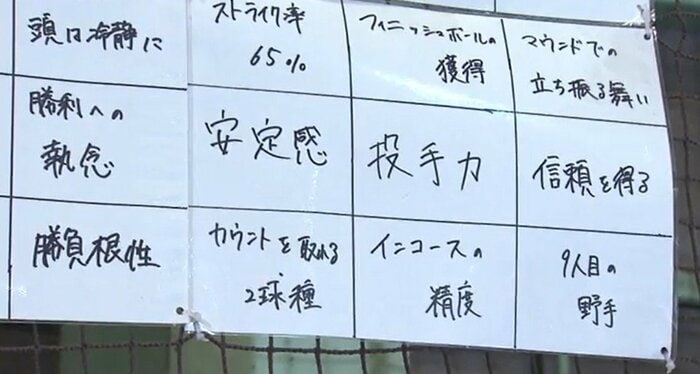
2024年12月。雪が舞う仙台のグラウンドに、甲子園優勝メンバーの髙橋煌稀が姿を見せた。
「甲子園は、めちゃくちゃ素敵な場所。だから後輩たちにも味わってほしい」
後輩たちにフォームやトレーニングを惜しみなく伝えるその背中は、“日本一の基準”そのものだった。
だが、キャプテン佐々木は冷静に考えていた。
「伝統を受け継ぐだけじゃ足りない。自分たち自身の勝ち方を見つけるべきだ」
この思いはチーム全体に広がり、冬の練習の空気を一変させた。
「もう一度甲子園へ」―。新たな覚悟とともに、勝負の2025年が始まった。
日本一のチーム内競争 仲間はライバルであり支え

須江監督は言い続けた。
「競争の先にしか成長はない。最後までギリギリの競争をしてもらう」
その競争の中で、選手たちは確かな成長を遂げていく。
吉川陽大(3年)は最速147キロを誇る直球に磨きをかけ、制球力を兼ね備えた絶対的エースに進化。
砂涼人(1年)、有本豪琉(1年)の新戦力も頭角を現し、恐れ知らずのプレーでチームを活性化。
学年も立場も関係ない、徹底した実力主義。
キャプテン佐々木は実感を込めて語る。
「それぞれの長所を最大限に集めて、その中で競い合う。これが“日本一の競争”」
仲間であり、ライバルであり、時に憎らしいほど意識し合う存在。
その競争が、停滞していたチームをよみがえらせた。
東北のスターが背番号を逃した理由
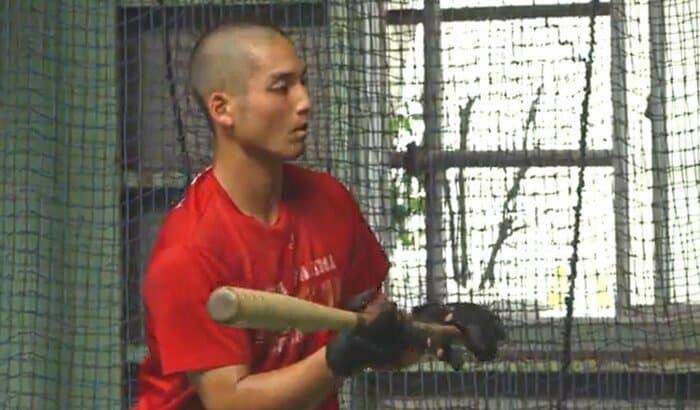
だが、全員が報われるわけではなかった。
田口大和(3年)。楽天ジュニアにも選抜されたスラッガーは「東北のスター」と呼ばれた逸材だ。
しかし仙台育英では一度もベンチ入りできないまま最後の夏を迎えた。
「もうなりふり構っていられない」
彼はプライドを捨て、フルスイングをやめてバスター打法に挑んだ。バスターだと打球は遠くに飛ばない。しかし、ここぞという場面でミートしやすくなる。
チームのため、「代打」の一枠に賭けた。
だが、背番号は呼ばれなかった。
田口は静かに仲間を見つめ、言った。
「甲子園の切符をつかんでくれることを信じて、自分は支える役になる」
応援団長として声を枯らし続ける田口の姿に、須江監督はこう語る。
「“面倒くさいこと”を率先してやるのが田口。チームが前に進めたのは彼のおかげ。チームを支える3年生全員を甲子園に連れていく。それが甲子園を目指す大きな理由かもしれない」
宮城大会準々決勝 運命を変えた一球

迎えた宮城大会準々決勝、宿敵・東北高校との一戦。
1点リードの7回裏、1死2・3塁の大ピンチ。
エース吉川陽大は心臓の鼓動を押さえ込むようにマウンドに立った。
「仲間を絶対に甲子園に連れて行く。その思いをこの一球に込めた」
苦しい時こそ、仲間の思いを背負って―。
二者連続三振で窮地を脱した瞬間、スタンドは歓喜の渦に包まれた。
仲間を信じる気持ちが、チームを救った一球だった。
甲子園での躍動 1年生と3年生の輝き

仙台育英は宮城大会を制し、2年ぶりの甲子園へ。
初戦から競争を勝ち抜いた選手たちが躍動した。
プロ注目のスラッガー・髙田庵冬(3年)が放ったホームラン。
有本と砂、1年生二遊間が決めた華麗なダブルプレー。
スタンドでは田口が声を枯らした。
全員で掴んだ勝利。1回戦、2回戦を突破した。
延長11回、沖縄尚学との死闘

3回戦の相手は、のちに日本一に輝いた沖縄尚学。
大会屈指の左腕・末吉良丞(2年)とのエース対決は、最初から最後まで緊迫感に包まれていた。
初回、4番・川尻結大(3年)が先制のタイムリー。アルプス席は歓喜の渦となる。
しかし2回と3回に失点し逆転を許す。それでも4回、再び川尻が勝負強さを見せ、走者2人を返す一打で再逆転した。
先発のエース吉川陽大(3年)は、100球を投じた2回戦から中2日。疲労を抱えながらも全身を震わせ、仲間の声援を背に投げ続けた。
7回、同点に追いつかれる。だがマウンドは譲らない。
「背番号1」のプライドを燃やし、吉川は腕を振り続けた。
スコアは3対3。勝負は延長タイブレークへ。
10回は両軍無得点。11回表、わずかな乱れを突かれ、沖縄尚学に2点を奪われる。
迎えたその裏、2死3塁。打席には吉川。相手マウンドには末吉。
互いに投げ抜き、投げ勝ってきた両エースの直接対決。
「誰も立ち入ることはできない」―。須江監督がそう評した極限の一打席。
フルカウント、最後の変化球を吉川は全身で振り抜いた。
打球はセカンド正面。必死に一塁へ滑り込むが、アウト。
その瞬間、吉川はベースに倒れ込み、泣き崩れた。
やり切った夏

試合終了。スコアは5対3。勝者は沖縄尚学。
吉川が151球、末吉が169球を投げ抜いた名勝負だった。
激闘を終えたナインがアルプスの前に並ぶ。
涙が止まらない選手たちの中で、キャプテンの佐々木だけは拳を突き上げた。
「やり切った」―。その表情には悔しさと誇りが同居していた。
須江監督は試合後に語った。
「1年生の夏から止まっていた針が、また動き出した。そう考えれば100点」
敗北の中にも確かな前進があった。選手たちはその言葉に救われた。
最後のミーティング 涙で語った言葉

宿舎でのラストミーティング。
佐々木は仲間を前に声を詰まらせながら語った。
「日本一にはなれなかった。でも、控えの3年生は“日本一の控えの3年生”。この仲間と野球ができたことが本当にうれしかった」
田口も涙を拭いながら言った。
「苦しくてやめようと思った時もあった。けど、自分のサポートが仲間の力になった。それだけで本当に良かった」
声を出し続けた3年生。
競争を勝ち抜き躍動した1年生。
仲間の思いを背負ったエース。
全員の想いが重なり合い、仙台育英の物語は紡がれた。
受け継がれる「仙台育英魂」

夏は終わった。だが、仙台育英魂は終わらない。
仲間を思い、仲間を信じ、仲間のために戦う。
その伝統がある限り、仙台育英はまた甲子園の土を踏むだろう。
スタンドの拍手は鳴り止まない。
東北の夢を背負った球児たちの物語はこれからも語り継がれていく。
仙台放送





