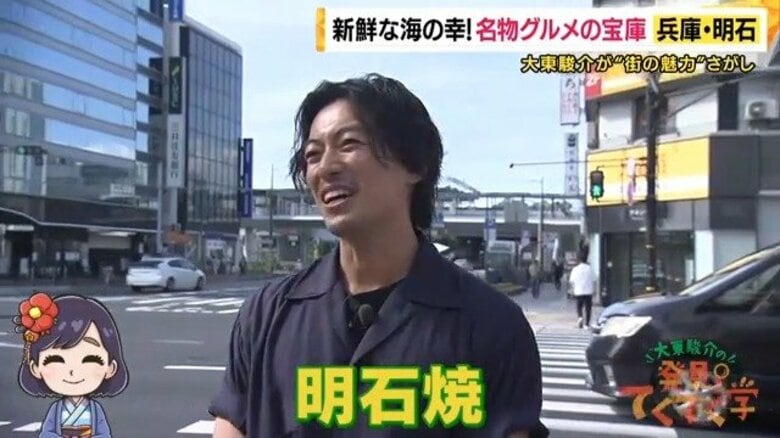大阪名物の「たこ焼き」が生まれる前から、実は兵庫県明石市には「明石焼」がありました。
その誕生の秘密と、明石だこの美味しさを追求する職人技を、俳優の大東駿介さんが探りました。
■「たこ焼き」のルーツは明石にあった!
地元では「玉子焼」と呼ばれている明石焼は、卵たっぷりでふわふわ、出汁が香る優しい味わいが特徴です。
大正8年が商売としての始まりとされています。
意外なことに、大阪の「たこ焼き」は明石焼からヒントを得て誕生したそうです。
昭和初期まで大阪では「ラジオ焼き」という生地に牛すじ肉とこんにゃくを入れて焼いたものが食べられていました。
「明石ではたこを入れている!」という情報をヒントに、大阪名物のたこ焼きが生まれたというのです。
【大東駿介さん】「え、それやのにあんなでかい顔してんの?たこ焼き」
■「明石焼」誕生のルーツ「明石玉」の謎に迫る
明石焼誕生のきっかけとなったのは「明石玉」という装飾品でした。
江戸時代に作られていたこの明石玉は、髪飾りなどの装飾品に使われていました。
大東さんは大正13年創業の「本家 きむらや」を訪問。
今も営業している明石焼の店で、最も古いとされる老舗です。
4代目の店主・衣川さち子さんに明石焼のルーツを聞きました。
【本家 きむら家・衣川さち子さん】「卵あるでしょ?この白身をどうにかして固めて、かんざしとか工芸品になるんですよ」
今から約160年前、明石玉を作る過程で大量に余った卵黄が活用され、明石焼が誕生したと言われています。当時の明石玉を作る道具は残っていますが、作り方は誰も知らないそうです。
【本家 きむら家・衣川さち子さん】「白身を使うから黄身が余るので、こういう玉子焼という文化が生まれた」
■ 斜めの板には理由があった!
「本家 きむらや」の明石焼は創業当時から変わらぬ味を守っています。
明石焼を斜めの板に乗せて提供するスタイルには実は理由がありました。
もともと、これは明石焼を銅板から外すための道具でしたが、腕に当たる部分が邪魔ということで持ち手を1本にしたそうです。
いつしか、板のまま明石焼を出すようになり、斜めに傾いた提供スタイルが定番になったのです。
■1ミリ単位の技術!明石だこを茹でる職人技
続いて、大東さんは明石だこを茹でる「1ミリ単位の職人技」を学びに水産加工会社へ向かいました。
明石海峡周辺で育つ「明石だこ」は、激しい潮の流れに揉まれながら岩場で踏ん張るため、足が太く短いのが特徴。
プリッとした歯ごたえが自慢です。
創業から100年以上の歴史を誇る「金楠水産」を訪問した大東さん。
4代目の樟陽介さんから「明石だこ」を茹でる技術を教えてもらいました。
まず、水揚げされたばかりのたこの内臓を手際よく取り除き、たこ一匹一匹に塩を塗り込みます。
これはぬめりを取るだけでなく、余分な水分を抜く重要な工程です。
【金楠水産・樟陽介さん】「ここが1番実は重要で、余分な水分だけ抜くっていうのがまた難しくて。たこの状態をチェックして、どういう弾力をしているか、どれだけ水分が抜けているか..」
さらに専用のもみ機でたこを洗浄した後、1ミリの技術「ゆで」の工程に進みます。
たこの状態はたった1秒でも変わっていくそうで、職人の経験と感覚で釜に入れるタイミングを微妙にずらし、大きさや形の違うたこをすべて均一に茹で上げるのです。
【大東駿介さん】「食感から全然違う」
■究極のたこ愛から生まれた「グラビア写真集」
そんな「明石だこ」の美味しさをさらに引き出すため、樟さんはたこに合わせるディップソースも開発しました。
イチオシは「山椒マリネ」だそうです。
さらに驚いたのは、たこを愛しすぎるあまり「たこのグラビア写真集」まで作ったというのです。
表紙には「こんなに官能的な食べ物があっていいのか…」というキャッチコピーが踊ります。
【金楠水産・樟陽介さん】「親父の茹でたたこを見た時に美しいって思ったんです」
【大東俊介】「僕もほんま常々思うんですけど、俺らは生きていく中でたくさんの命を頂いて生きていくしかないし、頂くものに思いを持つと持たないとでは全く違うわけで、それを理解することによって旨みがまるで変わっていくわけです。」
明石の地に伝わる伝統の味と職人たちの情熱。
「玉子焼」の誕生秘話と明石だこの職人技、そして究極のたこ愛から生まれた写真集まで、明石の魅力を大東さんが存分に伝えてくれました。
(関西テレビ「newsランナー」2025年7月24日放送)