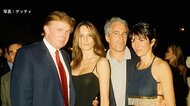イスラエル空軍によるシリア軍などへの空爆は、イスラエルと少数民族イスラム教ドルーズ派との「血の盟約」とも呼ばれる強い繋がりがあることを改めて思い起こさせることになった。
イスラエルがシリア国防省など空爆…背景にあった「盟約」
イスラエル空軍は16日、隣国シリアの首都ダマスカスにある同国国防省の建物などを空爆した。この模様は生放送中のシリアのテレビでとらえられ、女性キャスターが逃げ惑う様子が世界に配信された。
イスラエルのネタニヤフ首相は「シリア国内のイスラム教少数派ドルーズ派を保護するため」と釈明したが、中東紛争の新しい火種になりかねないと国際的に批判の声が巻き起こった。

そうした折、イスラエルの英字紙ザ・タイムズオブ・イズラエルは18日、攻撃を正当化する論評記事を掲載した。
「ドルーズとユダヤの盟約ーー運命と使命の特別な関係」
記事は、イスラエル国家とドルーズ共同体の間には、「忠誠、相互責任、そして真摯な協力関係という価値観に根差した深い絆ーーそれは『運命の盟約』であると同時に、『使命の盟約』がある」とする。
シリアによるドルーズ派攻撃に対し、イスラエル国防軍は、この盟約に従って即座に行動を起こしたものだと記事は訴える。
「これは国家の軍事作戦ではない。同胞を救うための人間としての自然な反応だった」
ともに功績と犠牲を積み重ねた歴史
ユダヤ教のイスラエルとイスラム教のドルーズ派は、相互扶助を約束した異例の同盟関係にある。俗に「血の盟約」と呼ばれ、その発端はイスラエルの建国にある。
1948年にイスラエルが建国された際、多くのアラブ人が強く反対する中で、ドルーズ派の指導者たちはイスラエルに協力する道を選んだ。

ユダヤ人が差別や抑圧の中で生き延びてきたという共通の歴史に共感したのと、当時盛んだった汎アラブ主義(ナセル主義)の中で、ドルーズ派のような少数派は排除、抑圧されていたことからだったと言われている。
イスラエルはドルーズ派を独立した宗教団体として認定し、独自の宗教裁判所や学校制度、文化的自治も認められた。
一方、ドルーズ派も、1948年の独立戦争の時点で多くの若者が自発的にイスラエル国防軍に参加して、アラブ軍と戦い、1956年にはドルーズ男性にも徴兵制が導入。以降、戦争や防衛で多くの功績と犠牲を積み重ね、「共に血を流した」ことから「血の盟約」と呼ばれるようになった。
ドルーズ派はイスラエル社会に組み込まれた存在なわけで、テルアビブ大学が行った調査でドルーズ派の若者の94%が「ドルーズ系イスラエル人」と自認している。(Ynetnews.com)

今回の紛争は、南シリアのドルーズ派の中心地スワイダで、ドルーズ派とベドウィン部族の衝突にシリア政府軍が介入してベドウィンを支援したことに始まった。
イスラエル国内のドルーズ派はシリアの同胞を支援するために越境してシリア軍と戦った。そのドルーズと「血の盟約」を結ぶイスラエルの空軍がシリア軍を空爆したのは、ある意味必然の成り行きだったのだ。

だからと言って空爆による被害を正当化できるものではないし、これによる中東情勢の不安定化を見逃せるわけでもない。ただ、紛争の終息を予見する上でその背後に中東では極めて異例な同盟関係があることを認めておくべきだろう。
(執筆:ジャーナリスト 木村太郎)