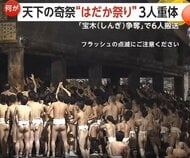長崎県で1月、危険運転を繰り返す暴走族のグループが事実上の壊滅となった。
暴走族は1980年代に全盛期を迎えたが、警察と地域が連携した取り締まりを続け、100人規模を検挙した年も続いた。
しかし、SNSを通じて集まる「暴走常習者」は依然存在し、深夜の騒音など市民からの苦情は今も絶えない。
1980年代の暴走族全盛期と執念の取り締まり
危険な違法走行を繰り返す「暴走族」。
各地で市民の平穏を侵害するその集団を、長崎県が“事実上の壊滅”へと追い込んだ。
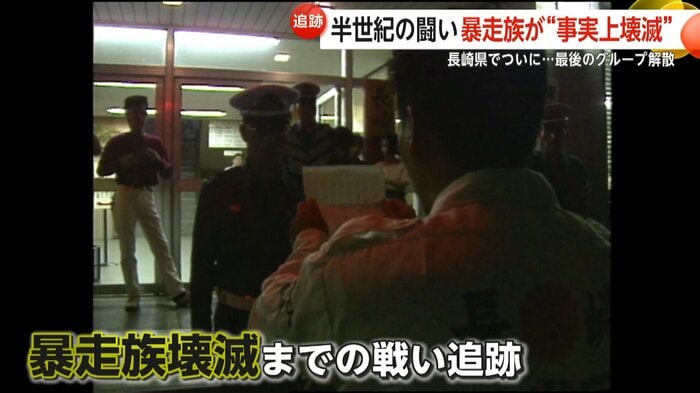
FNNは昭和から令和へと続く、暴走族壊滅までの戦いを追跡した。
テレビ長崎・円田智子記者:
大きな音を響かせながら、バイク数台が通り過ぎていきます。
長崎市で2月24日、カメラがとらえたのは壊滅後もあとを絶たない暴走行為だ。
いったい何が起きているのか。その実態を取材した。
爆音をとどろかせ、蛇行運転や信号無視など違反行為を繰り返す「暴走族」は、時に一部が暴徒化し、市民を巻き込む事件を起こすなど、1980年代をピークに大きな社会問題となっていた。
1994年にも、長崎市の繁華街で追跡するパトカーを挑発しながら、車の間ギリギリをすり抜け危険運転を行う暴走族の様子がカメラにとらえられていた。

しかし、2025年1月、県警は当時16歳から17歳の配管工や高校生など6人を逮捕し、バイクに同乗していた別の少年ら5人も送検した。
そして、少年らには誓約書を書かせ、県内に唯一残っていた暴走族を解散に追い込んだ。
テレビ長崎・磯部翔アナウンサー(2025年1月):
長崎市の国道交差点をバイクで危険な暴走行為をしたとして、少年ら11人が逮捕・書類送検されました。

長崎はなぜ、暴走族を事実上壊滅することができたのか。
県内でも暴走族の動きが激しくなっていた1988年、県警は県下すべての警察署の署長を集めた対策会議を開くなど、暴走族壊滅に向け総力を挙げた取り締まりの強化に取り組んだ。
長崎県警・遠藤唯雄本部長(当時):
一時沈静化したものの、1986年ごろから組織を拡大した。
同時にこのような暴走族を追放しようと、地域を巻き込んだ取り組みも活発化していく。

こうした地道な取り組みと警察の厳しい取り締まりによって、「解散」に追い込まれたグループもあった。
1991年の真夏の夜、白い特攻服を着た暴走族のメンバーたちが警察署の前に次々と集まってきた。
暴走族リーダー:
暴走行為により一般市民に多大な迷惑をかけ、とことん深くおわびいたします。今後一切暴走行為などをせず、交通道徳に従い、安全運転を心がけることを誓います。
暴走族の活動が活発になる夏場に合わせ、「サマーナイト作戦」と銘打った連日連夜の取り締まりによって、県警は複数の暴走族を解散に追い込んだ。
解散後も絶えぬ騒音に住民が悲鳴
当時、白バイ隊員として取り締まりにあたった県警交通指導課・松尾浩晴警視はこう語る。

県警交通指導課・松尾浩晴警視:
平成2〜4年(1990〜1992年)は、毎年100人の暴走族を検挙していた。暴走族の離脱、チームの解散に追いやってもまた新しく芽吹いてくる。いたちごっこと言いますか。
それでも県警が取り締まりの手を緩めることはなく、排気ガスで膨らますことができる暴走車両を阻止するための風船式アイテムも発案された。
県警によると、暴走族の認知件数は1972年42件をピークに減少、その後1998年になるとグループ数は6件となり、2025年1月に最後の暴走族が解散した。
これで市街地に静かな夜が戻ってくると思われたが、現状は違っていた。
2月24日午後9時ごろには、長崎市で暴走する複数のバイクが確認されている。
テレビ長崎・円田智子記者:
夜9時を過ぎました。大きな音を響かせながらバイク数台が通り過ぎていきます。近くに来るとかなり大きな音です。
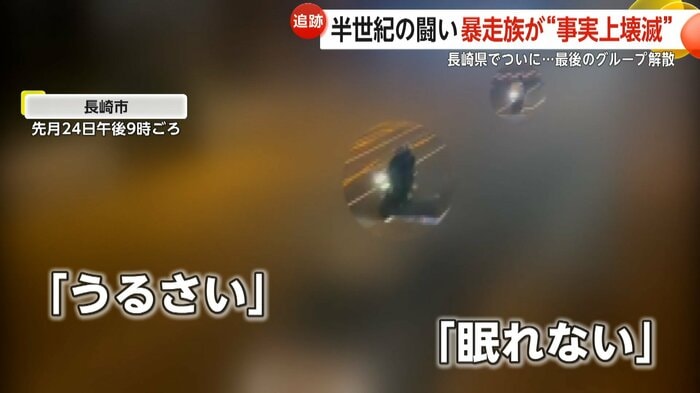
夜遅くに走るバイクの騒音で「うるさい」、「眠れない」などの苦情はあとを絶たない。
長崎県警の調べによると、苦情件数は2024年度も101件となっている。
県警は、この深夜の暴走者を、暴走族に属さない「暴走常習者」によるものと認識しているが、その実態を把握することは難しいという。
県警交通指導課・松尾浩晴警視:
どんな犯罪でもそうだが、SNSの発達で、非対面で(暴走族の)集会はなくても連絡が取れて、意思決定ができる。大げさに言えば、全然知らない同士が現場に集まって暴走行為をする。昔はなかったような形態も現代の特徴と言える。
(「イット!」3月11日放送より)