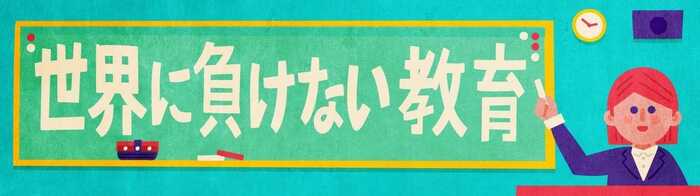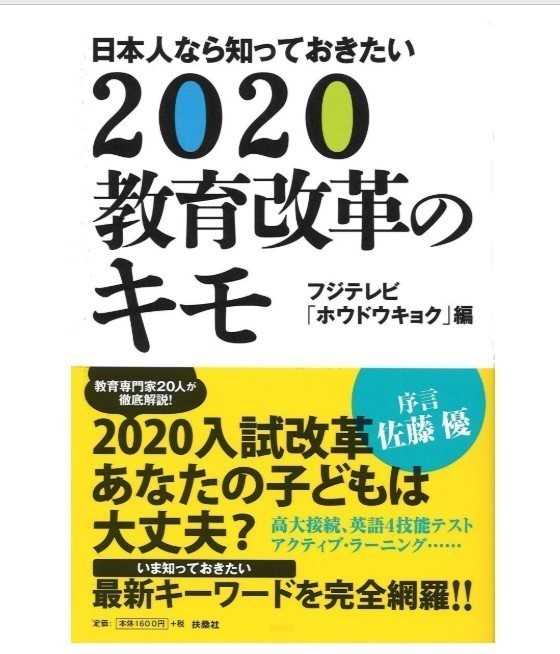スマホ解禁は是か非か
文科省が小中学校への携帯電話やスマホの持ち込み禁止を見直すと発表し、賛否両論が巻き起こっている。保護者の「緊急時に連絡が取れない」との不満の声に教育行政が押し切られたかたちだが、学校教育の現場では「さらにトラブルが増えるのではないか」と戦々恐々だ。果たして「スマホ解禁」は、是か非か?
ネット上での安全やモラルについて、企業や学校で年300回以上の講演をおこなっている、グリー株式会社の小木曽健さんにインタビューした。

ーー柴山文部科学大臣は19日の閣議後会見で、小中学校へ携帯電話やスマホをもちこむことを原則禁止にしていた2009年の通知を見直すと明らかにしました。小木曽さんは今回の文科省の見直しについては賛成ですか?反対ですか?
見直しと同じタイミングで、スマホの所持・持ち込みの「責任の所在」をより明確に出来れば、意味のあるものになると思います。現状、子ども同士のネットトラブルは学校が中心となって対処していますが、学校の本音は「スマホを買い与えたのは保護者なのだから、もっと保護者が積極的に関わってほしい」です。文科省からも「保護者も当事者意識を」と一言添えてもらうと、学校現場も少し動きやすくなるのではと思います。
ーー今回の見直しについて学校側はどんな反応ですか?
「学校内で起きる新たなネットトラブル」に戦々恐々です。学校はすでに、放課後のネットトラブル対応に追われています。「それがさらに増えるのか」と。中学校に関しては、スマホ所持率がある程度のレベルに達しているので、トラブル急増とまではいかないまでも、影響はあるでしょう。小学校は「持ってきていいよ」がきっかけでユーザー数が増える可能性があり、小学校の先生にとっては特に頭の痛い話だと思います。
いじめや犯罪に巻き込まれるリスクは?
ーーネット上のトラブルというと、LINEを使ったいじめとか出会い系サイトで犯罪に巻き込まれるケースがありますね?
先生方はネットいじめを「新たな問題」と認識しがちですが、例えば「LINEで別の会話グループを作って、陰口を言ういじめ」は、昔あった授業中にこっそり回した手紙と同じです。「LINE外し」と呼ばれるいじめは、「お弁当を食べるグループ」の仲間外しと一緒です。実はさほど新しい問題ではないのです。
犯罪被害については、「出会い系」よりも普通のSNSによるものが増加傾向にありますが、例えばLINEなら「友だち自動追加」や「友だちへの追加を許可」をオフにしておくだけで、知らない人とつながる可能性がかなり少なくなります。
ただ、そういった設定では防げないトラブルもあります。中高生カップルの男子生徒が、女子生徒に「裸の画像」を要求して、その画像を不特定多数が閲覧できる場所に投稿してしまう事例などがそうですね。
ーー中高生が裸の写真ですか?
はい。中高生のグループトーク(複数人が参加しているLINEのチャット)は、参加者が100人を超える場合もあり、当然、外部にも流出します。男子生徒の行為は論外ですが、女子生徒も自分の裸を撮影した行為が罪に問われるケースがあり、補導や訴訟に至る事例も多く起きています。
期間限定のお試しをやってみるという選択肢

ーー今回文科省が見直しを明らかにした理由には、大阪府の教育庁が府内の小中学校でスマホ持ち込みを認めるということがあります。では学校側はどう対応していけばいいんでしょう?
大阪の通達は、最終判断を各校の校長先生に委ねるニュアンスなので、「どうしたら良いか」というご相談を頂くこともあります。私は「持ち込む」「持ち込まない」ではなくて、「期間を区切って、試しにやってみましょう」というのをお勧めしています。
例えば1学期だけお試しでやってみる。その間、問題が起きる度にルールを追加し、保護者にも共有。1学期が終わったら「ルールが100個になりました」であれば「ウチの学校はまだ早い」と言えますよね。
子どもたちも、自分のせいでルールが出来てしまうのはイヤですから、自然と頑張るでしょうし、保護者にも当事者意識が生まれやすくなります。事前準備も最小限で済むので、先生方も少しは気が楽なのでは、と思います。
ーー全国的には、すでにスマホ持ち込みを実施している学校があるそうですね
はい、例えば千葉県のある新設の公立小学校では、開校以来、携帯・スマホ持ち込みに関しては一切ノータッチ、「持ってくるかどうかは任せるし、預かることもしない、トラブルにも関与しない」という方針を貫いています。新設校、新興住宅地、若い保護者が多い、という条件が揃って実現したのだと思いますが、学校がスマホを預かるような運用もしていないので、破損・紛失のトラブルは個人の責任で対処しているようです。ただ授業中に携帯が鳴ることもあり、その場合は子どもが普通に怒られます。
責任をもって使う

ーー大阪府教育庁のガイドラインでは、「画像や個人情報を安易に他者に送らない」「ネットで知り合った人とは会わない」と呼び掛けていますが、この呼び掛けには効果があると思いますか?
呼びかけだけで問題が解決するなら、例えば私がやっているような講演は必要無いですね(笑)。これは大阪に限りませんが、「なぜダメなのか」を論理的に説明できないと難しいでしょう。そもそもこれは、家庭が主体となって取り組むべき分野です。自転車に置き換えるとわかりやすいのですが、児童・生徒が通学中に自転車で加害事故を起こしたら、その責任は事故を起こした本人、家庭が引き受けるべきものでしょう。スマホも一緒です。スマホも自転車のように、その特性やリスクの理解が進んで、早くこういった議論ができるようにしたいです。
ーー最後に「とはいえITリテラシーを高めるためには、スマホやPCやタブレットを使いこなすべきで、持ち込みを認めないこと自体がそもそもおかしいんじゃないか」という意見もあります。
道具として役立つ使い方が出来るのであれば、使ったほうがいいと思いますが、だからと言って全員が使う必要もなければ、使いこなせない子供に合わせて一律に禁止するのも違うと思います。スマホはただの道具ですが、まだ普及・理解の途中であり、発展途上な分野でもあるので、課題の本質や「そもそもなぜ使うのか」といった議論をしっかりした上で進めていきたいですね。
ーーありがとうございました。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】
【関連記事:「世界に負けない教育」すべての記事を読む】
【画像提供:グリー株式会社】