1日に発生した能登半島地震で3000件以上の家屋が損壊した富山県。建築士は「次の地震が来たら耐震壁として性能が発揮できないリスクも」と警鐘を鳴らす。地盤の違いで建物への被害に差もあり、住宅の耐震化だけでは解決できない問題が露わとなった。
「氷見市で倒壊被害なぜ」

氷見市北部に位置する宇波地区。
地震から2週間が経っても、車庫が倒壊し、屋根が電線に引っかかったままとなっている場所もある。

車庫が倒壊した男性:
「田んぼの中に落ちてどうでもいいのなら、ほっといてもいい。何かあった場合『お前のところがいつまでもこんな状態にしとくからだ』と言われたら困る。(市も)忙しいかもしれないが、優先的に対処してほしい。もし雪の重みでなんかあった場合…」

この地域で、余震などによる倒壊の危険性を調べる「応急危険度判定」を行った1級建築士の川合光行さんは、同じ揺れでも被害の程度が異なり多くの被害を受けたほとんどが旧耐震基準で建てられた1981年以前の住宅だと話す。
応急危険度判定は、建物の傾きや壁の被害などを調べ、倒壊の危険性を赤、黄、緑の3段階で示したもので、氷見市内では1月12日までに調査した2142件のうち、赤色=危険と判定されたのは425件に上った。(要注意は689件)
川合さんは特に、昔ながらの瓦や土壁がある住宅は筋交いを入れたり、壁を増やしたりするなどの耐震化を進める必要があると話し、2階をなくして、床面積を減らす減築や平屋建てになるとリスクが違ってくるという。
「富山で進まない耐震化」

住宅の耐震化は、犠牲者の8割以上が倒壊した家屋の下敷によって亡くなった阪神・淡路大震災をきっかけに全国で進められてきた。2000年には、木造住宅の耐震性向上を目的に、基準をさらに強化した現行の耐震基準が設けられている。
しかし、富山県内の一般住宅の耐震化率は国が2018年に行った調査で80%。全国平均を7ポイント下回っている。背景には住宅の延べ面積が大きく、改修費用がかさむなど、富山県特有の事情があり、県は耐震化の促進を図るため、耐震改修に最大100万円の補助を出す制度を設けている。
「高岡市では液状化現象」
今回の地震は、住宅の耐震化だけでは解決できない「液状化現象」による問題が露わとなった。

小矢部川と庄川の河口に位置する高岡市の吉久地区では、もともと水平だった道路と住宅に50センチほどの段差ができ、車も簡単に出せなくなっているところもある。
建物が倒壊する被害はほとんどないものの、液状化現象によって、住宅などの重い建物が沈み、道路が隆起するといった被害が多く、下水道管も損壊し、復旧の目途が経っていない。
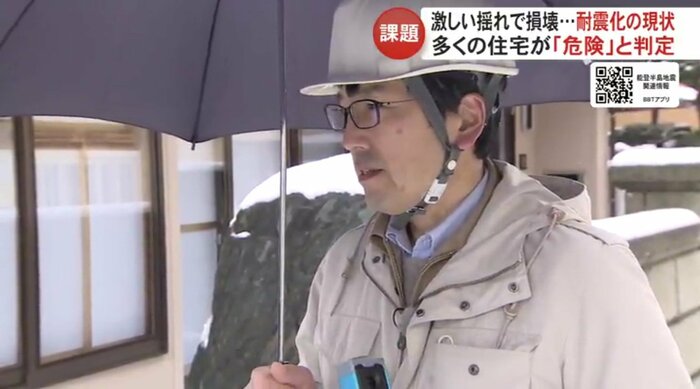
富山県建築士会 林芳宏理事:
「(水を)流したら戻ってくる。(液状化で)逆勾配になっている。1、2カ月後に解消できる目途があれば、それなりに対処できるが、はっきりわからない。」
吉久地区に住む1級建築士の林芳宏さんは、今回の地震では隣の伏木地区で応急危険度判定を行い、地盤による被害の違いを体感した。
富山県建築士会 林芳宏理事:
「同じ伏木でも台地にある家と液状化の被害にあった家はすぐ近くだが、全く違う。いかに地盤が建物に影響を及ぼすかを目の当たりにした」
その一方で、建物の倒壊は一部にとどまったものの、相次ぐ余震によって住宅の強度が落ちているケースもあると指摘する。
富山県建築士会 林芳宏理事:
「地震によって部分的に破壊された場合は、次の地震が来たら耐震壁としての性能が発揮できないリスクが生じている。ちょっと雨漏りがあって、部分的に柱や土台が腐朽や損傷がある場合は、簡単に倒壊する危険性がある。日頃から建物は健全な状態にしておくのが大事」
県は、建築士会などと連携し、被災した住宅の建て替えや修繕の相談を無料で受ける拠点を17日から高岡市役所や氷見市役所などで開設した。
(富山テレビ)





