東京都パスポートセンターで大量の個人情報が漏洩
11月24日、警視庁公安部は東京都豊島区にある池袋パスポートセンターに勤務していた中国籍の女を、窃盗容疑で書類送検した。
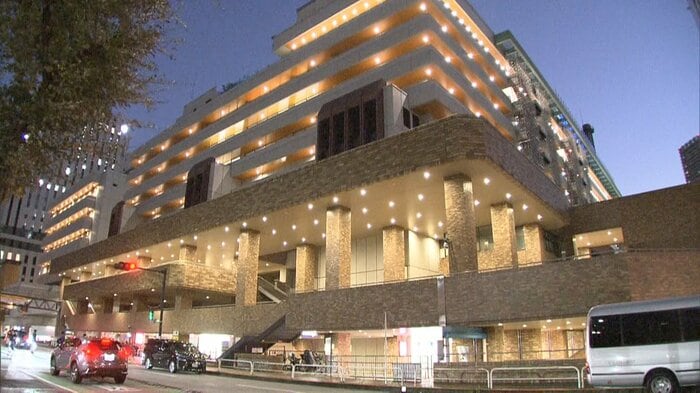
警視庁によると、容疑者はパスポートセンターの業務を受託する(株)エースシステム(東京・足立区)の契約社員として窓口で勤務していた。容疑者は、旅券申請者が提出した戸籍謄本や住民票をコピーしたり、窓口での対話を録音するなどの手段で、1920人分の個人情報を不正に入手した疑いがあるという。

これまでの報道によれば、本事件では「第三者への情報流出」や「国家的背景」の確認はされなかったというが、1920人分のデータ量を考慮すると私的な利用とは考えにくいだろう。
まず、悪徳業者への情報の販売など第三者への流出に関しては、第三者と会い、個人情報が記載された紙などを手渡していたら捜査機関が把握するのは至難の業だ。
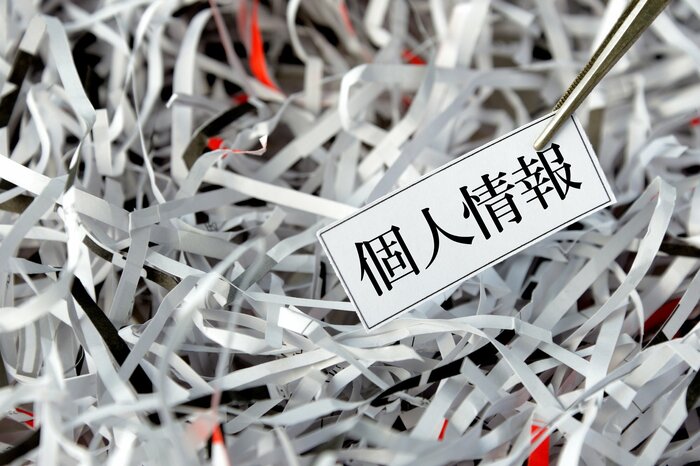
また、国家的背景についても、容疑者の交友関係を調査し、接触において情報機関関係者やその周辺者との関連を確認する必要があるほか、通信手段を含む接点において、指揮命令関係を示す証拠がない限り、国家的背景の立証は難しい。
「確認されていない」というよりは「確認できなかった」という表現が実態に近いだろう。
個人情報漏洩による危険性
本事件での情報漏洩により、パスポートを不正に取得されたり、そのパスポートを公的身分証として提示することで様々な犯罪を助長してしまうほか、個人情報を悪徳業者に販売するなど様々なリスクが考えられる。
2018年には、2億件以上の日本人の個人情報が、中国の闇サイトで売買されていたことが発覚している。闇サイト上では個人情報が1件当たり1000元(当時:約1万7000円)で販売されていたという。

特に、本事件では、外国籍者が個人情報を取り扱う業務に従事することに対する懸念が広がっている。
そもそも、中国の“国家情報法”は国内外の中国人や企業が当局の情報活動に協力することが義務付けられている。中国籍の人物が当該業務に従事していた状況は安全保障に関わる問題であることは明白だ。

また、仮に海外の情報機関に個人情報が渡った場合、当該個人情報を利用した各種諜報活動の礎となるのは言うまでもなく、要人の個人情報が把握され各種工作に悪用される可能性も十分にある。
事件が突き付けた課題と平和ボケした日本
この事件は、平和ボケした日本の「認識の欠如」を浮き彫りにした。
東京都が「個人情報を扱う業務自体が安全保障に関わり得る」という認識を持っていなかったことは深刻な問題である。

通常、官公庁や企業では出入り業者や委託先に対する管理は厳格に行われているはずだが、今回の事件で東京都の委託先管理が不十分であったことが露呈した。
外務省は即座に対応し、各都道府県に対しパスポート発給窓口の担当者を「日本国籍を持つ人物」に限定するよう通知を出したが、昨今の日本を取り巻く情勢を考えると、より厳格な管理が求められている。

東京都は今後、委託先管理を徹底し、特に経済安全保障の観点からのリスク管理を強化しなければならない。過度な性善説に基づく管理は現実的ではなくなっており、現代の複雑な安全保障状況に適応する必要がある。

また、この事件が社会であまり問題視されていないように感じる。事件の内情は置いておいても、外国籍者がパスポートセンターの業務に従事し、戸籍を含む個人情報を窃取していたという事実は極めて重大である。これがどれだけ深刻な問題であるか、もっと広く認識されるべきである。
この無関心は、平和ボケの現れではないだろうか。
国民全体が安全保障に関する意識を高め、現実の脅威に対処する必要がある。
【執筆:稲村悠・日本カウンターインテリジェンス協会代表理事】





