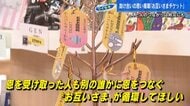西日本豪雨からまもなく5年がたつが、土石流で壊滅的な被害を受けた広島県呉市の田んぼでは、5年ぶりに田植えが行われた。ボランティアらの多くの人の手を借りて復興にこぎつけた田んぼをめぐる人々の思いを追った。
5年前、自宅も田畑も土石流に…農業継続が危ぶまれる
中村正美さん:
最初の絶望感から、こういう形になって嬉しいですよ

6月初旬、早朝から田植えの作業に追われていたのは、呉市安浦町市原地区の自治会長・中村正美さん。自分の田んぼで作付けするのは5年ぶりだ。


2018年の西日本豪雨。市原地区は多発的に土石流が発生。3人が死亡し、集落につながる道路が寸断され、一時孤立状態に陥った。

中村さんの自宅も被災し、代々受け継いだ田畑は一瞬にして土砂に飲み込まれた。

被災後には行政の現地調査もあった。
行政担当者:
どういう課題があって、何を先にこなしていかないといけないかというものを策定するのに、現地調査に入らせていただきました

中村さん:
復旧、復興を前提としたものという位置づけでいいんでしょうか? もう切り捨てるとかね、そういうものではないんですかね
行政担当者:
いやいや

中村さんは、当初から、生まれ育った市原地区を離れる気はなかったという。

中村さん:
郷土に対する愛着がありますからね。なかなか切り捨てることはできない

しかし、再び田植えを迎えるまでには5年の月日がかかった。
3月末に呉市が行った整備の2つある区画のうちの1つが完成。土地がかさ上げされ広くなり、機械を使った作業がしやすくなった。

中村さん:
広いと作業が楽ですね。べリーグッドよ

田植えまでの5年を支えたのはボランティア
ここまでの5年を支えてくれたのは災害以降、継続的に訪れてくれるようになったボランティア。この日も3人が中村さんを手伝う。

ボランティアの会社員・長谷川明夫さん(広島市在住):
ほぼ毎週のように顔を合わせていたので、自分の親じゃないですけどお父ちゃんみたいなもんですよね

ボランティア・小笠原繁哉さん(呉市在住):
ほ場整備が全部済んで田植えが完了した時点、我々が見守るのは、そこまでかなと思っている

災害後、土に覆われ手つかずとなっていた田んぼには草木が生い茂り、重機が入れない水路はボランティアが手作業で土砂をかき出した。

中村さん:
もう頼もしいよね。僕もボランティアに依存しないようにしているんだけどね。豪雨災害がきっかけでね、今、こういう形があるわけだからね

それでも土の中からはまだ土石流の爪痕の大きな石が…。重機で出しきれなかった異物は地道に取り除くしかない。

ボランティアの教員・北篤志さん(広島県坂町在住):
石の重さは1~2キロくらいですかね。1回災害が起きると1年だけで終わらないから、そこを継続的に見に行って、一緒に色んな人と協力し合うことが大切なのかなと思います

地元を支えるボランティアは、こんなところにも…
空からドローンで土砂崩れを確認 二次災害を防ぐ
被災後、この地区では雨が降るたびに小規模な土砂崩れが繰り返し起きていて、定期的にドローンを飛ばし、その映像をもとに避難情報などに役立ててもらおうとしている。

今回の調査でも、砂防ダムの上に発生して間もないとみられる土砂崩れの跡が確認できた。

広島県防災ドローン研究会・西佐古信夫さん:
二次災害を防ぐためにやっている。平面じゃ分からないところを、こういう鳥の目じゃないですけど、立体的に見たら一目瞭然なんですね

市原地区の現在の人口は11世帯27人。この5年で半分以下に減少。復興が進む一方で、西日本豪雨以降、集落の過疎化が急速に進んでいる。
そんな中、西日本豪雨から5年、ようやくたどり着いた田植えの再開。

中村さん:
将来がどうなるか、よくわからないところもいっぱいあるんですけどね。正直なところね。みんなに支えてもらったり、色んなこともあったりして、どうにかこうにか・・・というところですかね。みんなにおいしいと言われるコメを作りたいと思います

今回、作付けが終わった区画のすぐ近くでは、現在も残り半分のほ場整備が続いており、8月に完了する見込みだ。

災害と過疎化のきびしい現実の中、ひたむきに歩んできた被災地の人たち。ボランティアの継続的な後押しを受けながら、少しずつ日常を取り戻そうとしている。
(テレビ新広島)