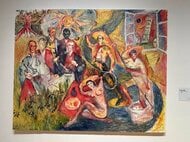世界各地で大規模プロジェクトが進行中のSANAA。日本では2024年度完成予定の新香川県立体育館の工事が進んでいる。高松駅方面から瀬戸内海へ視覚的にも開けていて、実際歩いて抜けられる設計になっているという。
駅から瀬戸内海に“抜けられる”体育館
世界文化賞の授賞式の翌週、SANAAの妹島和世さんと西沢立衛さんの姿は、新香川県立体育館の建築現場にあった。

体育館は、香川県の鉄道のメインターミナル高松駅から海へと向かうところにできる。駅側から見ると背景には瀬戸内海、海側から見ると背景には讃岐山脈がそびえる、という立地である。
高さを低く抑えた曲線状の屋根は瀬戸内海に浮かぶ小鳥をイメージし、陸側から見ても海側から見ても、周辺の景色に溶け込むようなデザインになっている。


西沢:「瀬戸内海に面した敷地で、駅からすぐのところで、その周りに瀬戸内海とか、山とか、もともとある広場とかがあるので、そういうものと一緒になって何か大きな一つの公園というか、運動だったりイベントだったりが起こる、そういう場所になったらいいなと思っています」

メインアリーナはスポーツの国際大会やコンサートの会場にもなる1万人規模の広さだが、観客席上部に壁を作らず、交流ゾーンという下の部分と一体感があるのが、いかにもSANAAらしい。


西沢:「ドームって基本的に着地するもの、閉じるものですが、われわれは“抜け”を出しています」
妹島:「アリーナでくっつくけど、エントランスを入って体育館に入った瞬間に体育館と周りが一体となることを目指しています」

金沢21世紀美術館を“美術館は街”として作ったのと同じように、この新香川県立体育館はメインアリーナなど3つの施設が一つ屋根の下でつながり、さながら“体育館は街”と言ったところ。

中央には、海に抜けられる開放的な通路があり、人々が自由に歩き回ったり、くつろいだりできる。2024年度末の完成が楽しみだ。
シドニーの海が“近づいてくる”美術館
世界に目を向けるとオーストラリアのシドニーでは、SANAAの新しい作品が完成し、今年12月3日に一般公開された。ニューサウスウェールズ州立美術館の新館である。
妹島:「ボタニカルガーデンの中に美術館があり、その上に首都高が走っていて、横に古い給油タンクが埋まっており、給油タンクと首都高の上に増築する、という難しい形の土地でした。各レベルに展示室を置いていって、順々に下りてくるときれいな海がどんどん近づいてきます。地形とか風景を楽しみながら場所を歩き回れるので、みんなに親しんでいただけるだろうな、と思っています」

使用説明書よりもわかりやすい建築を
新香川県立体育館も、ニューサウスウェールズ州立美術館新館も、「周りの人たちに愛され、受け入れられる建物を」という妹島さん、西沢さんの思いが詰まっている。SANAAの建築が人々に愛される理由。それは二人が作品を決して大仰なアートとしてではなく、人々に身近なものとして造っているから。その思いが建築と人々の幸せな関係を生んでいる。
西沢:「建築は本来わかりやすいものだと思っています。言葉だと100万の言葉を使うのを、空間で見せると1個でわかる。われわれは、使ってわかる、見てわかる、使用説明書を読むよりわかりやすいものを目指しています」
建築を芸術のジャンルに入れてくれてうれしい
世界文化賞の建築部門では、これまでに丹下健三氏(1993)、安藤忠雄氏(1996)、槇文彦氏(1999)、谷口吉生氏(2005)、伊東豊雄氏(2010)と日本人の受賞が多い。率直な感想を聞いてみた。

妹島:「芸術の中に建築というジャンルを入れてもらえてうれしいです。建築は色々なところから計れて、広いので、評価軸が色々あって、どっかで芸術だと全体的にわかるものです。場所場所で、時代を通して、今の人にも受け入れられ、違う価値基準の人からも受けいれられる、使ってみたくなる建築として評価されたらうれしいです」
西沢:「(自分たちが評価されたのは)ひとつはすごい日本的な部分があるのかな、と思います。世界のどこでもありうる建築をめざしていますが、同時に固有の文化、気候風土に根ざしたことを感じさせる建築に出会うと感銘を受ける。西洋からすると日本の建築はすごい違って見えるのかな、と思います」
世界に羽ばたく日本人ユニットSANAAのますますの活躍から目が離せない。