日本の小児科医療は、危機に瀕している。そんな中で、昼間は福岡市と大牟田市の小児科で、そして夜間は急患センターで小児医療に携わる女医がいた。母親の訴えを聞くことを信条とするベテランの小児科医・佐藤聖美(仮名)さんだ。
フジテレビ系列28局が1992年から続けてきた「FNSドキュメンタリー大賞」が第30回を迎えた。FNS28局がそれぞれの視点で切り取った日本の断面を、各局がドキュメンタリー形式で発表。今回は第9回(2000年)に大賞を受賞したテレビ西日本の「母だからこそ…―リストラされる小児病棟」を掲載する。
前編では、4歳の長女を風邪と診断された翌日に、心筋炎で愛する子供を亡くした母親を追った。後編では、全国的に小児科病棟が閉鎖されていく中で、母親本位を徹底する女医が診察に奮闘する姿を追う。
(記事内の情報・数字は放送当時のまま掲載しています)
小児医療は危機的な状況
2000年7月31日の第149回臨時国会で、当選したばかりの1年生議員・水島広子氏が異例ともいえる代表質問をした。
「今、日本の小児科医療は危機に瀕しております。『患者数が少ない』『大人の医療と比べて儲からない』『手間がかかる』などという理由で小児科医の数が減り、医療の質の低下、小児科医のますますの激務につながっています。小児科救急の不備のために命を落とした不幸な子どもの例も多数報道されています」
この危機的な状況の最たるものが小児科のリストラだ。
夜10時、昼間の病院での勤務を終えて久留米市のマンションに戻った小児科医・佐藤さんが、再び自宅を後にした。行先は40キロ離れた福岡市の急患診療センターだ。

この急患診療センターで、佐藤さんは週に3回、夜間の当直医をこなす。深夜0時から翌朝6時までの勤務で、寝る間もほとんどないまま診察に臨む。
特に夜間は、急な発熱や症状の悪化で病院に駆け込む人が後を絶たない。それにもかかわらず、他の病院は小児科の当直医がいないため、人口200万人の福岡都市圏で、夜間に子どもを診察できるのは、ここ一カ所だけとなる。

小児科の減少は続いている。例えば、福岡市のベッドタウンを担う福岡大学筑紫病院では、建物の老朽化や経営状態の悪化を理由に、1999年に小児科の縮小を決定。小児用の病室を成人用に改造し、外来部門も内科などに転用するというもので、事実上の小児科の廃止だった。

小児科が減り続ける理由
厚生省のデータによると、4119施設あった1990(平成2)年から、1998(平成10)年までの8年間に姿を消した小児科は全国で400に上る。今後も小児科の閉鎖縮小の流れは止まりそうにない。なぜ小児科をリストラするのか。
第一は収入面の問題だ。小児科は保険点数や補助が少なく、全国の病院連盟が調査したところ、小児科の病院収入は他の科の60%に前後にすぎないという。

2つ目はベッドの稼働率。緊急の入院に備え、子ども用の病床は常に空きを用意しておく必要があり、稼働率は80%が理想といわれる。残り20%に対する法的な補てんは当然ない。
3つ目は人手がかかること。細い血管に点滴の針を刺したり、泣いたり暴れたりする子どもを抑えたりする必要があることから、人手は大人を治療する場合の5倍といわれている。
このようなことから小児科は“赤字”となるのだ。
小児科医の“高齢化問題”も顕在化
そして今、小児科の減少と合わせてもう一つ起きているのが、小児科医の高齢化だ。例えば、福岡県添田町には、かつて小児科医が2人いたが、1999年までに相次いで亡くなった。

現在、小児科の医者が最も多い世代は60代から70代。これでは夜間の診察や当直は体力的にも過酷となる。一方で小児科のなり手は少なく、小児科を選んだ新卒医師が、この10年間で20%も減ったことが全国18の医大の調査で分かった。
そこで厚生省では小児医療対策として、新しいエンゼルプランを策定。小児科医を確保するという方針を打ち出し、具体的な政策を協議中だ。しかし国独自では限界もあり、地方自治体や医学部の協力が欠かせないのも実情だ。
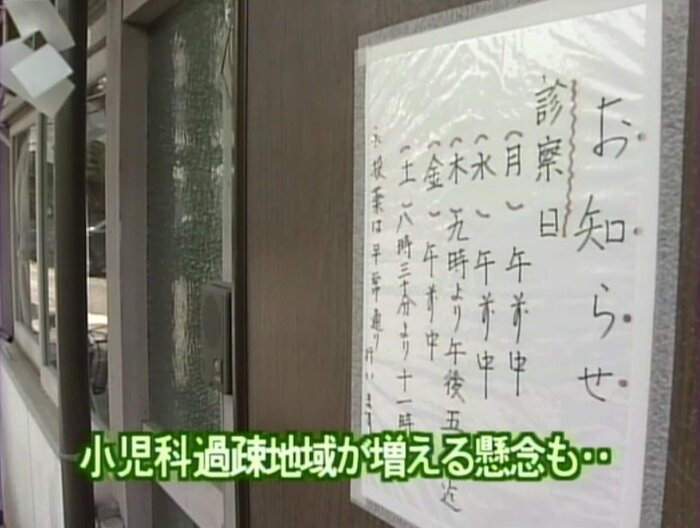
なお平成12(2000)年度の厚生白書では、4月の介護保険施行を受けて高齢化対策を全面に打ち出したが、小児に関する部分はわずか10ページ。にもかかわらず、厚生省は小児科に絞って当直医の診療報酬を引き上げたことをあげ、「これで夜間も子どもの救急治療、入院の態勢が万全になった」としている。
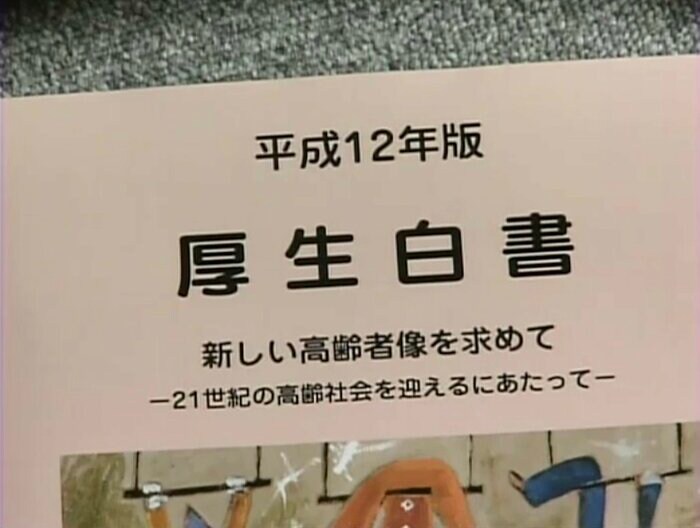
母親本位の診療は自身の苦い経験から
佐藤さんがかつて総合病院に勤めていたとき、待合室には子どもがあふれていたという。診察時間は2、3分しか取れず、ベルトコンベヤーのように診察をしなければならないという経験をした。
だからこそ、今は母親に安心してもらえることを第一に考え、病状や経過を細かく説明している。そんな診察を急患センターでもしていることから、いつの間にか朝となっていることも多い。
「患者さんがものすごく多かったり、例えば嘔吐や下痢が流行って、そんな患者さんばかりだと、みんな同じように処置してしまったりして…。その中で、自分も少し引っかかることがあったんですけど、明日の朝、また来てもらえればと思って。しかし、その待っている間に急変されたという例も…」
佐藤さんが、母親本位の診療を行うようになったきっかけはそんな苦い経験でからだった。

一方で、それまでにも母親の「子どもがいつもと違っておかしい」との言葉を信じて、入院させることで助けられたという例が多かったという。
「ここ十何年か小児科医をしてきて、お母さんがおかしいって言ったときは、90%はやっぱりおかしいことが多いし、急変する場合もある。だから、それはもう重要な訴えだと思っています」
なお、この急患センターでも課題はある。患者を最初に診察することは出てきても、入院させることができないのだ。

入院させた方が患者も安静でき、母親も精神的に安心する。しかし実情は、この大都市・福岡でも夜間に子どもの入院を引き受けてくれる病院がひとつもない。
夜間でも子どもの救急治療入院が可能にというのがウリだった、厚生省の診療報酬引き上げ策はまだまだ実行力を持つにはほど遠いようだ。
佐藤さんも、夜間入院を引き受けてくれる病院探しに奔走するが、小児科の当直医がいないため拒否されるケースがほとんどだという。

故郷で小児科を開業
そんな中、佐藤さんは2001年春に、故郷の大牟田市で小児科を開業することを決めた。急変しやすい子どもの病気を、自分ができる範囲で、自分の納得のいくような場所を作りたいとの思いからだった。
「わざわざ1時間くらい待って、1分とか2分とか診療時間が短いし。診察が終わって帰られるときも、親御さんの顔を見た感じとして納得されてないなという、後ろ髪を引かれるような思いが残ることもありました。しかし、次の患者さんが待っているということで、どうしようもできないというジレンマがあった」
無我夢中で働いた総合病院での勤務医時代には、つらい経験もあったという。「あの時、もうちょっと自分が注意していれば、こういう結果にならなかった」と後悔したことがあり、「絶対そういうふうなことがないようにしたい」と決意をあらたにしている。

しかし、小児科は“子どもが少ない”“もうからない”のないないづくしで、開業に不安はないのだろうか。
「一人でも患者さんが来られて、その親子にとって、少しでもお役に立てるので、もうそれでいいと思っています。たとえ一人、二人しか来られなくても、それで自分にとって納得できればいいと思います」
医療を医の生業、医業と履き違え、小児病棟は閉鎖縮小に追い込まれている。リストラされる小児病棟。厚生省のデータでは、1998年までの8年間に姿を消した小児科は全国で400に上るが、さらに拍車がかかったといわれる。
(第9回FNSドキュメンタリー大賞受賞作品 『母だからこそ…―リストラされる小児病棟』 テレビ西日本)
その後も小児科病院は減り続け、2019(令和元)年10月1日時点で、全国の小児科病院の数は2539施設。1998年と比べると、約1200も減少している。
一方で2018(平成30)年の小児医療に関する検討会では、「小児中核病院、小児地域医療センターのどちらも存在しない圏域では、『小児地域支援病院』を設定し、拠点となる医療機関等と連携しつつ地域に必要な入院診療を含む小児診療体制を確保する」としている。






