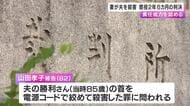大分市で発生した大規模火災では、住宅密集地での火災の危険性が指摘されました。
一方、そうした危険な住宅密集地が全国で最も多いのが大阪です。
大阪市西淀川区で21日に発生した火災も住宅密集地の路地の奥で火災が起き、住宅5棟、合わせて150平方メートルが焼けました。
【火災現場付近の住民】「不安でした。風向きで燃え移れへんか…(家が)密集しているんですよ。文化住宅とかアパートとかもあるし…」
行政が危険な密集地について“2030年度末の解消”を目指す中、戦前の建物が残る街では、建物が撤去され更地になっているエリアも。
大阪の“危険な住宅密集地対策”を徹底取材しました。
■大分市佐賀関の住宅密集地で170棟以上が焼ける大規模な火災
住宅密集地ではたちまち炎が広がる不安があります。
18日には大分市佐賀関(さがのせき)の住宅密集地で、170棟以上が焼ける大規模な火災が起きました。
【近隣住民(18日)】「山の方まで燃え移っている。(住宅街の)中の道は人が1人通れる道が入り組んでいる感じ。なかなか入っていけないところ」
火災から4日目で、離島以外の火はほぼ消し止められましたが、多くの住人が、21日現在も避難所での生活を続けています。
空からみるとその密集具合がよくわかります。
火災翌日の映像では、どこに道があったのかわからず、消防車からホースを長く伸ばして消火していた様子が見てとれます。
【記者リポート】「火災現場の近くです。このように手を広げると壁に当たってしまうほどの細い路地の両側に、家は密集して立ち並んでいます」
■“危険な密集地のおよそ7割が関西に集中”
住宅などが密集する場所での大きな火災は関西で、何度も起きています。
全国の危険な密集地のおよそ7割が関西に集中していて、このうち大阪市がおよそ640ヘクタール=甲子園球場160個分の広さを占めていました。
一方、大阪市の横山市長は解消に前向きな姿勢を示しています。
【大阪市・横山英幸市長】「令和12(2030)年度末の解消にむけて、残る密集市街地の対策につとめて参ります。国が定める『危険密集市街地』について、全て解消する予定です」
大阪府全体で、この危険な密集地を、5年後までにゼロにするための計画が進められていて、大阪市も、3年前と比べると、およそ400ヘクタール減らしています。
こうした計画はどうやって進めているのでしょうか。
■“昭和一桁台”という建物も残る 大阪・生野区では
取材班が訪れたのは、大阪市生野区。戦前から建物があったといい、建てられたのが“昭和一桁台”という建物も残っています。
生野区は第二次世界大戦の際、空襲の被害をほとんど受けなかったため、住宅や商店、工場が混在して密集する戦前からの街の姿が多く残り、狭い道路もいたるところにみられます。
【大阪市都市整備局・生野南部事務所 橋口孝幸副所長】「昔からの道路で、建築基準法(1950年制定)ができる前から道路として存在してましたので」
生野区の南部地区は地震や火災が発生した際、延焼し、避難も困難になる恐れが強いとされる”危険な住宅密集地”ですが、今、大きく変わろうとしています。
■「土地の買収の8割が済む」建物が取り壊され更地に
街の中のある区画は、すでに建物が取り壊されていました。
【大阪市都市整備局・生野南部事務所 橋口孝幸副所長】「建物を解体して更地にして、フェンスを張っています。ここに地元のお地蔵さんがあったんですけど、それも含めて、撤去して、更地にしております」
衛星写真で見比べても、住宅が密集していた場所がなくなり、今は多くの部分が空き地に変わっています。
密集地の解消は地元からの要望の声もあって進んだといいます。
【大阪市都市整備局・生野南部事務所 橋口孝幸副所長】「建物がほとんどくっついている状態ですので。
消防車が入れないところは、やっぱり一回火が出てしまうと止められないんで、やっぱりそういうことをなくすために、街をどうしようかという意見が地元であって。
それを受けて大阪市と一緒になって、街づくりを考えて、それを具体化していっている」
こちらの地区では土地の買収の8割が済んでいて、計画では2029年度以降に事業が完了する予定で、その後は公営住宅を建設するほか、道路も広げる見込みです。
■「今更知らんところで仲良くなれるかというと難しい」移転進まない地域も
一方で、簡単に対策を進められない地域もあります。同じ生野区の北鶴橋地区はその1つです。
【北鶴橋連合振興町会 田中照章会長】「大分と同じようなことが起こるでしょうね。
消火活動に入ってきても、消防車がなかなか入れない。まして、長屋。全部、壁一枚でつながってるので、火の回り早いでしょうね」
この地区も危険な密集市街地に指定されていますが…
【北鶴橋連合振興町会 田中照章会長】「折角、自分らが長い間住んできて、今更よそ行って、知らんとこでみなさんと仲良くなれるかというと難しい」
大阪市によると、「家に住み続けたい」、「相続が面倒」などの理由で、整備が始まっている地域でも買収が進まないケースが多くあるといいます。
果たして、大阪市はあと5年で、危険な住宅密集地をゼロにすることができるのでしょうか?
【大阪市・横山英幸市長】「これまでも着実に取り組みは進んでいるので、引き続き、ご理解を得ながら、密集市街地の解消に取り組んでいきたい」
■京大・藤井教授『“積極的”都市計画を』と提言
こうした危険な密集地の対策について、都市計画の専門家である、京都大学大学院の藤井聡教授は『“積極的”都市計画を』と提言。
立ち退きをしてもらう人たちには、コミュニティを維持して移転する方法などを行政が提案して、進めるべきだと話しました。
【京都大学 藤井教授】「戦後80年間問題になってきた、土地区画整理事業、いわゆる木造家屋の密集地帯の解消をどうするかという問題を、大阪市は今本気で取り組もうとしています。
都市計画で行政が本気で、積極的に取り組んでいくと、ハードルを乗り越えていきやすくなるんですよ。
まず計画を立てて、(土地の)買収を進めて、立ち退いてもらった人たちに住んでもらう代わりの場所に、かつてのコミュニティーをそのまま保存するような移転などといった、合理的な計画のやり方を積極的に行政が関与していけば、道が開けると思います。
(大阪市は)目標年度を決めて進めておられるので、積極的に行政が関与して、かつ納税者も公共性があると理解して、協力してもらえると道は開けるんじゃないかと思います」
(関西テレビ「newsランナー」2025年11月21日放送)