11月4日、兵庫県加古川市の国道250号線で13台の車が絡む大きな多重事故が発生した。
この事故で1人が死亡し、2歳から6歳の子ども3人を含む12人がけがをした。
鳴り響くサイレン、大破した車。事故現場は壮絶な光景となった。
■加古川で発生した車13台が絡む多重事故
近くに住む人:ドーンって音が聞こえたあとに、キッチンにいたんですけど、少し家が揺れた感じがして、『やばい、やばい』という声が聞こえた。
関西テレビが入手した事故の瞬間をとらえたドライブレコーダーの映像には、左前方を走る白い車が映っていた。
これが事故を起こした車だ。
最初は前の車との距離がまだあったが、突然スピードを上げて前の車に衝突。当たった車は180度回転し、その後も速度を落とさず、信号待ちの車列に突っ込んだのだ。

■急性心筋梗塞が引き起こした悲劇
運転していたのは近所に住む78歳の岡本年明さん。一時、車の中に取り残され救出されたが、死亡が確認された。
なぜ、このような事故が起きたのだろうか。岡本さんの車に同乗していた男性が重要な証言をしている。
岡本さんの車に乗っていた男性:岡本さんが事故直前に発作を起こして意識を失い、ハンドルにもたれ掛かっていた。
警察などによると、岡本さんは淡路島で釣りをして高砂市を経由した後、突然意識を失ったということだ。
その後の行政解剖の結果、岡本さんの死因は急性心筋梗塞による病死で、体調の急変で車の制御ができなくなったとみられている。
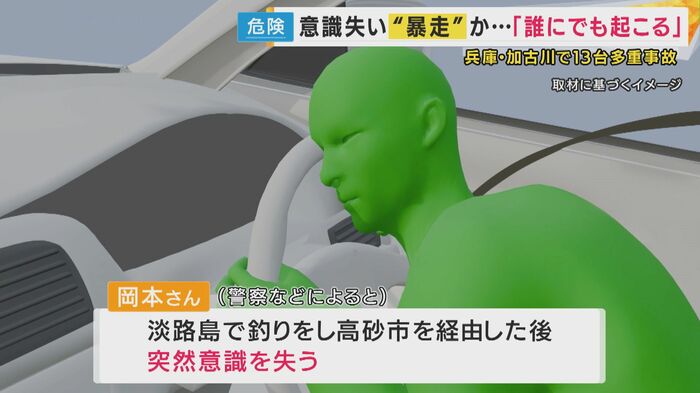
■運転中の急病「誰にでも起こりうる」
このようにドライバーの急病や発作が原因で起こる事故は、年間200から300件ほど報告されている。専門家は「誰にでも起こりうる」と指摘する。
滋賀医科大学社会医学講座 一杉正仁教授:大きな脳出血、心筋梗塞以外に、一時的なめまい、てんかん発作も含めた意識消失が原因になると思う。
運転は集中力を保たないといけないのと、ある程度緊張します。運転していないときに比べて血圧は上がる。
集中力を維持しないといけないということでストレスがかかる状態。決してこれは、高齢者だけの問題ではない。
多くの病気を持っている方だけの問題でもありません。どなたにも起こりうること。
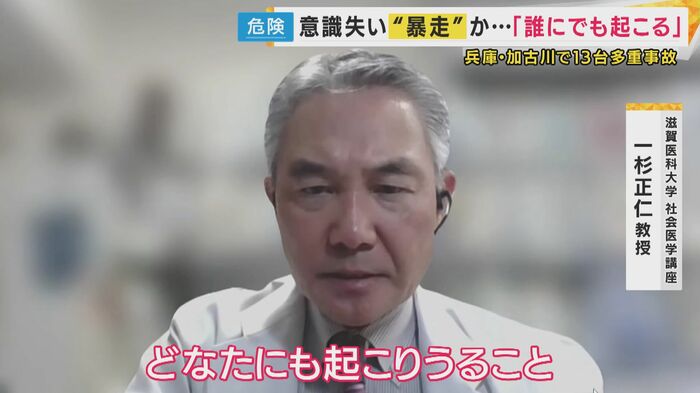
■なぜ13台もの車が巻き込まれたのか
12人もの負傷者を出した今回の事故。1台の車の暴走がなぜ12台もの車を巻き込む事態となったのだろうか。
「newsランナー」取材班は、”交通事故の鑑定官”として多くの事故を捜査してきた専門家と現場へ向かった。
現場で小西公昭さん(元京都府警交通事故鑑定官)の目に留まったのは、交通量の多さだ。
取材した時間は交通量が少ないとされる昼の時間帯だったが、信号待ちでは多くの車が止まっていた。
さらに、信号待ちをしている時の車間距離についても指摘があった。
元京都府警 交通事故鑑定官 小西公昭さん:(車間距離は)みんな1車長までは足りない。3メートル台かな。1車長というのは、大体4メートルから4.5メートル。そこまでは空いていない。
目安となる、およそ4メートルの距離を取る車は少なく、玉突きによって多くの車が巻き込まれた可能性があるということだ。
(Q.車間距離がある方がリスクは減る?)
元京都府警 交通事故鑑定官 小西公昭さん:そうです。車線の数、信号で止まる車の数を考えたら、ここだから大きな事故になった。

■身を守るために必要な「適切な車間距離」
取材班は事故があった夕方の同じ時間帯に車で現場を訪れた。昼間より交通量が増え、車間距離についてはかなり近い状況も見られた。
元京都府警 交通事故鑑定官 小西公昭さん:後ろから当てられる交通事故は、不可抗力的なもの。信号で停止してるわけだから。でも、被害の軽減を考えるなら、停止するのにも適切な車間距離で。バンバン詰めたりはしない方が良いですね。
では、どれくらいの距離を取るべきなのだろうか。
(Q.車間距離の目安は?)
元京都府警 交通事故鑑定官 小西公昭さん:車1台分ぐらい空けて、停める方が好ましいですよね。
急病による事故は予測が難しいものだ。しかし、適切な車間距離を保つことで被害を軽減できる可能性がある。
日常の運転で意識したい重要なポイントと言えるだろう。
(関西テレビ「newsランナー」2025年11月6日放送)






