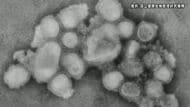国宝・松本城天守の建てられた時期が、市が木材の伐採時期などを調べた結果、「1596(文禄5・慶長元)年から97(慶長2)年頃」とみられることが分かりました。これまでの見解より3年ほど遅くなっています。
松本城の大天守の創建年代には諸説あり、市は古文書などから「1593(文禄2)年から94(文禄3)年頃に乾小天守・渡櫓とともに建てられた」を公式見解にして来ました。
市は正確に特定したいと、2023年度から24年度にかけ、使われた木材の年輪から年代を特定する調査を行いました。
奈良文化財研究所・光谷拓実名誉研究員:
「こちらの木材の面皮がほんの一部残っている場所があって、ここで1596という年代が確定できたわけです」
5重6階の大天守のヒノキを調べた結果、1596(文禄5・慶長元)年に伐採されたものと判明。伐採から時間を置かず、1階から6階まで翌年頃までに建てたと見られることがわかりました。
名古屋工業大学・麓和善名誉教授:
「伐採年代が科学的に判明したことから、本来持っている価値に加えて、文化財的、建築史的な価値がさらに高まった」
大天守の30年ほど後に月見櫓と共に増築したと考えられていた「辰巳附櫓」については、構造などを詳しく調べた結果、大天守と同時期に建設されたとみられることもわかりました。
また、優雅な朱塗りが施され「戦から平和の時代に移った象徴」とされる月見櫓には、1626(寛永3)に伐採されたツガの木が使われていることもわかりました。
従来は、1630年代に3代将軍の徳川家光を迎えるため増築されたというのが定説で、新たな発見となりました。