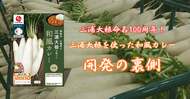ファッション・ビューティー領域に特化したソリューション・グループ、ワールド・モード・ホールディングス(WMH)のビジネススキームは、ユニークで他に例がない、文字通り唯一の存在です。人材の採用育成、店舗運営、マーケティング、空間デザインなど、専門性の異なる企業が集まり、クライアントの課題に応じて協業することで多岐に渡るソリューションを提供しています。
本ストーリーでは、「越境ECからはじまる海外進出支援」をテーマに、WMHグループの取り組みをご紹介します。
DXとマーケティングの専門的知見から探る、越境ECの今とグローバル戦略の可能性

写真左から:GDX(株) 代表取締役 洞田潤氏
(株)AIADおよび(株)双葉通信社 代表取締役 小西聡
リテールの領域で企業のDXを支援するGDXと統合型マーケティングソリューションを提供するAIAD(アイアド)は、ビジネスパートナーとして相互の事業成長に向けて協業を進めてきました。そして今、越境ECを通じて日本発のファッション・ビューティーブランドのグローバル展開を成功へと導くために、WMHの店舗運営と海外進出支援の知見も融合した包括的なソリューションの拡充と協業体制の強化を図っています。
海外市場へ挑戦するクライアント企業の成功をどのように支援し、成長を後押ししていくのか。GDX代表取締役の洞田潤氏とWMHグループのマーケティング事業を率いるAIADおよび双葉通信社代表取締役 小西聡の対談を通して、近年勢いが増しているグローバルEC市場の今を紐解くとともに、ふたりが描くグローバルなマーケティング戦略を深掘りしていきます。
強みの掛け算で切り拓いた越境ECの可能性
―GDXは2007年に創業し、ブランドのDXをサポートされてきました。創業当初から越境ECに力を入れていたのでしょうか?
洞田:2007年当時は、ほぼ国内向けのECだけをやっていました。海外展開を始めたのは2012年頃で、最初はインドネシア事業からです。海外展開には大きく分けて、日本から海外に販売するいわゆる越境ECと、現地に在庫を持ち現地でECを行う海外ECがあります。インドネシアでは後者のビジネスから始めました。そのとき扱っていたのは錦鯉や盆栽といった日本文化を象徴するような高級商材でした。当時、Facebookが急速に普及してきた時期で、それを活用したソーシャルコマースで各国の富裕層に日本の商品を販売していました。
―当時はソーシャルコマースという言葉はほとんどなかったかなと記憶しているので、まさに先駆者ですね。
洞田:2017年から本格的に海外展開へシフトし、国内のEC事業を縮小して、ほぼすべてを海外事業へと移行しました。事業のスクラップ&ビルドを一斉に行い、人材面・ノウハウ面・資金面すべてで大規模な構造改革を行いました。その大変な時期に、全面的にサポートしてくださったのがWMH代表取締役の加福さんと小西さんです。当時、私たちの挑戦に非常に前向きかつ積極的に賛同・応援いただき、そこから現在のグローバルEコマースの取り組みが始まりました。
小西:私は2017年にAIADの代表取締役に就任したのですが、最初に取り組んだ仕事が五反田電子商事(現GDX)との事業提携と出資です。
当時、AIADの業績は低迷しており、デジタル変革を進めることが急務となっていました。しかし社内にノウハウを持つ人材がいなかったので、五反田電子商事と提携することで短期間にデジタル化を達成しようという意図もありました。結果として、AIADの事業改革は一気に進み業績回復に繋がりました。洞田さんは先ほど「支援していただいた」とおっしゃっていましたが、デジタルシフトが円滑に実現できたのは、洞田さんが寄り添って、AIADの事業変革に手を貸してくださったおかげです。本当にお互いにとってたいへん意味のある提携でした。



越境ECの現状とは?成長を続ける市場で勝ち続けるためのヒント
―今では越境EC市場を牽引する存在となっていますが、ファッション・ビューティー領域における越境EC展開の現状をどのように捉えていますか?
洞田:現在、「グローバルEC」は世界的に見ても成長が続いている分野のひとつです。その中でも、越境ECは特にここ数年で急激に成長し、かつ地に足のついたビジネスモデルとして確立されてきました。
コロナ以前はEC化率も越境ECの規模もまだまだ小さく、「ECはリアル店舗を補完するチャネルのひとつ」という状況でした。しかし、コロナ禍でステイホームとなったとき、「ECは日常生活に必要不可欠」という認識が広がりました。さらに、世界的に見てもコロナ後は、人々の海外への関心や行動が一気に活発になりました。「世界中の良いモノをいつでも手に入れたい」という欲求が高まり、ステイホームの反動から多くの人々が一斉に海外旅行に出かけ、旅行先で今まで知らなかった海外ブランドとのたくさんの接点が生まれました。その結果、消費者の購買領域が広がり、「欲しい」と思ったら国内問わずすぐにECで購入するという習慣が、多くの人々に広がりました。
直近では、米国の関税政策などによる変動もありますが、EC業界全体は成長が続いており、さまざまなチャンスが生まれています。今後もEC市場は安定成長が続くと予想されており、それに伴い投資が集まり、AIなどの新技術も積極的に導入されることで、さらに発展していく循環に入っていると考えています。

小西:ECビジネスには、越境ECだけでなく海外のローカルECマーケットプレイスや現地自社ECとの連動もあります。GDXが提供しているサービスはいくつかのステップに分かれていて、クライアントの事業フェーズに合わせて展開されていますよね。
洞田:まず、越境ECとインバウンド送客を狙って国別に展開を図り、可能性の高い国を特定します。次に、その国のローカルECマーケットプレイスに出店し、何が売れ、どのように動くのかというデータを収集します。そして「本格進出できる」と判断すれば、その国向けの自社のグローバルECを立ち上げます。顧客の動きを追いながら、最終的に国をまたいだ人の動きも捕捉できるグローバルCRMへと発展させていくイメージです。
小西:このプロセスにおいて、AIADはブランディングや送客などデジタルマーケティングの領域を支援しています。また、WMHではリアル店舗の運営や流通開発、人材サービス・教育、受発注や在庫管理、物流、さらにはシステム開発までを担う「新しい店舗運営受託ビジネス」を一部マレーシアなどで展開しています。
GDXのECビジネス支援、WMHのリアル店舗領域の事業、ブランド認知を高め、送客するAIADのデジタルマーケティングを掛け合わせることで、リアル店舗とECのハイブリッド型サービス提供が可能になります。これが私たちの目指すグローバルな事業支援の最終的なイメージであり、それを洞田さんと一緒に推し進めたいと考えています。

WMH、AIAD、GDXの協業による海外展開支援のイメージ
洞田:ある資料によると、日本企業のファッション領域に限らず、日本の越境EC市場は2030年頃には7.9兆円〜8兆円規模に達するとも言われています。日本国内のアパレル総市場規模の見込みは約6兆円ですから、越境ECは今後、非常に大きなマーケットになることが予測されます。
成功のためのカギは「トップダウン」と「マーケティング力」。日本発ブランドの越境EC展開における課題
―越境ECやグローバル展開への関心が高まっているというお話がありましたが、一方で攻めていくためには課題も多いのではないかと思います。特に、日本企業が越境ECやグローバル展開において直面している課題について教えてください。
洞田:日本企業は韓国や中国の企業と比べて、海外進出をスピーディーに進めるのが難しいと感じています。特に思い切った投資判断には十分な検討を重ねるので、時間が必要です。これは組織経営の問題でもあり、トップダウン型の会社は決断が早く円滑に進めますが、ボトムアップ型の会社の場合はなかなか動きだすことができなかったりします。
さらに、国内だけである程度の規模を維持できてしまうために、それで満足して海外に出ないという企業も少なくありません。その結果ガラパゴス化してしまい、海外で通用しづらい状況があります。持続的な成長を目指すには、グローバルな視点で成長機会を捉えていくことが必要ではないかと思っています。
小西:日本の企業統治の仕組みが影響しているとも考えられます。ボトムアップ型だと、何かを決めるときに多くの人が集まってコンセンサスを取る。全員が賛成したら進む、というやり方です。でもそのスピード感では海外企業には太刀打ちできません。トップが「やる」と決断して旗を振らないと、海外進出は難しい。
洞田:弊社で支援しているあるアパレル企業は全く逆の姿勢で、会長や社長が全域のプロジェクトに直接参画しています。海外進出は、トップや役員の強いコミットメントがなければなかなか進みません。
小西:「パナソニック」「ホンダ」「ソニー」「ユニクロ」など、日本を代表するブランドを展開する企業は成長過程の早いタイミングで決断し、海外展開を進めています。経営者がリーダーシップを発揮し、意思決定している。逆に、成長が進み、官僚的な体質になると動きにくくなる気もします。

―日本と海外を比べたとき、ファッションやビューティー領域で勝っていくために、今足りていないのは何でしょうか。
洞田:まず、消費者をつかむためのマーケティング力が足りていません。どの国の人が、どういうものを好み、何を求めているのか。マーケティングの4P(Product、Price、Place、Promotion)の中で、何を強化すべきかを把握する必要があります。
例えば、今人気の「オニツカタイガー」がなぜ世界中で売れているかというと、ブランドが確立されているのはもちろん、デザインが洗練されていてファッションアイテムとしての完成度が高いだけでなく、機能性と品質も優れていて、手に届く価格帯だからです。このバランスが強みであり、高い評価を獲得しています。一方で、日本の多くのブランドは、海外市場で成功するために自分たちのどこをどう強化すれば良いのかが明確にできていないまま挑戦してしまう傾向があり、そこが課題だと考えています。日本で成功しているから「この価格なら売れるだろう」と国内基準の発想で挑戦したものの、海外市場では通用せず、グローバルプライシングを見直してようやく成果が出てきた、という例もあります。
結局、「自分たちの商品がどこで、いくらで売れるのか」という感覚を持つことが必要なのです。だからこそ、徹底的にデータをもとに検証し、仮説を立ててマーケティング戦略を練る必要がある。これを繰り返し、精度を高めていくことが重要です。
小西:海外展開に関しては、ヨーロッパは技術力のみならずブランディングが非常に上手く、地域ブランドをグローバルに育てるのが得意です。
イタリア・パルマのプロシュート(生ハム)やパルミジャーノ・レッジャーノ(チーズ)、ノルウェーのトロムソやベルゲンのサーモン、デンマークの豚肉などは地域名から品質の良さが想起されますし、オランダのアールスメールやリッセは、チューリップ、バラなど花の名産地としてのブランドを確立しています。工業製品でもイタリア・モデナの「フェラーリ」「マセラッティ」、ボローニャの「ドゥカティ」、ドイツ・シュトゥットガルトの「ポルシェ」などは世界中のファンを魅了しています。
ファッション分野でも、イタリアのペルージャやプラートの「ニット製品」、コモ湖周辺の「シルク」など、地域の名産や伝統を活かしてブランド化する事例が多くあります。
日本はこのようなブランディングがあまり得意ではありませんが、グローバル市場での成長が期待される有望なブランドや製品が数多く存在しています。だからこそ、GDXとAIAD、WMHが培ってきた知見と経験をもとに、店舗とデジタルマーケティングの両面から、日本ブランドの海外展開を支えるパートナーとして寄り添っていきたいと考えています。


WMHグループとGDXの機能を融合し
店舗とデジタルマーケティングの両面からの支援を実現
成長を続けるEC市場。ここ数年が、ビジネスモデル構築や先駆者ポジション確立の重要な時期。
―海外進出に意欲のある企業を支援するにあたり、両社で推し進めていることはありますか?
小西:先ほど越境EC + インバウンド → ローカルEC → 海外自社EC → グローバルCRM の流れで攻めていくという話がありましたが、2028〜2030年頃までには、一連のビジネスモデルを構築したいと考えています。もしかすると洞田さんの方が、もっと早いイメージをお持ちかもしれません。
洞田:EC市場は今後も10年、20年という長期スパンで成長していくと見ています。ただし、現在のフェーズででは「先駆者としてのポジションを築くこと」が非常に重要だと思っているため、新規事業にも追加投資を積極的に行っています。特に今年・来年・再来年あたりが、市場をつくり上げるための最も重要な時期だと考えています。加えて、当社は来年にも上場を予定しており、全力で投資し、成長を加速させる方針です。
―かなり積極的に事業を進められていますが、何かきっかけがあったのでしょうか?
洞田:コロナ後のインバウンド需要の急増です。今まで知らなかった日本のブランドや商品に触れる機会が増え、新たな発見や認知が広がりつつある今、リピーターやファンが増えていく良いタイミングに入っていると思います。
この時期に、より早く届く物流体制や多様な品揃え、送料や関税をセーブしたプライシングなど安定したサービスを提供できれば、大きなファン層を獲得できると考えています。また、日本ブランドの多くは海外展開が遅れていますが、インバウンドでの成功体験があれば海外でも売れるという見込みに繋がります。この流れを後押しし、早めに準備を整えることが大切だと思います。今年から再来年までにステップアップし、その後はオムニチャネルや現地店舗展開を進め、最終的にはCRMでの囲い込みにつなげていく。これらのフェーズにビジネスパートナーとともに取り組むことで、市場全体を大きく成長させていけると考えています。
小西:御社は発注予測、在庫管理などにもAIを導入されていると伺っていますが、そのあたりの投資も積極的ですよね。
洞田:はい。シリコンバレーに拠点を設け、スタンフォード大学と連携して現地の学生をインターンとして受け入れ、BtoC領域やEC領域に活用できるAIを開発しています。利益構造を改善する取り組みを行っており、すでに実装も始まっています。その他にも、「パナソニック」とは生成AIを活用した需要予測システムを共同開発しました。
小西:そうしたGDXのソリューションをグローバル全域に導入して、海外展開を順調に拡大され、現在はヨーロッパやアジアに多数店舗を展開されている事例もありますよね。この海外展開にはAIADも参画し、広告やデジタルマーケティングの部分を支援させていただきました。
洞田:以前からデジタル支援をさせていただいている、数少ない日本発のラグジュアリーブランドとしてワールドワイドに展開する、急成長中のブランドです。海外事業では、世界の主要都市に旗艦店舗を構えてブランド体験を最大化する場として位置付け、その後の購買は自社ECで行ってもらうという、特徴的な展開をされています。デジタルが非常に重要な役割を果たしており、旗艦店の立ち上げと並行してデジタル面を当社が構築しました。

日本のブランドを世界に羽ばたかせるために
― オムニチャネルの話が出ましたが、現在L Aに日本ブランドの海外展開とブランディングを支援するオムニチャネルストアを計画しているそうですね。
洞田:「日本のホスピタリティを体感できる空間」をテーマに、日本のブランド発信拠点となる「プレスルーム兼セレクトストア」を計画中です。ターゲットはキム・カーダシアンのような一流の海外セレブリティ。彼女やその周辺にいる人たちが好むブティックを目指し、ラグジュアリーブランドのヴィンテージアイテムに日本ブランドのアイテムをうまく織り交ぜ提供するという構想です。
ブランド構成は、ラグジュアリー感を醸成するためにラグジュアリーブランドのヴィンテージアイテムを取り入れながら、LAのセレブリティが好むテイストにあった日本発ブランドや日本人デザイナーによるアイテムをセレクトします。審査基準は厳密に設定しますが、条件を満たせば小規模ブランドでも参加可能です。商品を展示するスペースはブランドの世界観がわかるようなデザインにします。店舗奥にはアメリカンジャパニーズスタイルの寿司を提供するカウンターを設け、セレブリティにゆったりと過ごしてもらいつつショッピングを楽しんでいただきます。
PRを打つのではなくセレブリティを囲い込み、オーガニックの発信を行ってもらうことで、「本物のトレンド」を作っていきます。そのため、この店舗は単なる販売拠点としてではなく、日本ブランドを世界へ広めるためのゲートウェイ拠点という位置付けにしています。
― ありがとうございます。最後に、近い将来、遠い将来を含めて、今後の事業展望をお聞かせください。
洞田:日本のブランドには、もっと世界に羽ばたいてほしいし、そのための仕組みを我々が整えサポートしたいと思っています。「国際都市に進出したい」と思った翌日から展開できるくらいのスピード感で動けるソリューションを作りたいです。
最終的には、「グローバルでビジネスをやるって楽しいよね」という感覚を広げたい。ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、そしてスペインなど、どこに行っても拠点がある状態にしたいです。現地での運営はWMHと我々GDXで完結できるようにして、NY、パリ、ミラノのファッションウィークなど国際的な舞台にどんどん出ていく。そういう流れを、5年以内に作れたら嬉しいですね。
― ありがとうございます。小西さんはいかがでしょうか。
小西:現状、WMH全体の売上比率で言うと海外事業は10%程です。クライアントはラグジュアリーをはじめワールドワイドに事業展開をするブランドが多いのですが、我々の事業活動は国内が中心で、海外展開はまだまだこれからです。
WMHはファッション・ビューティーに特化し、経営課題の対応から店舗運営まで、一気通貫で様々なサービスを提供していきます。クライアントがワールドワイドに活動しているのであれば、我々も同じフィールドに出ていく必要があります。現在はAPACエリアに注力していますが、欧州や米国への展開は、その延長にある将来像です。
しっかりと日本ブランドを世界へ発信し、その事業成長を支えていける仕組み作りを、私たちの力で実現していきたいです。
※WMH STORY vol.1、vol.2、vol.3もぜひご覧ください。
【ワールド・モード・ホールディングス株式会社について】
ファッション・ビューティー業界を専門に人材やデジタルマーケティング、店舗代行など様々なソリューションを提供するグループ。iDA、BRUSH、AIAD、AIAD LAB、フォーアンビション、VISUAL MERCHANDISING STUDIO、双葉通信社 の7 社の国内事業会社および シンガポール、オーストラリア、台湾、ベトナム、マレーシアに海外拠点を持ち、専門性の高い各社のシナジーによって、クライアント企業の課題に応じた実効性の高いソリューションを提供しています。
【株式会社AIADについて】
メディアありきの課題解決ではなく、クライアントの課題から導きだしたソリューションを提案。広告・SP・CRM・OEM・ライセンス・EC・SNS。ファンクションを自在に組み合わせ、さらに顧客やマー ケットの本質、ブランドの強みを加えたビジネスモデルを構築します。
【GDX株式会社について】
「ワンクリックで国境を越える小売を実現する」をミッションに、グローバル市場でブランドの成長を加速させるリテールDX企業です。生成AI、ECプラットフォーム、業務自動化ソリューションを駆使し、戦略立案からシステム開発、運用支援まで、独自のオムニチャネルソリューションを一気通貫で提供。アメリカ、インド、東南アジアをはじめとする世界各地の拠点から、各地域の商習慣や顧客ニーズに応じたデジタル戦略を展開しています。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ