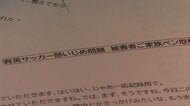「初めて見た政治家の姿」ジャーナリストの視点
宮城県の村井嘉浩知事が検討していた「土葬墓地」整備。その撤回は、国内外に議論を広げている。
全国の土葬問題や外国人労働者の取材を続けてきた、元ニューヨークタイムズ東京支局のフリージャーナリスト・鈴木貫太郎さんはこう語る。
「積極的にこの問題に食い込んで、真正面から取り組もうとした政治家を見たのは初めてでした。率直に言うと残念です」
鈴木さんは今年3月、各地の土葬問題を取材した著書を出版。その中で村井知事への取材も行っていた。取材では、バングラデシュ出身で石巻市在住のソヨドさんの存在が話題になったという。
「ソヨドさんは津波で流された民家の再建に関わるなど、東北の復興を支えた人です。村井知事は『犯罪を助長する外国人が来てほしいわけではない。東北の経済に貢献した人には報いたい』と語っていました。市町村長の誰かが受け入れに手を挙げれば、論理上は可能だと期待していたのです」
土葬をめぐる全国の動き
一方で、鈴木さんは「土葬に理解を得る難しさ」を全国取材で痛感してきた。
大分県日出町では去年、イスラム教徒向けの土葬墓地計画が町長選の争点となり、反対を訴えた新人候補が現職を破って当選した。
「まず、日本にかつて土葬文化があったことがあまり知られていない。大昔ではなく比較的最近まで残っていたのに、火葬が急速に進んだ背景を多くの人は意識していない。『日本では火葬しかできない』と考える人が多いのが前提です」
「唐突感」が招いた撤回
村井知事が今回「撤回」を決断した背景について、鈴木さんはこう推察する。
「知事が議会で構想を打ち上げたことは、やはり唐突感があったのではないかと受け止めています」
整備を目指す理由や考えが広がらないまま、反発や不安が膨らんでしまったと指摘する。
外国人理解をどう深めるか
鈴木さんは「日本社会が外国人理解を深める岐路に立っている」とも指摘する。
観光客として短期滞在する外国人と、日本に拠点を置き定住する外国人は分けて議論すべきだと強調する。
「『外国人問題』とひとくくりにされがちですが、きちんと言葉遣いを丁寧にして、1つ1つ議論する必要がある。違う文化に接した時に人は違和感を覚えますが、それは責められる感情ではありません。違和感を憎悪につなげるのではなく、理解へと変える力学が社会に働けば、解決へ進めると期待しています」
未来への課題
「理解を深める努力を続けない限り、土葬墓地にはたどり着けない」
各地の現場を歩いた鈴木さんはそう語る。
村井知事が掲げた「土葬墓地」構想は撤回されたが、外国人労働者の増加が続く日本において、宗教や文化をどう受け入れるかという問いは残されたままだ。