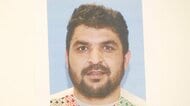米国務省が、トランプ氏の選挙勝利にショックを受けた職員の精神的治療のために、官費でセラピーを開催していたことが分かった。
「変化の中でのストレスを管理」国務省で“官費セラピー”
この情報は11月11日にニュースサイト「ワシントン・フリービーコン」が複数の国務省高官の話として伝えたもので、それによると国務省ではトランプ氏が再選を決めた直後「変化の中でのストレスを管理する」という件名のメールが全職員に送付され、大統領選挙の結果について感情を話し合う1時間のセッションに参加するよう促した。
‘Managing Stress During Change’: Biden-Harris State Department Holds Therapy Session After Trump Winhttps://t.co/JliqxXpdLF
— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) November 11, 2024
その結果、8日早朝に第1回のセッションが開催され、資格を持った臨床専門医によって「ストレスを管理し、健康を維持するためのヒントと実践的な対応策」が話し合われたという。
第二次トランプ政権では、米国の内外政策が大幅に変わると予想されるが、中でも外交は「国際協調主義」のバイデン政権から「アメリカ・ファースト主義」へと180度の変換が予想される。バイデン政権がこだわってきたウクライナ支援はトランプ政権では無下にされそうだし、ガザ紛争でもイスラエルの立場が強化されることが考えられる。ある意味で、米国の行政機関の中で第二次トランプ政権の誕生の影響が最も大きいのが国務省になるのかもしれない。

国務省職員としても当然その変化を覚悟すべきだったと思うが、選挙を前にワシントンの官庁街の雰囲気には「まだハリス副大統領の可能性がある」と淡い期待感があったのだろうか。
「外交官が国民の意思に従えないのであれば辞任を」
それはともかくとして、その国務省がトランプ新政権の外交をつつがなく展開できるのか、疑問視する声が議会内から上がった。
下院外交委員会の委員で、次期委員長の呼び声が高いダレル・アイサ議員(共和党・カリフォルニア州)が11月19日、この件をめぐりブリンケン国務長官に次のような抗議文を送った。
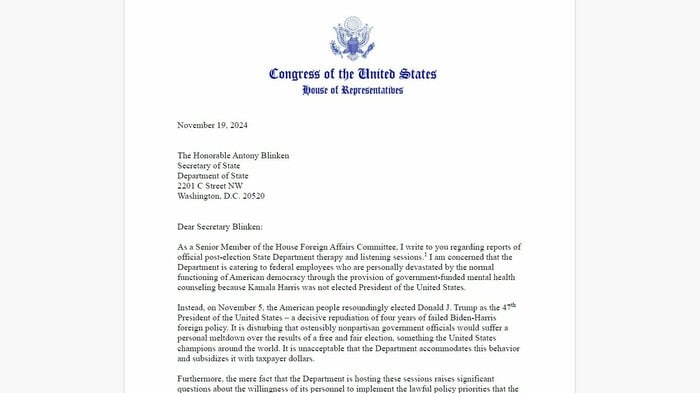
「2024年11月5日、アメリカ国民はドナルド・J・トランプ氏を第47代アメリカ合衆国大統領に選出しました。これはバイデン=ハリス政権の4年間の失敗した外交政策に対する決定的な拒否表明でした。自由で公正な選挙の結果に対し、表向きは非党派的であるべき政府職員が個人的に動揺するというのは憂慮すべきことです。このような行動に対応し、税金でそれを助長するようなことは容認できません。
さらに、国務省がこれらのセッションを開催しているという事実そのものが、職員がアメリカ国民が選出したトランプ大統領の合法的な政策優先事項を実行する意思があるのかについて重大な疑問を投げかけます。トランプ政権は外交政策分野で全面的な変革を行うという国民の委任を受けています。外交官がアメリカ国民の意思に従えないのであれば、辞任し、次の民主党政権で政治的任命を受けるべきです」

トランプ次期大統領は11月25日、中国やカナダ、メキシコからの輸入品の関税を増額する方針を発表し、1月20日の就任式を待たずに外交がスタートしている。その外交を司る国務省で、職員がいまだに政権交代を受け入れられずにセラピーを受けているような状態で米国は大丈夫なのだろうか?
【執筆:ジャーナリスト 木村太郎】
【表紙デザイン:さいとうひさし】