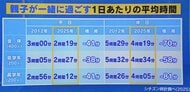自由気ままな子どもたちに、いつも親はハラハラドキドキ、時にもやもや。
「笑った!困った!」…。でもウチの子はどうしてこんなことするんだろう。その行動の裏には、知られざる“子どものココロ”が隠されているはず。
元気なココロちゃんとマナブくんきょうだいの育児に追われる小木(こぎ)さん一家に聞こえてきたのは、こんなお話。

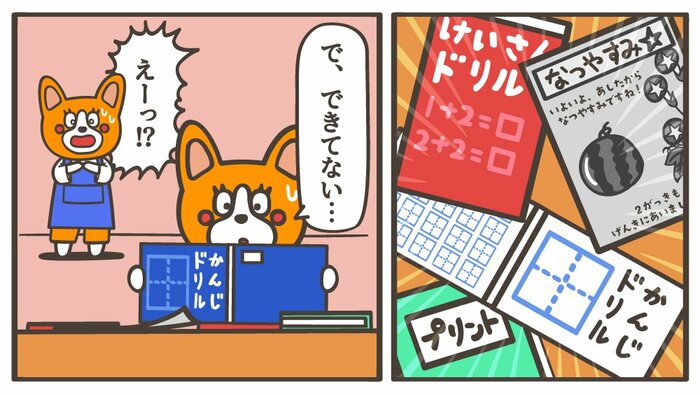

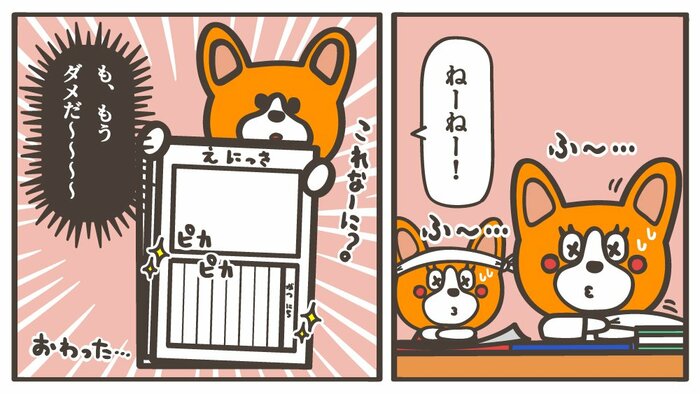
「夏休みの宿題、まだ余裕…。と思っていたら、いつの間にかあと数日で新学期!?」
まもなくやってくる夏休み。旅行に遊びにとすでに楽しみな予定がたっぷり入っているという人も多いはず。
そんな中でちょっと気がかりなのが、子どもたちの「宿題」!夏休みもあと数日という時になって初めて「えっ、宿題が真っ白…」と気付くなんてこともあるだろう。
「早め早めにスケジュールを立てて、コツコツ頑張ってほしい!」。そう思っているパパママは多いだろうが、「宿題しなさい!」と急かしても「まだまだ余裕だから~」と、ギリギリまで宿題に手をつけないのが、夏休みの子どもたち“あるある”。
今年こそは夏休み最終日にバタつきたくない!育児に役立つ“子育て心理学”を発信している公認心理師・佐藤めぐみさんに、解決法を聞いた。
普段は「シャキッ」でも夏休みはダラけちゃう子も
――子どもが「夏休みの宿題をギリギリまでやらない」理由って?
子どもに共通する一般的な特性として「好きなことを優先しがち」ということが挙げられます。待ちに待った夏休み。勉強よりも遊びが先、ということですね。
年齢も関係していて、小1の子の方が小6の子よりも「目の前の魅力に心を奪われやすい」と言えます。しかし、年齢が高くなるにつれて宿題は多くなる傾向があるので、高学年でも“宿題ギリギリ現象”は起こってしまいますが…。
性格の影響もあります。もともときっちりしている子は低学年でも早めに行動できますが「今が楽しければそれでよし」というタイプの子はどうしても宿題は先延ばしにしてしまいがちです。
また、普段の学校の宿題などはきちんとできても、夏休みだとダラけてしまうという子もいます。夏休みは長いので「まだ大丈夫」という気持ちが働きやすいのです。与えられた宿題が多く、どこから手をつけたらいいのかわからないというのもあるでしょう。
――そもそも「宿題をギリギリまでやらない」のは、親が注意するべき?
これは色々な考えがあると思います。たとえば「やるべきことは決まっているのだから自己管理すればよい」「子ども自身で向き合った方が結果的に時間管理を学べる」というような子どもの意向に沿う意見。逆に「まだまだ計画的に事を進められるわけではないから親のサポートが必要」「最後にまとめて“やっつけ仕事”的にやるのは身にならないから、親リードで進めるべき」という意見。
どちらが正解というのはありませんが、小さい子ほど計画を立てることがまだ難しいのはたしかです。なので「放っておけばギリギリになってしまうものだ」という捉え方はあながち間違ってはいないでしょう。
まだまだ「好きなこと優先」の時期ではあるので、夏休み最後のイライラやバタバタが恒例行事になっている場合は、子どもひとりに全て管理させないなど「期待し過ぎない」というのも大事かと思います。
子どものプランに無理がないかチェックして!
――では、パパママはどんなサポートをしたらいい?
先述のように、子どもたちの時間感覚はまだ発展途上中です。「うちはまだひとりで宿題をさせるのは難しいな」という場合は、子ども任せにせず、親も関わっていきましょう。
関わる場合のポイントとしては、
・夏休み開始時に親も宿題の全容を把握しておく
・毎日コツコツやるもの、まとめてできるもの、などタイプに分けてみる
・子どもと一緒に現実的に達成可能な計画を立てる
・そのペースに親も並走する
が挙げられます。
宿題をやるのは本人ですが、長い期間でのペース作りや配分は子どもには難しいものです。最初に宿題の全体像を見て、絵日記や観察記録のような“コツコツ型”以外のものがどれだけあるかを把握し、見通しを立てておくのは大事だと思います(分量が少なく最後の数日で終わるものであれば子どもに任せるのもあり。到底終わらないのであれば親が計画に関わってあげる、など)。
子ども任せにすると「ドリルを1日20ページやる」のような無理なプランになりがちです。まずは子どもに計画を自由に練ってもらって「これは無理だ」という場合に親がアドバイスしてあげるといいと思います。お小遣いの使い方と似ているところがありますが、子どもたちはまだ「手持ちのものを日々に分散させる」のが苦手なので、そこは親が関わってあげたいところです。
また、何より大事なのは計画の実行です。自分でできる子はいいですが、毎年ギリギリになりがちな子は、今年こそそうならないように日々のペース作りも並走してあげましょう。家庭学習は、毎日同じ時間に親子で座ってスタートできると習慣化しやすいので、忙しい日々だとは思いますが、宿題初めの10~15分でもいいので時間を作っていけると望ましいです。
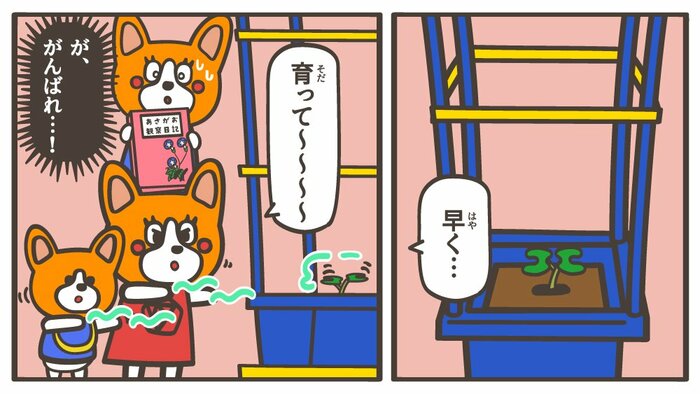
他にも、「計算ドリルが得意じゃない」「読書感想文は気分が乗らない」など、苦手なものはついつい「先に終わらせちゃいなさい」とアドバイスしたくなるだろう。
しかし、宿題へのモチベーションを保つためには、苦手な教科の宿題を進めたら「得意な教科の宿題も進める」「遊びの時間を挟む」「おやつタイムにする」など、“好きなものとコンビにする”のも良いそうだ。
今年こそは「夏休み最終日に大変な思いをしたくない」というパパママは、ぜひ試してみてはどうだろうか?
(解説:佐藤めぐみ/公認心理師)
英・レスター大学大学院修士号取得・オランダ心理学会認定心理士。欧米で学んだ心理学を日本の育児で取り入れやすい形にしたポジ育メソッドを考案。アメブロの「ちょっと子育て心理学」(http://ameblo.jp/la-camomille/)にて発信中。
(漫画:さいとうひさし)