幼い頃からスマホやタブレット端末に触れ、当たり前のようにインターネットを使ってSNSやゲームで人と繋がる、今の子どもたちは、まさに「デジタルネイティブ世代」だ。
折しも今年度から、小学校でのプログラミング教育が必修となった。AIとともに生きる世界では、プログラマーのような専門職に限らずともプログラミングへの理解、デジタルリテラシーが不可欠だということだろう。
そんななか、フジテレビでは人気鉄道アニメ「チャギントン」のAR(拡張現実)を使用したプログラミング入門アプリ「チャギントンプログラミング」をリリース。対象年齢が3歳からと、小学校に入学する何年も前からプログラミングに親しめるアプリだ。そのような頭の柔らかい幼少期からプログラミングに触れることは、どんなメリットがあるのだろうか?

「プログラミングは、これからの子どもたちにとって欠かせない経験です」と語る、脳科学者の茂木健一郎氏に詳しく話を聞いた。
子どもの脳を育むプログラミング
「子どもたちの脳の成長にとても大事なのは、多様な経験です。今の子どもたちは“デジタルネイティブ世代”ということもあって、YouTubeで動画を見たりインターネットでゲームしたりしながら経験を深めていきますが、そういうときにプログラミングに触れていれば、動画やゲームを受け身で楽しむだけではなく『このゲームはどうやったら出来上がるんだろう?』という部分にまで興味を持って、能動的に学びを深めることができるのです」
この「チャギントンプログラミング」も、今後はユーザーが自由にステージを作って配信するなど、より能動的に取り組める機能をアップデートしていく予定だという。
そして、プログラミングに取り組む際には、物事の本質を見極め、単純な動作やルールの組み合わせを整理して問題を解決することが求められる。そうした論理的思考・システム思考も、子どもの脳に良い影響を与えるようだ。
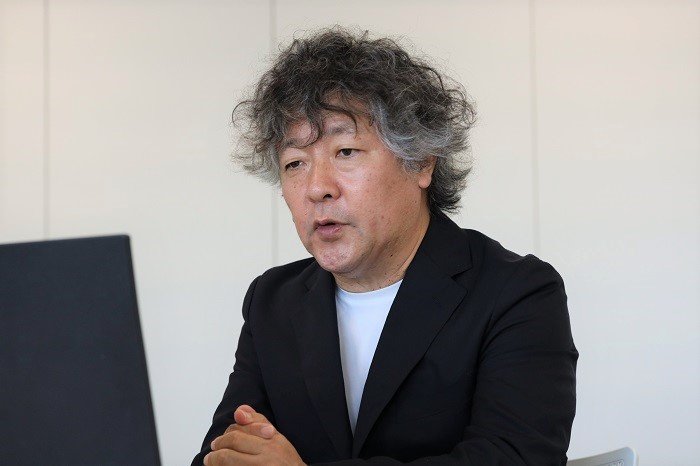
「プログラミングで論理的、またシステム的に物を考えるとき、子どもの大脳皮質の頭頂葉と呼ばれる、空間の情報処理を担当する部位が活性化することがわかっています。さらに、プログラミングがうまくいくと『できた!』と嬉しくなって、脳にドーパミンという物質が放出されます。
すると、脳のシナプス結合と呼ばれる神経細胞間の結合が強くなる『強化学習』という作用が起こり、その嬉しかった行動を何度もやりたくなるのです。結果としてプログラミングの経験を深めていける、というわけですね。そういった感動体験から論理的な思考までを含めた様々な回路が脳の中で働いて、子どもたちの脳を育くむことが期待されます」
また将来的にAIが台頭し、あらゆる仕事がAIに取って代わられる時代が来ると、既存の知識にとらわれず自分の頭で考えて問題を探究できる「地頭力」がカギとなると言われる。茂木氏は、そのような地頭力もプログラミングによって鍛えられると語る。
「そもそも脳科学的にいうと地頭力の大部分は、今、目の前にある物事に集中する能力のことです。つまり集中力に関わる脳の前頭葉の回路が強い人ほど地頭が良い、と言えるのです。実際、天才や偉人と呼ばれる各分野の成功者たちは、脳の中でも前頭葉が発達しているといわれています。
集中力は、使えば使うほど鍛えられます。例えばチャギントンプログラミングでは、ステージが進んでプログラミングの難易度が上がるほど、子どもたちは深く集中しないとなかなかクリアできないでしょう。こうして何度も深く集中する体験が、結果的に地頭を鍛えることにつながるのです」
大事なのは、遊ぶように学ぶこと
小学校でのプログラミング教育必修化は将来に向けた大事な一歩だが、茂木氏が懸念するのは「学校の教科としてプログラミングを学ぶと、どうしても成績評価の対象になり、苦手意識を持つ子が出てくるかもしれない」という点だ。
ゆえにプログラミングを「お勉強」として捉えるずっと前、ちょうど思考能力がついてきた3歳ごろからゲーム感覚でプログラミングに触れると、素直に学びに取り組めるようになるだろうという。

「これはすごく大事なポイントなのですが、子どもの脳にとって『遊び』と『学び』は本来区別がないんです。何かを経験して脳の回路のシナプス結合がつなぎ変わることを『学習』と呼ぶのですが、その作用は学びでも遊びでも同じことが起きている。ある物事を探究した結果、成功するか否か、という要素はどちらも同じですよね。だから、何かを指して、それを学びとするか遊びとするか、というのはあくまで人間側が作った決め事なわけです。
また、成績優秀な子はだいたい、学校の勉強もゲームだっていう感覚を持っています。そこがどうも、勉強が得意になるか、苦手になるかの分かれ道のようですね。だからこそ、3歳くらいからプログラミングに触れることで遊びと学びの境目をなくしてあげると良いのではないでしょうか」
さらに茂木氏は「早い時期に始めれば、その経験が土台となって、学びの定着の仕方や、どこまで学びを高く積み上げられるか、という展開が全く違ってきますね」と語る。

「チャギントンプログラミングならば、身近なキャラクターがすぐそこに立ち現れるといった、ARによる直感的なインターフェイスでプログラミングを楽しめるので、思考能力が付いてきた3歳くらいの子でも親しみやすいでしょう。そのような楽しみ方によって、何より子どもたちがプログラミングを好きになる、ということが大事なのです」
子どもをきっかけに、大人もプログラミングを
とはいえ親として悩ましいのは、そのきっかけ作りだ。こちらから何度も働きかけて取り組ませるのではなく、子ども自らが自然とプログラミングに夢中になってほしい、というのが親心だろう。
事実、脳科学的にも人間の脳は「やらされている」と受け身に感じてしまうと、脳が抑制され、前頭葉を中心とする「やる気の回路」がなかなか動かなくなるのだという。では、どうしたらいいのだろうか?

「やはり、普段から家の中にスマートフォンやタブレット端末を置いておくことです。すると子どもたちは自然と触るようになるので、それらの端末にチャギントンプログラミングのアプリをただダウンロードしておけばいい。最初は他の動画やゲームを楽しんでいたとしても、ある時、あれ、これなんだろう? って気づくでしょう。そこであえて『プログラミング』という言葉を使う必要は全くありません。自由に触らせて、『あ、なんか新しい遊びがあるんだ』って思わせて、子どもが興味を持ったらしめたものです
あとは親自身が子どもの前でチャギントンプログラミングをやってみせるのが1つの方法ですよね。子どもは親がやってることを真似したがるものです。ママがやってることおもしろそう、パパがやってることを自分もやってみたい、って思わせられるといい」
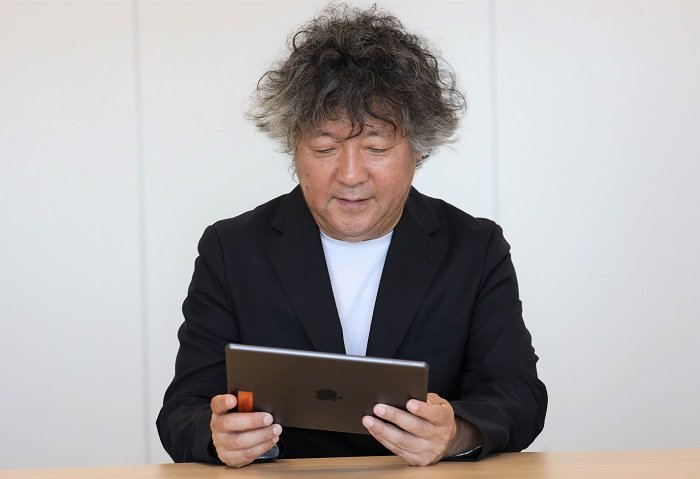
そうやって大人がプログラミングをすることは、子どものきっかけ作りだけではなく、そもそも大人自身の脳に想像以上のメリットがあるようだ。
「何歳になっても、脳の回路はつなぎ変わるのです。だから大人も脳のアンチエイジングのためにもぜひ子どもと一緒にやってほしいですね。プログラミングは論理的思考を積み重ねる作業ですが、私たちの脳はその論理的思考がもっとも苦手なのです。だからプログラミングは、脳の核心部分に至る“最高位の脳トレ”と言っても過言ではありません。高齢者の認知症予防にもおすすめでしょう」
人生100年時代を見据えれば、親世代の大人にだってまだまだAIとともに生きる未来が待っているだろう。となればプログラミングへのリテラシーは子ども同様に必須のスキルであるに違いない。最初は、子どものきっかけ作りのため、という名目でも構わない。チャギントンプログラミングを入り口に大人もプログラミングをはじめてみてはいかがだろうか。
チャギントンプログラミング
https://chuggipro.com/
取材・文=高木さおり





