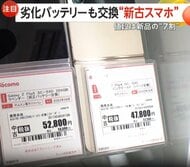連日の猛暑が続く中、人々の消費行動にも影響が出ている。
17日に39.1度を観測し、日本一暑かった愛知県豊田市では、夏に大人気のはずの“かき氷店”が「暑すぎて人が出てこないから全然売れない」との理由で、涼しくなる夕方まで一時休店。
気温と消費の関係を、第一生命経済研究所、星野卓也主任エコノミストに聞いた。
データが裏付ける「35度」
ーー猛暑が続くと、経済面ではどういった影響がある?
一般的には夏は暑ければ暑いほど、消費が増えるという傾向が見られます。
それは、プールや海などのレジャーの消費、飲み物やアイスクリーム、かき氷などの夏物の消費が増えるということが、押し上げ要因になります。
ただ、暑すぎると、逆に消費にマイナスに及ぶ影響もあります。
それは、暑すぎることで「きょうは家にいよう」と、外に出かけるのをやめる人たちが増えるからです。

ーーその境界線は?
私のデータに基づいた分析だと、その境界線はちょうど35度ぐらいです。
35度ぐらいまでは、暑くなればなるほど消費が増えるという関係にあり、35度を超えてくると36度、37度、38度となるにつれて、消費が減っていくという分析結果があります。

外に出ることで、お金が使われるというところが大いにあるので、暑すぎるとスーパーに行かなくなって食材を買わなくなるとか、レジャーも減るので、消費全体にはマイナスになってくると考えています。
まさにコロナで皆さんが出かけなくなって消費がマイナスになったのと同じだと思います。
お惣菜やお弁当は好調
一方で、熱中症対策や火を使う料理を避ける目的で増える消費もあるという。
ーーすべての消費がマイナスになる?
全般的に減るという傾向がありますが、細かく見ていくと、35度を超えても増える消費がないわけではありません。
例えば、熱中症の危険性が高まるという点から、スポーツドリンクやお茶などは35度を超えても増える傾向が見られます。

食材についても、野菜やお米など調理をする必要があるものは、暑すぎると消費が減る傾向にありますが、一方でお惣菜やお弁当はむしろ増えます。
暑いと火を使って料理するのが大変なので、お惣菜やお弁当に流れる傾向があると考えられます。

ーー消費の今後の見通しは厳しい?
今、春闘の場で、賃金の上昇がある程度妥結している状況で、消費の追い風が吹いているような状態なのに、暑い日が多すぎると、それに水を差すことにならないかが懸念される材料です。
過去のデータを見ると、所々で35度を超える暑い日はありますが、連日というのはあまりないので、今年は珍しいと思います。