医療の正しい知識を有する名医たちが、健康に関するお悩みを解説する「名医のいる相談室」。
今回は整形外科の専門医、大阪公立病院 整形外科の岡野匡志(おかの・ただし)医師が「関節炎」について解説。痛風、関節リウマチ、加齢など様々な原因で起きる関節炎の治療法、また四十肩・五十肩についても解説する。

関節炎とは
関節炎というのは、関節に炎症が起こって、痛みや腫れが起こってくる状態を指します。慢性と急性という形に大きく分類されます。
慢性の関節炎は、基本的には1~2カ月、関節の痛みあるいは腫れといった症状が長期間持続する状況です。
急性の関節炎は、数日ないしは1週間程度で症状が改善します。
慢性の関節炎の代表的な疾患としては、関節リウマチなどの自己免疫性疾患が主です。急性の関節炎の主な代表としては、いわゆる痛風などが該当します。
あとは、膠原病に関連した関節炎「シェーグレン症候群」や「全身性エリテマトーデス(SLE)」などの疾患や、高齢の方でよく膝が腫れて水が溜まるといった加齢性の変化になる「変形性関節症」ですね。膝や肩、そういった加齢性の関節炎というのもあります。
関節炎の症状と原因
まず急性の関節炎で、先ほど痛風という疾患を挙げました。痛風はいわゆる尿酸の値が高くなって、その尿酸の結晶が血管の中から関節の中に漏れていって、それが火種となって関節に炎症が起こってくる、そういった疾患です。

ほとんどが男性に起こりやすくて、飲酒や肥満といったような食生活などの関連が一般的に報告されています。
慢性の関節炎の代表としての関節リウマチというのは、いわゆる免疫の異常によって起こるとさ
れています。
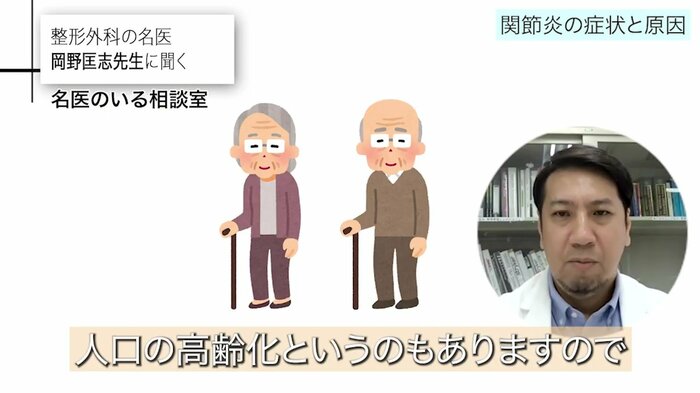
一般的には30代~50代の女性に発症しやすいとされていますが、男性に発症することももちろんありますし、人口の高齢化もありますので、60歳以降での発症も少なからず存在しています。
免疫の異常によって関節の中の「滑膜(かつまく)」が慢性的な炎症を起こして、骨や軟骨を破壊していくという疾患です。
しかし、免疫の異常だけで必ず発症するというものではありません。そこに免疫学的な背景のある方に、いわゆる「環境因子」というような、喫煙あるいは歯周病といったものが合わさることによって発症すると考えられています。
そして変形性関節症は、だんだんクッションの軟骨がすり減ってくる。特に体重のかかりやすい膝などに起こりやすくて、軟骨がすり減ってくるとだんだん骨のトゲができてきたりとか、膝だとすごく水が溜まったりとか、それによって腫れてくるということがあります。
これは70歳以降ぐらいの、特に女性の方が比較的男性よりも起こりやすいということになります。
関節炎の治療法
治療法に関しては、痛風であれば尿酸が高値になっているということが原因になるので、尿酸を下げるような薬ももちろんあります。

しかしそもそも、生活習慣に問題がある方が多いかと思います。飲酒あるいは食生活など、まず生活習慣を見直すことで痛風の発作を抑制したり、尿酸値を低下させることが十分見込める疾患です。
関節リウマチに関しては、免疫の異常によって滑膜炎が生じるという病態がわかってきているので、その免疫の異常を改善させるというか、抑える治療として、免疫抑制剤の使用が一般的に推奨されています。

関節リウマチに関しては、先ほど発症のところで歯周病や喫煙を原因として挙げましたが、やはり喫煙や歯周病は、治療のお薬の抵抗性にも関連していると言われています。
ですので、発症後でも禁煙していただいたり、歯周病を治療していただくことで、リウマチの病性が比較的落ち着いたり、薬が効きやすくなるということもあります。そういった生活面も含めて、一緒に治療していくというのが重要かと思います。

変形性関節症に関しては、膝であれば一般的に、ヒアルロン酸の関節内注射がよく行われます。それ以外には、炎症を抑える消炎鎮痛剤の薬の内服などが行われますが、これは根本的な治療というわけではありません。
一度傷んでしまった・変成を起こした軟骨とか、すり減った軟骨が完全に元に戻るという治療は現時点ではまだありません。炎症や痛みを抑えて、進行を少しでも遅らせるという治療になります。根本的な治療・改善というのは、現時点ではなかなか難しいということになります。
季節による痛みの変化
寒くなると、血液の流れが乏しくなり血流が低下することによって、筋肉が動きにくくなったりといったことが実際に起こる可能性があります。寒くなって血流が低下することによって、関数の痛みが増悪するということは、疾患によってはあり得ると思います。
よく温泉に行くと、効能・効果に「リウマチ」と書いてあるのを見たことがある方も多いのではないかと思います。血流というのが、関節の痛みなどに関与していることは間違いありません。
四十肩や五十肩について
一般的に言う「四十肩」や「五十肩」は、「肩関節周囲炎」と言われたり、肩を上げたり下げたりする腱(けん)が引っかかる「インピンジメント症候群」と言われたりすることもあります。
一般的な四十肩や五十肩は、肩関節の周りの骨を動かす腱、筋があるんですけども、そういったところに炎症が起こっている状態で、実際は肩の関節の中ではないことが多いと思います。
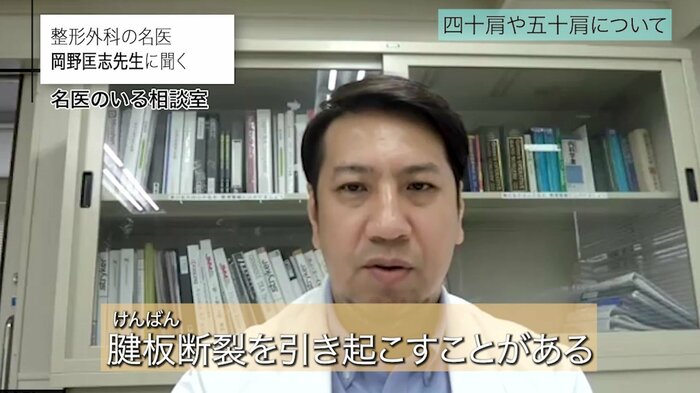
四十肩・五十肩で肩の周りに炎症が起こって、腱が傷んできて「腱板(けんばん)断裂」を引き起こすことがあります。肩を上げる腱、筋が切れてしまうと肩が上がりにくくなってくるのですが、それを他の筋肉、三角筋などが代償して上げるようになってきます。
そういうふうに腱の変性が進んで、腱板断裂が起こって…という風になってくると、関節自体の適合性が悪くなって、それによって軟骨が傷んだり、骨のトゲができたり、と関節内の変形性関節症という病態につながってくる恐れがあります。
やはり最初の方の、痛みが出た軽い段階でしっかりと治療していただいて、そういった鍵板断裂、そしてそれに引き続く変形性関節症を起こさないように、早めに治療・対応していただくのが望ましいと思います。






