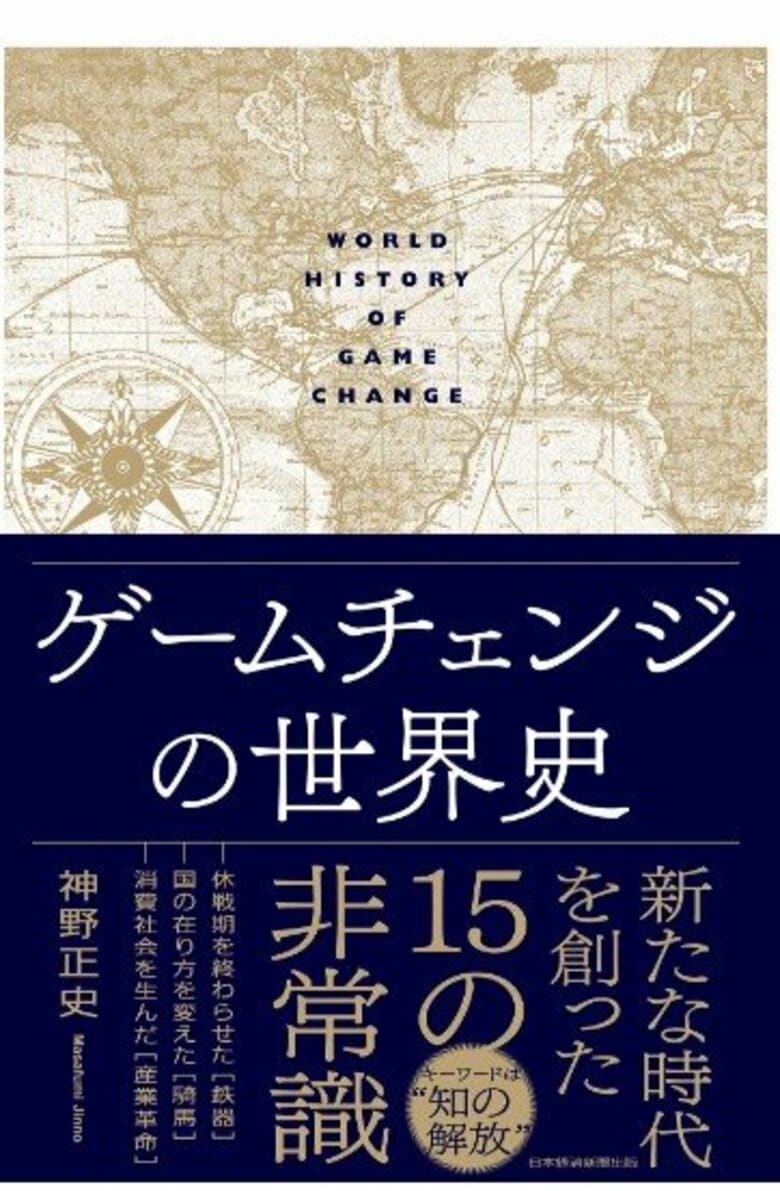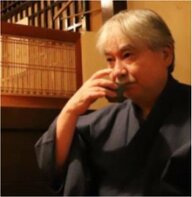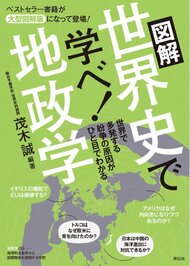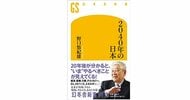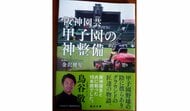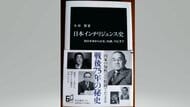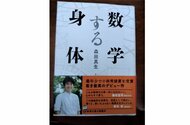以前『図解 世界史で学べ!地政学』(茂木誠 編著・祥伝社)という本をこの書評で扱ったが、その編著者、茂木誠氏は駿台予備学校の世界史の講師だった。とてもわかり易い叙述であの難解な地政学を説明する手さばきに、感心したものだった。
今回紹介する『ゲームチェンジの世界史』の著者・神野正史氏も、偶然にも予備校講師である。やはり予備校講師という職業柄、教える術に長けているのだろう。重要な語彙や内容が太字ゴシックになっているところは参考書を思わせるところがあるが、理解を助けるためなら何でもOKである。実際、この本も内容がすっと頭に入った。
「ゲームチェンジ」という切り口で歴史を眺める
さて、この「ゲームチェンジ」という言葉、元はビジネス用語だったものだが、著者は「ジェンガ」というゲームに例えて、実にうまく表現している。
「初めに木片(パーツ)を塔のように積み上げておき、参加者が順番に一本づつ木片(パーツ)を抜き取っていくゲームですが、ゲームが進むごとに塔は不安定になっていき、ある臨界点に達すると塔全体が一気に崩れ落ちます。じつは、これと同じことが歴史・社会・国家でも起こっています」
非常にイメージしやすい描写だ。
この本の著者は、ゲームの始まりの状態を「泰平の世」と呼ぶ。政治・経済・文化などの諸要素が密接に絡み合って安定した社会を形成している状態だ。ジェンガでいえばゲームの始まる前の「初期状態」に当たる。しかし…
「世はつねに移ろいゆくため、徐々に “社会機構(システム)と現実が乖離“していき、それにより社会は次第に不安定になっていきます。この状態をジェンガで喩えれば、“ゲーム進行中”に当たります」
ゲーム進行中、ジェンガの塔は盤石に見える。しかし内部では力学的な歪みが累積しており(社会の矛盾)、それが臨界点に達したとき、つまり最後の一本が引き抜かれたとき、ジェンガの塔は倒壊する。
一つの王朝・政権・帝国の中で矛盾が蓄積していき、ある事柄が契機となってその国家が崩れ去る。それと同じである。
著者は「ゲームチェンジ原則」として10の原則を上げているが、いずれも16のテーマでその実例を挙げているので、なるほどと納得しやすくなっている。
たとえば、
「ゲームチェンジに必要なものは、『発明』ではなく『実用化』『普及』」
上の原則では「鉄」の項目で「銃」に例をとって説明しているが、むしろ「鉄」そのものにも適応できることを著者は前段で説明している。
古代オリエント世界で「ヒッタイト王国」が隆盛をきわめたが、その原動力は「鉄」の実用化にあった。「青銅器時代」であった当時、「鉄」の精錬法を見つけ出したヒッタイトが地域の主導権を握ったのである。鉄は青銅よりもはるかに硬度が高く、鉄の武器は柔らかい青銅の武器を相手にしないほど勝っていた。
地理的環境には恵まれていないが鉄鉱石だけは豊富にあるヒッタイトは、起死回生を祈念して、鉄の精錬に全力を注いだ。「鉄」は新石器時代から知られていたが、低温で精錬した鉄は柔らかすぎて武器などの実用に耐えなかった。ヒッタイトは鋳造の際に炭を混ぜることによって、ついに実用に耐える鉄を「発明」したのだった。ここでは「発明」「実用化」が語られ、ヒッタイト王国を地域の強国に押し上げたという「弱いゲームチェンジ」の達成が見られるが、面白いのはその後である。
ヒッタイト王国は、当然のごとく鉄の精錬法を厳重な「国家機密」としたが、「アーリア民族の移動」という激動の中で滅亡してしまう。すると、製鉄技術がオリエント世界全体に広がり「青銅器時代」から「鉄器時代」にチェンジすることになる。
もちろん鉄は軍事的にも重要な素材となったが、農業でも柔らかく耐久性に難のあった青銅製から鉄製の農具に切り替わった。鉄の農具で耕すことによって土に空気を含ますことができ、根が張りやすくなるうえに、空気中の栄養素である窒素が土に溶け込むことになる。鉄製農具の導入で農業生産力が数倍になったという試算もあるらしい。
農産物の増大は人口の増大を引き起こし、さらにあらゆる側面で歴史を変えていった。ヒッタイト王国の地域大国化よりも、はるかに「強いゲームチェンジ」をここに見いだすことができる。

「キリスト教」「仏教」におけるゲームチェンジ
また、世界宗教である「キリスト教」「仏教」の項目もなかなか面白い。
たとえばキリスト教は「博愛」を語るが、それは同じユダヤ人同士のみのことである。イエスがいたころのキリスト教は「ユダヤ教イエス派」という位置づけだった。つまり異端視されてはいたが、やはりユダヤ教の一派に過ぎなかった。だからユダヤ教のもつ選民思想も引き継いでいた。
しかし、そこで疑問が生じる。なぜ、そんな選民思想を持ったキリストの宗教が世界宗教になりえたのだろうか。
そこで、一人の人物が登場する。使徒パウロである。
パウロはイエスの死後に入信したので、直弟子ではなかった。さらにイエスを迫害したパリサイ派の人間だった。当然のごとく教団の中での立場が悪い。そこでパウロは布教活動、つまりより多くの信者を獲得することで教団内での自らの地位を高めようとした。ここでパウロは禁じ手を使う。「純血ユダヤ人かつ割礼した者」だけがユダヤ教の信者になれるという戒律を破り、各地で伝道しては異邦人たちを次々と入信させたのだった。
パウロのこの行為によって、ユダヤ教イエス派は大混乱に陥ったが、一方でユダヤ民族に限られた宗教から世界宗教への第一歩を踏み出すことができたのである。
さきにふれた「ゲームチェンジに必要なものは、『発明』ではなく『実用化』『普及』」をこう言い換えることができる。
「ゲームチェンジに必要なものは、『開祖の登場』ではなく『誰でも入信できる分派の登場→普及』」である。
面白いことに、それと同じようなことが、やはり世界宗教の「仏教」にも起こっている。
仏教には「大乗仏教」と「小乗仏教」があるが、「小乗仏教」という言い方は、大乗に比して蔑称のニュアンスがあるので、いまは「上座部仏教」が一般的になりつつある。
その「上座部仏教」は、出家して修行を積むことによってのみ、悟りの境地に達することができるとする。個人の「魂の救済」という仏教本来の主題に忠実な宗派である。ただ、戒律・修行とも非常に厳しく、誰もが悟りの境地に達するわけではない上に、修行による個人の「悟り」が主要テーマとなるから、当然のことながら、僧以外の多くの人々の救済には無頓着だ。
そこで大乗仏教の登場である。
大乗仏教はサンスクリット語で「マハーヤーナ」というが、これは「大きな船」という意味である。そこには「大乗」、つまり多くの人々を救うという願いが込められている。自らの「解脱」以上に利他を重く見て、利他行為によって出家、在家を問わず、すべての人々を救うという考えがそこにある。喜捨、布施などの形で仏教のサポーターであれば救われるし、仏教的慈愛の行為でも救われるのである。
仏教は大乗仏教の登場により「実用化・普及」を成し遂げ、歴史にゲームチェンジを起こした。逆に言えば、釈迦の登場だけでは、歴史は大きく変わることがなかった可能性がある。
このように、ゲームチェンジという切り口で歴史を眺めると、歴史の底を流れる地下水脈にふれることができる。しかし、多様で複雑な歴史は、ひとつの見方だけで理解できるものではないことだけは忘れてはならないだろう。
【執筆:赤井三尋(作家)】
『ゲームチェンジの世界史』(神野正史 著・日経BP 日本経済新聞出版)