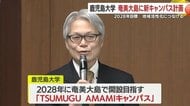さんぽセルを開発した子どもたちに末松文科相の発言の感想を聞いた。
「大臣にほめてもらって嬉しい」
「うおう」
6月14日、末松文科相の閣議後会見でさんぽセルについて質問が出ると、開発した小学生の兄弟から思わず声が上がった。彼らは自宅で14日夜、YouTubeの会見映像を見ていた。
映像を真剣に見続ける2人。
終わった後「どうだった?」と開発を支援している大学生が聞くと、「驚いたわ」と即答。
「気にしてくれたことは嬉しい。もっと改良が必要、安全性に配慮しながらと言っていたね」
大学生が「ほめていたよね」と聞くと、「うん、ほめていた。ほめていたね。大臣にほめてもらって嬉しい」とちょっと嬉しそう。
さらに大学生が「びっくりだね」と聞くと、「うん」と頷いた。
しかしもう1人は「なんともいえない」を連発。まだ実感がわかない様子だった。
「願った社会が実現すると期待しています」
開発を支援している大学生はこう感想を語った。
「まず、本当に文部科学大臣に認知してもらえていてとても驚きました。さんぽセルがほめてもらえたり、学校の荷物の状況について見直すと言っていて、これは、小学生とみんなで願った社会が本当に実現するんじゃないかなって期待しています」
「素晴らしい取り組みだと文科省は皆思っている」
会見で筆者は末松文科相にこう聞いた。
「さんぽセルを開発した子どもたちが、クラファンで集めたお金でつくるさんぽセルの寄付先を募っています。その対象に学校長だけでなく総理や大臣も入っていますが、大臣は応募する考えはありますか?その理由も教えてください」
すると末松文科相は「写真を拝見しました。ひくこともできるし、背負うこともできるような非常に便利なもの」と感想を語ったうえで、子どもたちをこう絶賛した。
「驚きましたのは、小学生自ら重いランドセルをなんとかしたいと発案した製品であるということ。子どもたち自身が課題を見つけ試行錯誤し、大人の協力をえてこうした一つの解決策を見いだしたのは素晴らしい取り組み。文科省も皆そう思っています」

「様子を見守りながら方針を述べたい」
子どもたちからの寄付に応募するかについてはこう答えた。
「寄付先として私も募集の対象となっているようだが、販売元は注文が殺到しているときいているので、まずは希望する方に製品が届くのが一番大事かなと思います。そのあと、どうするかは様子を見守りながら、方針というか私の考えを述べたいと思います」
そして末松文科相は筆者に「総理はなにかおっしゃっていましたか?」と逆質問。首相も子どもたちの応募の対象となっているのだ。筆者が「まだ聞いていませんけど、閣議で何か言っていましたか?」と聞くと、「いやあきょうは出なかったね。総理にきいてみたいと思いますけれど」と笑顔で応えた。
「教育委員会や学校に対応を求めていく」
末松文科相はこう続けた。
「文科省の担当者と話したが、子どもたちの身体の健康に留意し、ランドセルの重さや量への配慮は大変重要でありますし、子どもたちの問題提起もそこだと思うんです。タブレットもコロナの感染時期におきまして大変重くなっていましたから。文科省としてはかねてより、教材のうち何を持ち帰らせ、何を学校に置くのか、保護者ともよく連携し、児童生徒の発達段階や学習上の重要性、通学の負担や学校地域の実態を考慮し適切に判断したいと、事務連絡の発出について現場にお願いしているところです。今後も引き続き教育委員会や学校に対応を求めていきたいと思います」
そして最後にこう語った。
「子どもたちの貴重な問題提起ですので、子どもたちを第一に考えたランドセルなどの携行品の取り扱いについて、各学校で考えて頂くことを期待しています。一番の問題は、安全性。引きずられてしまうとか、事故など無いように研究する必要があると思っています」
子どもたちの願いへ満額に近い回答だ。

「“ランドセル=悪”の風潮にならないように」
さんぽセルの募集状況はどうか。応募を考える小学校の校長はその理由をこう語る。
「実際に需要があるのか?使い心地はどうか?知りたいと思いました」
一方でこの校長は「“ランドセル=悪”みたいな風潮にだけはなってほしくない」と続ける。
「重たいことが改善されるべき事項であり、ランドセルには罪はありません。機能的だし長持ちします。ランドセル作りに携わっている人たちも大勢いるので、“ランドセル=悪”みたいな風潮にだけはなってほしくないです」
大人のマインドセットを変えるのが急務
埼玉県戸田市教育委員会の戸ケ﨑勤教育長は「拍手を送りたい」としたうえで、批判した大人こそ変わるべきだと語る。
「子供が自ら目の前の課題解決に主体的に関わって対策を講じたこと、また様々な批判に果敢かつ冷静な対処をしたことに拍手を送りたいと思います。子どもたちの素晴らしい発想を批判する大人たち(教師も含めて)のマインドセットを変えていくことが急務だと思います」

そして戸ケ﨑氏は「本市でも力を入れているPBL型(問題解決型)の学びに通底するもの」だと続ける。
「新学習指導要領や令和の日本型学校教育でも強調されている“一人ひとりの子供が、自分のよさや可能性を認識することができるようにすること”の実現には、一人ひとりの子どもを主語にする学校づくりに向け、自分たちでいろいろ考え、様々な人たちと対話や相談しながら実践し、うまくいかなければ振り返り、改善してよりよいものにしていく、そういう取組を取り入れていくことが何より大切だと思います」
戸田市では2019年に行われたプレゼンテーション大会で、ランドセル問題が提案されたという。
子どもたちの可能性は無限だ。今回のさんぽセルがそれを証明している。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】