アメリカは中国を「為替操作国」に指定
今月5日、アメリカは中国を「為替操作国」に指定した。「為替操作国」は、アメリカが、貿易で競争上の優位を獲得したり、経常収支を調整したりする目的で、為替を意図的に操作している、と判断した国を指定するものだ。指定国に対しては、協議を通じて是正を求め、改善が見られない場合は、輸入品への関税など制裁措置に踏み切るケースもある。
5月の報告書では指定を見送っていた

「為替操作国」かを判断する条件は3つある。
ひとつは、アメリカに対する貿易黒字が年200億ドル以上あること。ふたつめが、為替介入による外貨購入が1年で6か月以上行われ、かつGDP=国内総生産の2%以上となっていること、そして、3つめが、経常黒字がGDP比で2%以上あることだ。原則として、ふたつに該当すれば「監視リスト」に入り、「為替操作国」指定では、3つの条件すべてにあてはまるかどうかが考慮される。
アメリカ財務省は、半年ごとの報告書で貿易相手の通貨政策などを分析している。5月下旬に、直近の報告書が公表された際には、中国はひとつめの条件だけが該当し、操作国の指定は見送られたが、為替介入の実績の公表を見合わせているなどの理由で、半年間かけて中国の政策の透明性を見極める姿勢が打ち出されていた。
元の対ドル相場が11年ぶりの安値に
今回アメリカは、3条件とは別の枠組で操作国の指定に踏み切ったが、背景にあるのは、まず中国との貿易協議の手詰まり状態だ。
トランプ大統領は、1日、第4弾の制裁関税の発動に踏み切ると表明したが、あわせて操作国に指定することにより、膠着状態に陥った交渉で、中国への圧力を強めるねらいがみてとれる。
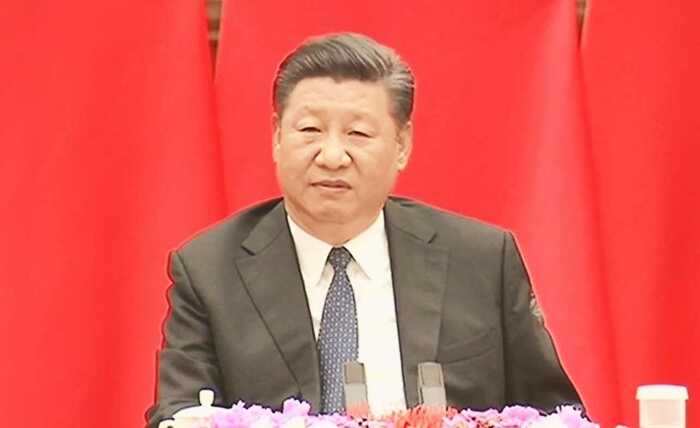
さらに大きな理由が、元安ドル高が加速したことだ。人民元相場は5日、1ドル=7元台に突入し、約11年ぶりの安値をつけた。
人民元相場では、中国の中央銀行にあたる「中国人民銀行」が毎日、基準値を設定していて、中国本土での取引は、この値の上下2%の範囲内で行われる。人民銀は、元の前日終値や、ドル、ユーロ、円など複数の通貨でつくる「通貨バスケット」に対する元の変動幅などを踏まえて、その日の基準値を決め、朝方発表していて、人民銀の意向が元の相場形成に大きく反映される。
最近は、元相場が1ドル=7元に近づいても、7元台には突入せずに、押し戻されるという展開がみられ、中国からの資本流出を警戒する人民銀が、元安の防衛ラインを「1ドル=7元」に置いているとの見方が浸透していた。
強まる中国当局「1ドル=7元台」容認観測
元相場がこのラインを超えた5日は、朝に公表された基準値が、去年12月以来の低水準となる1ドル=6.9225元に設定された。取引では、中国語で「破七」と呼ばれていた「1ドル=7元を突破しての元安」がついに起こり、中国当局が、アメリカとの貿易摩擦の高まりを背景に「1ドル=7元台」の容認に転じたのだという観測が広がった。中国を為替操作国に指定したこの日、トランプ大統領は、「中国が歴史的低水準に通貨の価値を引き下げたのは、為替操作だ」とツイッターに投稿している。

その後も連日、1ドル=7元台での取引が続き、8日には、基準値そのものが約11年ぶりに1ドル=7.0039元に設定された。人民銀が、基準値の水準を市場実勢に近づけて、緩やかな元安は許しているとの見方はさらに強まっている。「意図的な切り下げだ」というアメリカ側の反発に拍車がかかるのは必至だ。
米中衝突は「貿易」から「通貨」へ
ここ数日で、米中衝突の舞台は「貿易」から「通貨」へと広がった。
元安は、中国の輸出企業を下支えする効果があるが、急速に元売りが進めば、資本が中国から海外に流出する事態を招き、中国経済のさらなる減速につながる。
対中制裁関税第4弾を9月に発動する一方で、アメリカは為替操作国指定での具体的な措置に踏み出すのか。中国が「元安カード」をちらつかせる姿勢を見せるなか、始まった米中通貨戦争への金融市場の警戒感は一段と強まっている。






