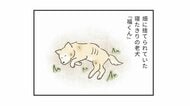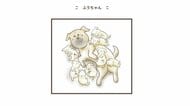ここまで、社会的手抜きが生じる理由として、個人の成果が自分自身やまわりから見えにくいことで、モチベーションが下がることを説明してきました。
逆に言うと、一人ひとりの成果が「見える化」されていれば、社会的手抜きは抑制されるのです。

たとえば、「大声を出す」という集団実験では、参加者一人ひとりの声の大きさが不明な状況では、集団サイズが大きくなるほど1人あたりの声の大きさが小さくなっていました(※Latané, Williams, & Harkins(1979))。
しかし、その後の実験で調べたところ、個々の声の大きさがお互いに分かるようにした実験では、社会的手抜きは発生しませんでした。つまり、集団サイズが大きくなっても、1人あたりのパフォーマンスが低下しませんでした(※Williams, Harkins, & Latané(1981))。
互いに貢献度が見えるとサボらなくなる
言い換えると、お互いに個人の貢献度が見えるならば、集団状況でもサボらなくなるのです。
この結果は、個々人の成果を「見える化」し、フィードバックすることの重要性を示しています。自分の進捗を正確に把握し、それが他のメンバーにも認識されることで、個人のモチベーションは高まり、結果として集団全体のパフォーマンスが向上します。
これは単に「他人にバレないようにしっかりやろう」と思うためだけではありません。
自分自身の進捗を、自分でしっかり把握することも同じく重要なのです。自分の貢献度が自分でも分からないなら、モチベーションを持続させるのは難しいでしょう。
また、そのためには集団のサイズを大きくしすぎないのも重要です。
集団の人数が多すぎると、社会的手抜きの程度が高まります。
そのため、お互いの顔が見えやすく、互いの貢献も認識しやすい、適切な大きさの集団サイズに留める方がよいでしょう。
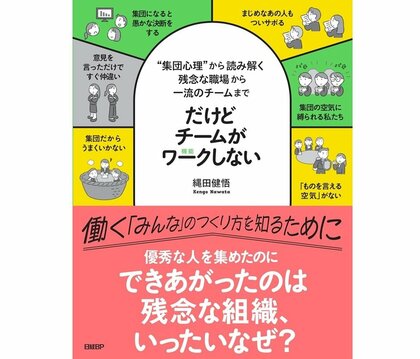
縄田健悟
福岡大学人文学部准教授。専門は、社会心理学、産業・組織心理学、集団力学。集団における心理と行動をテーマに研究を進め、特に組織のチームワークを向上させる要因の解明に取り組んでいる。一般社団法人チーム力開発研究所理事も務める。著書に『暴力と紛争の“集団心理”:いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ』(ちとせプレス)などがある。