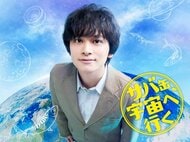日本人の国民食とも言われ、長年、外食産業の中心にいるラーメン業界。原材料高騰と人手不足で全国的に倒産が急増する中、ここ数年で店舗を増やしている店があります。本店のオープンから7年。直近の2年で2店舗を出店し、5月にオープンした店は人口減少、人手不足が進む中での拡大戦略を可能にするモデルケースととらえています。その経営戦略を取材しました。
福井市新田塚に店を構えるラーメン店「麺匠 麦之助」は、濃厚鶏白湯ラーメンが人気の店です。
「客に喜んでもらうためだけにやっている」
そう話すのは、店主の小村明彦さん(47)です。兵庫県出身で、これまでラーメン業界だけではなく、様々な業種で働いてきました。
22歳で布団のリフォーム会社の営業として福井を訪れて以降、仏壇の出張クリーニング店やバー、飲食店などを経営したものの、7年前に全ての店をたたみました。
「良くなるために新しいことを続けて店舗展開したが、すればするほど悪くなる。一つの店を繁盛させるだけで大変なのに、色んな業態で続けるのは難しいと感じた」
その後、ラーメン店・麦之助の経営に集中した小村さん。躍進のきっかけとなったのが「セントラルキッチン」でした。
セントラルキッチンとは、スープや具材を前もって大量に作り、各店舗に配送する仕組みで、多くのラーメンチェーン店で採用されています。
小村さんは、これまでの失敗を活かし、様々な味を多くの店で提供するのではなく、徹底的に追求した一つの味を多くの店で提供しようと、店裏のスペースにセントラルキッチンを設けました。
セントラルキッチンの魅力について小村さんはこう説明します。「役割分担ができる。スープづくり専門でやることで技術が上がるし、味のブレもなくなるし、店舗ごとの仕込みがない分、接客サービスに力を入れられる」
麺やチャーシューもここで仕上げます。
セントラルキッチンの導入により、2024年の北陸新幹線開業に合わせてオープンした商業施設・ミニエでは、わずか8坪のスペースに2号店を出すことができました。
「あの店でスープを炊くのは、無理があるので、販売することだけに集中できるスペースだけで出店できた」
セントラルキッチンが順調に稼働する中、小村さんは出店を加速させています。
3店舗目は、福井市の旧国道8号線、通称フェニックス通り沿いの全国チェーンの牛丼店の跡地にオープンさせました。
2025年5月に福井市花堂にオープンした店では、これまで以上に生産性を高めるため、注文はタッチパネルに変更。サイドメニューのチャーハン作りには調理用ロボットを導入するなどDX化を進めています。
また、従業員にはインドネシアからの特定技能留学生を採用しました。働き始めて2カ月程度だといいますが、麺の湯切りも機械が行うため「カンタン!」と笑顔を見せます。
小村さんは、職人のような技術がなくても、高品質な味をいつでもどこでも提供できることが、ラーメン店の多店舗化で重要だと考えています。
「この花堂店をモデルにして、ロードサイドで駐車場もある店を確実に展開していきたい」
セントラルキッチンに、DX、そして外国人の採用。人口減少が進む福井で、ラーメン店の多店舗化を進める麦之助の挑戦が続きます。