鹿児島・曽於市の全校児童18人の小学校に、アフリカの伝統的打楽器、ジャンベの音が響いた。学校には当初、本物のジャンベがなく、子供たちは机をたたいて練習した。でも「本物のジャンベで地域の人を元気にしたい」との熱意が大人を動かし、国内外からの支援で本物のジャンベがそろい、感動の演奏会となった。
机をたたいて練習する子どもたち
色とりどりの民族衣装を着て、一生懸命にジャンベを演奏する子どもたち。鹿児島テレビに演奏会の動画を送ってくれたのは、全校児童18人の曽於市立中谷小学校。大隅半島北部の山あいに、その小学校はあった。

演奏会のきっかけは、2024年5月、音楽の時間に体験したジャンベの演奏だった。音楽の先生は当時を振り返り、「三島で(ジャンベを)されている方にお願いして『全校児童何人です』、『できれば全員に体験させたいです』と」お願いしたという。

「三島」とは鹿児島県本土の南約40kmにある人口わずか350人の「三島村」のこと。1990年代、世界的ジャンベ奏者が訪れたのを契機に、ジャンベの演奏が盛んに行われている。
「体までドーンってくる感じがすごいと思いました」「興味が湧きましたね、ジャンベに」と興奮気味に語る児童たち。
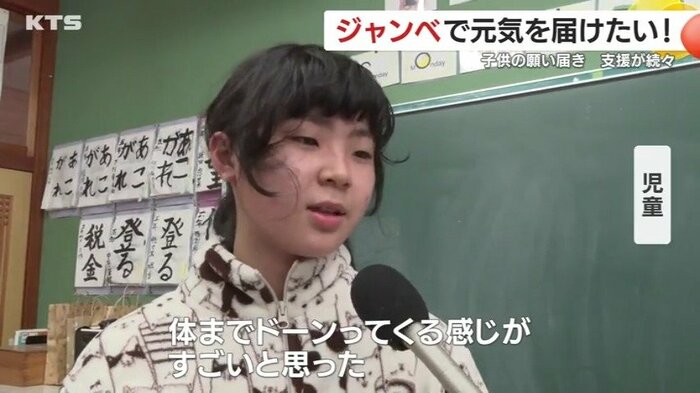
その迫力ある音色に魅了された児童たちは、もっとジャンベを演奏したいという思いを抱いた。しかしジャンベを買いそろえるには予算が足りず、子供たちは “机”をたたいて練習を始めた。
当時の練習を再現してもらった。「普通に机をたたいたら手が痛いから、タオルを敷いてやっています」と児童の一人。タオルを敷かなければ「手が真っ赤になってました」という。やがて子供たちに2つの思いが芽生える。ひとつは、「本物のジャンベで演奏すること」。そしてもうひとつは「ジャンベの演奏で地域の人に元気を届けること」だ。諦めなかった子どもたちの姿勢が、周囲の大人たちの心を動かすことになる。

子どもたちの願いを叶えた支援の輪
子どもたちは、「せっかくならダンスもできるようになりたい」と、SNSの動画をみながらアフリカンダンスの練習も始めた。2024年7月、そんな子どもたちの思いに応えるかのような出来事が起きた。なんと、12台のジャンベが学校に届いたのだ。

支援に動いてくれたのは、東京にある「国際アフリカンダンス&ドラム協会」。溝口里美代表理事は「予算的に購入するのは難しそうなので、皆さんに呼びかけて、おうちに眠っているジャンベを譲ってもらうという企画をしてみてはどうかと私から提案しました」と教えてくれた。溝口さんがSNSで呼びかけたところ、わずか10日で12台のジャンベが集まったという。
しかも届けられたジャンベは、溝口さんによると「全部アフリカ産の、プロが使うようなジャンベだった」という。中には皮が破れて使えないものもあったが、溝口さんを通じて神戸の職人が無償で修理してくれた。修理を担当した、民族楽器を扱うメットリー(神戸市)の黒郷多津子さんは「ヤギの皮を張り、リングもやり直して、『最高』っていう太鼓を贈りたかった」と語る。

また、ジャンベと一緒にアフリカの布も多く寄せられ、先生の知り合いを通じてインドネシア在住の女性が子供たちの衣装に仕立ててくれたという。こうして実現したのが、鹿児島テレビに寄せられた動画(演奏会)だったのだ。
地域に響くジャンベのリズム
2025年3月7日、授業参観の日にもう一度、演奏会が企画された。山あいの小さな小学校に響く太鼓のリズムには、子どもたちの情熱と多くの人々の温もりが込められていた。演奏を指導したのは三島村出身の高校生で、休みを使って小学校に通い、ジャンベや踊りを教えてくれたという。

地域の人々も演奏会に足を運び、「豊作祭りで1回見ててぜひ、きょうも見たいと思ってきました。すごい感動です」と喜びの声を上げた。子どもたちは「支援してくださった方々にとても感謝しています」と感謝の言葉を述べた。
子供たちが演奏する動画を観た神戸の黒郷さんは「みんな楽しそうに演奏してたよね」と、傍らにいる同僚・アントニさんと一緒に目を細めていた。
子供たちの夢をかなえるために、地域や国境を越えて多くの人々が協力し合うことで実現した演奏会は、大きな響きと感動をもたらした。これからもジャンベの響きが人々の心をつなぎ、地域に活力をもたらしていくことだろう。
(鹿児島テレビ)






