能登各地を継続取材し、人々の暮らしや心の動きを追うシリーズ企画「ストーリーズ」地震で甚大な被害を受けた志賀町の町立富来病院は、復旧工事が本格的に始まった一方、病棟では地震を経てある変化が生まれていた。
地震で病院機能は一時停止
2024年1月2日の志賀町立富来病院。病棟の天井は崩れ落ち、検査室の機械も散乱していた。笠原雅徳事務長は「ダメですダメです、機械が全部いかれとるんで。こちらは全然ダメです」と話した。能登半島地震で震度7を観測した志賀町。町の基幹病院は病院としての機能を失っていた。

「簡単な治療だけはやっていただいている」しかし重傷の患者への対応については「できません。ストップさせていただいている」と笠原さんが話す通り、94の病床はすべて使えなくなり、当時72人いた患者は別の病院に移動せざるをえなくなった。1月28日、馳知事が視察に訪れた際、笠原さんは「こちらは被害が甚大で入院のフォローができない」と、事務方の責任者として被害の大きさを訴え続けた。

2024年5月には病棟の半分が仮復旧し入院もできるようになったが、元の状態に戻すには本格的な復旧工事が必要だった。
待ち望んだ復旧工事
笠原さんが目指してきたのは一日でも早く、以前の受け入れ体制を取り戻すこと。「病院の経営自体も地域医療を担う病院としても、患者のニーズに応えていかなきゃいけない。病床の復旧は最重要課題で早々に復旧したい」しかし、依頼した設計事務所が他の復旧工事も抱えていたため、設計書ができあがったのは半年後。工事業者も不足していて、復旧工事は一向に進まなかった。
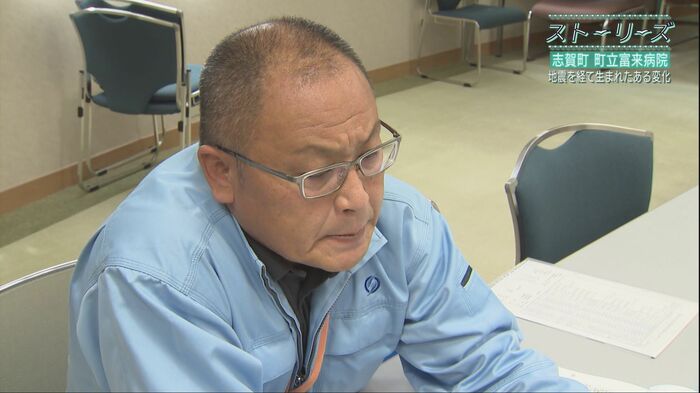
2024年11月下旬、笠原さんから連絡を受けて病院へ行くと、ようやく町の入札で工事業者が決まったと報告を受けた。患者を受け入れながらの工事は様々な制約があるため、早速業者と打合せを行う。

笠原さんが「平日日中ダメなのは1階外来すべてやね」と話すと、業者は「1階はすべて夜間、もしくは土日で」と答えた。患者がいる時間は工事を控えなければならないのだ。さらに地震の影響もあり、業者によると「能登地区にいる配管工が集められるかわからない」という。業者が決まっても、様々な課題が残っていた。
看護のあり方を見つめ直す
一方病棟では、地震後ある変化が生まれていた。看護師と患者の会話。好きな食べ物から夫婦の関係までたわいのない話を、長いときには30分以上話し込む場面もあった。入院患者が以前の半分に減った一方、スタッフの数は地震前と変わらないため、患者1人1人と向き合う時間が長くなっていたのだ。

看護師の竹林江里子さんは「今の患者さんの人数に合った感じで割とゆったり患者さんに接する時間、お話する時間が増えたし細かく看護できているんですけど」ゆとりを持って患者に接することで看護のあり方を見つめ直すきっかけにもなったという。「もとに戻るだけではあるんですけど、やっぱり前の忙しさが戻るから、ちょっとドキドキしています。今できていることを疎かになってもだめやし、頑張って時間配分をしてやらんとな」富来病院では地震による離職者はゼロ。全員が、この町の医療をこれからも支えていくつもりだ。

2024年12月、工事が始まった。笠原さんは「1年でようやく工事にとりかかった、一歩ずつ前進あるのみ。患者が増えても初心を忘れず、丁寧な看護をしてもらいたい。富来病院としてやるべき地域医療を目指したい」やるべき地域医療とは何か。地震で得た「気づき」をどう活かしていくか。病棟の工事が終わるのは2カ月後だ。

病棟の工事は2025年3月末の復旧を目指している。病院自体の本格的な復旧は2026年3月を目指している。富来病院で働く皆さんはこの1年、なんとか患者を受け入れようと奮闘してきて、やっと工事がはじまったことに安堵している状況だ。一方、患者が少ない期間が半年以上あったため、これまでより患者と接する時間が長くなって看護のやりがいや在り方を見つめ直すきっかけにもなっている。事務長の笠原さんは「患者が元の数に戻ってもチーム医療で丁寧な医療、看護を引き続き行っていくためにどうしたらよいかを、病院全体で考えていく必要がある」と話した。
(石川テレビ)





