働く障害のある人の数が増えている。
仕事も、かつて主流だった製造業から接客業など人と関わるものへと多様に。
本当にやりたい仕事を見つけ、誇りをもって生きてほしい。
夢を応援する札幌市の特別支援学校の取り組みに迫る。
あこがれの航空会社のお仕事
2023年、子どもの頃からの夢だったJALに就職した堀田愛佑梨さん(19)。

堀田さんには軽度の知的障害がある。
「帽子を忘れたみたいなんで」(乗客)
「お忘れ物の捜索をお願いします。1のAに黒色の帽子です」(JALグランドサービス札幌 堀田愛佑梨さん)

「ありがとうございます」(乗客)
「黒色じゃなくて白色でした。私の聞き間違いですね」(堀田さん)
堀田さんは、複数のことを同時にこなしたり、優先順位を決めるのが苦手だ。

「重なってお客様がお申し出されたりするので、心の中ではザワザワしてますね。こういう時、どうしたらいいんだろうって」(堀田さん)
子どもの頃から家族旅行でよく空港を訪れていた堀田さんは、次第に航空会社で働く人たちに憧れるようになった。
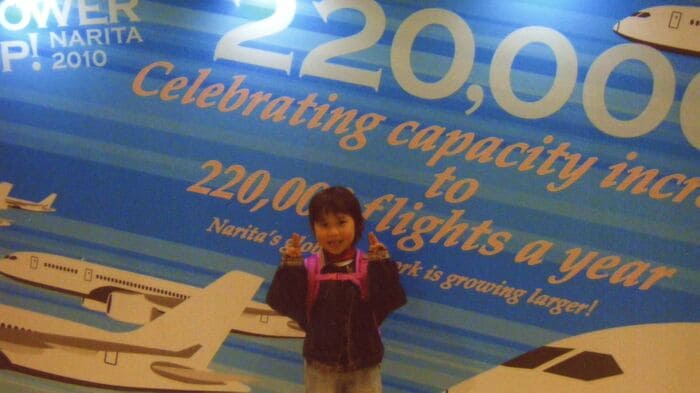
「すごいですよね。パソコンを扱いながらお客様と接する。どんなに忙しくても笑顔で接しているのがすごく格好いいなって思うし」(堀田さん)
真似してスカーフつけてみた 夢を後押ししてくれた先生
「当時の私の流行りだったと思うんですけど、グランドスタッフの方とか、もちろんCAさん。スカーフをつけて仕事をしていたので、それに憧れて自分も真似していたって感じです。でも高校生になるにつれて、現実性が分かってきたというか。きっと自分の特性もあるから、なることは難しいんじゃないかなって考えていました。周りもそう思っていたと思います」(堀田さん)

航空会社で働くという堀田さんの夢を後押ししてくれた人がいる。

ふたりは、堀田さんの母校、札幌みなみの杜高等支援学校の先生。

生徒の就職を応援する「進路」担当だ。

「思ってもみなかった業種を、生徒たちが言ってくれるんですよね。高等支援学校卒業の生徒が行ったことがないとか、前例がないとか、どうでもいいですよね。だってその子が言うんだから、その子のイメージを現実に寄せていきたい」(札幌みなみの杜高等支援学校 佐々木香織先生)
教員自ら会社に出向き“生徒の就職先の可能性”を探る
向かったのは学校の黒板などを製造する会社だ。

ふたりはさまざまな業種の企業に出向いて、生徒たちの就職の可能性を探っている。
「3年生に上がったら4週間と4週間、力試しで実習させてほしい」(佐々木先生)
「タイミング次第ですね。うちも毎年新入社員を取るほどの規模の会社ではないので」(社長)

ふたりがやり取りする企業の数は、多い時で月に100社を超える。
2017年に開校したみなみの杜高等支援学校には、軽度の知的障害がある生徒約170人が通っている。

特に職業教育に力を入れ、農業や調理、接客などを学んでいる。
生徒との何気ない日常会話もヒントに
学校が大切にしているのは、生徒の夢を応援することだ。
普段の会話も、将来の仕事を考えるヒントになる。

「8月1日に『インサイドヘッド2』を見に行こうかなと思ってて」(生徒)
「映画が好きなの? 映画館とかで働いたらいいんじゃない?」(先生)
「ありかもしれないです。真面目にありかもしれない」(生徒)
「わたし、接客を前からやりたいと思っていて、飲食店とか、そういうところの」(生徒)
「(名刺が)いっぱいになっちゃいましたね。はちきれそうでですね。足してるんですけど」(佐々木先生)
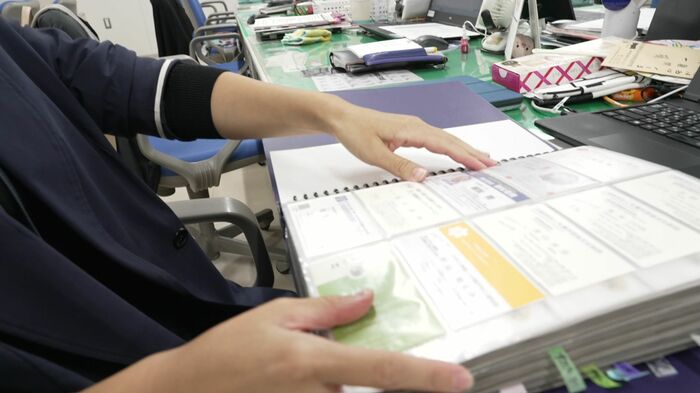
佐々木先生がこれまでにやり取りした企業は1000社以上。
生徒の夢を応援するため、新しい企業との出会いを大切にしている。

「生徒の就職につながるかもしれないという想いもありながら、私たちの視野を広げることも一つの目的です。『こんな世界があるよ』って。『チャレンジしてみたい生徒はいないかい』とか、『あなたの良さはここに合うと思うよ』と提案できるので、視野を持っていないと話ができないですよね」(佐々木先生)
「職業ゼミ」 就職した先輩から直接対話する生徒
「お洋服売る接客もあるし。こんな接客だったあるし、こんな接客だってあるしって一杯提案できるよね。そのうちのどれがやりたいのって」(高杉先生)
今年始まった「職業ゼミ」の授業では、企業から直接学ぶ機会を大切にしている。

石屋製菓では、卒業生から話を聞くことができた。

「先輩は最初、どういうところで働きたいと思っていましたか?」(生徒)
「一回はパン店じゃなくて違う場所もいいかなと思ったんですけど、やっぱり諦められなくて、先生に思い切ってここがいいと伝えました」(卒業生)
現代の仕事に合わせて生成AIの使い方も学びました。
従来の進路指導に疑問 生徒の力を生かした職探しを模索
30年以上知的障害のある生徒の教育に携わってきた小山学校長は、従来の進路指導に疑問を感じてきた。

「例えば、スーパーを調べて順番に電話をかけ、『こういう学校ですけれども、お話を聞いてもらえませんか』と一件一件回るんです。自分がこういう人生を歩みたい、こういう仕事に就きたいということに大きな制限がありました。その制限が当たり前だと先生方も思っていたんです。でももっとできることがあるはず。それぞれの子どもたちは一人一人力があるのに、なぜそれを生かして、自分がやりたい仕事にチャレンジできないのか、ずっとそう思っていました」(札幌みなみの杜高等支援学校 小山学校長)
小山先生は、みなみの杜高等支援学校の立ち上げに携わった一人だ。
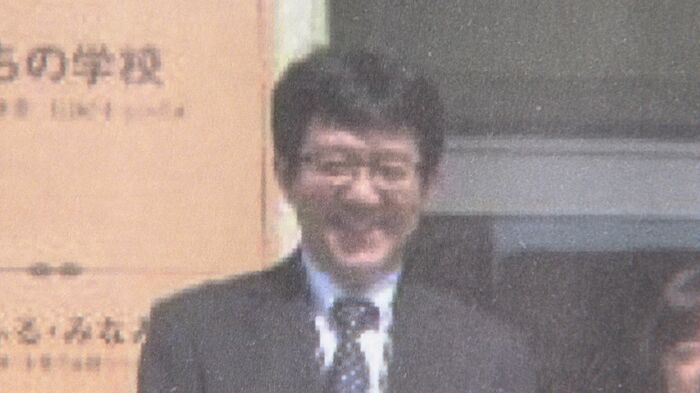
生徒が挑戦したいことを応援する学校にしたいという想いを込めた。
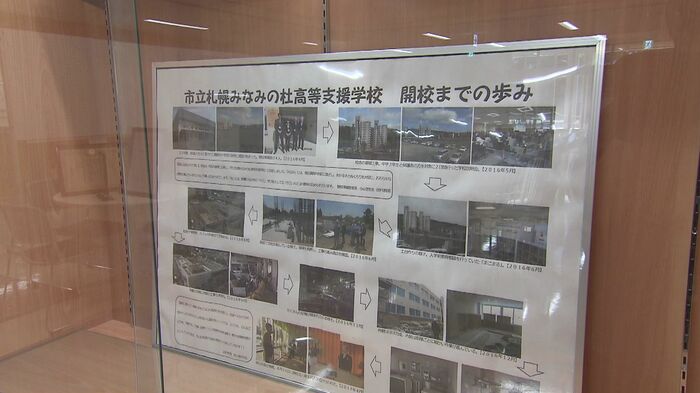
「彼ら彼女たちの可能性を、僕たちが決めてはいけないんです。これまでの常識にとらわれず、生徒たちの『こうしたい』という思いを全力で応援したい、それが大きな視点となっていました」(小山先生)
国が障害者雇用を進めるも道半ば 教員が情熱を持ち会社訪れる
国は障害者雇用を進めているが、「法定雇用率」を達成している企業は半数ほどにとどまっている。
雇用の課題として「会社内に適当な仕事がない」「イメージやノウハウがない」などが挙げられている。
この日、佐々木先生たちは北海道北見市に来ていた。

新たな企業を開拓するために建設業の伊藤諭さんと出会った。

「企業が求める人材を聞きたいんですよね。そうすれば就労に近づいていくので」(佐々木先生)
「音とかに弱い子は向いていないかも。機械が動くので、音が気になる子ってやっぱりいますよね」(大和谷工業 伊藤諭副社長)

「建設業をやりたいと言った生徒がいたら、『どこまで分かってる?』『どういうイメージ?』とか。建設業なら大きな音が出るよって」(高杉先生)
「生徒たちは遠くから自分の足で通ってきています。札幌は冬場、JRがすぐ止まるんですが」(高杉先生)

「その時の臨機応変な対応が」(伊藤さん)
「できます。職場や学校に連絡を入れたりして」(高杉先生)
「やっぱり(生徒を)一回見た方がいいっていう話ですね」(伊藤さん)
「見てください!いつ来ますか」(高杉先生)
「最初に会うのは先生ですから、先生から熱意を感じないと、企業側として受け入れようとは思いません。この先生がこれだけ言うなら、生徒を見てみようって。そこまで持っていきたいんです。生徒を見てもらえたら、変わるかもしれない。一生懸命ですから」(佐々木先生)
企業側も生徒と先生の熱意に打たれる 自分らしく社会で活躍
「1年経って、任せられる仕事も増えてきたので、胸の張り方が違いますね」(JALグランドサービス札幌 中原雄祐さん)
JALの中原さんも佐々木先生の情熱に動かされた一人だ。

Q. 挑戦させてあげたいと思った理由は?
「本人の熱意と佐々木先生の情熱です。『こういう子がいるんです。どうしてもやりたいと言っています』と言っていただいたとき、叶えてあげなきゃいけないと思いました」(中原さん)

佐々木先生の原動力。
それは、卒業生の活躍を見ることだ。
「今のようなシーンはけっこうありますか?」(佐々木先生)
「ありますね、日常茶飯事なかたち」(中原さん)

「素敵ですね、憧れます。彼女は臨機応変にいろんなことを器用に対応できるタイプです。それを見抜いてくれて、チャンスの場を与えてくださった会社の皆さん、本当に特別です。奮い立たされます。本人の姿を見て、企業の方の話を聞いて、学校に持ち帰るんです。在校生に何ができるか、職業教育にどうやって落とし込むかをまた考え始めます」(佐々木先生)
これからも、一人また一人と、自分らしく社会で活躍する卒業生を送り出していく。





