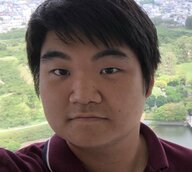9月1日に発足から1年を迎えたデジタル庁。
日本社会のデジタル化を推進する司令塔として当時の菅義偉首相肝いりで発足したが、結論として目に見える成果が乏しい1年だった。
河野太郎氏のデジタル相就任はデジタル改革の起爆剤になるのか?
マイナンバーカード申請はわずか50%
9月1日に行われたデジタル庁設立1年の活動報告会では、成果として2021年10月に始まったマイナンバーカードの健康保険証利用や、2021年12月にサービスを開始した新型コロナワクチン接種証明書アプリなどが挙げられた。
注目度が高いマイナンバーカードの普及では明確に苦戦している。
マイナンバーカードの普及事業「マイナポイント」などを推進した結果、マイナンバーカードの申請件数は、8月23日時点で人口の50%を超えたが、依然プライバシーやセキュリティ面での懸念が根強く、「2022年度末までにほぼ全国民に行き渡らせる」という政府の目標の達成は困難だ。
問題は実績だけではない。

報告会では、デジタル庁裏方トップの浅沼尚デジタル監が「今までデジタル庁は何をしているかわかりにくいという声をいただいているというのもしっかり認識をしている」とデジタル庁の広報にも課題があることを認めた。
デジタル庁の業務内容は多岐にわたる上に、法整備やシステム整備など裏方の仕事も多く、国民の多くがデジタル庁の活動内容が何かを認識していないのが現状だ。
河野デジタル相が誕生
こうした実績の物足りなさ、広報体制の弱さを突破してくれるかもしれないと期待が高まっているのが、河野太郎デジタル相の誕生だ。
8月に就任した河野デジタル相は、デジタル庁のこれまでの1年間の歩みについて「種をまいて、それに水と肥料をあげて、ようやく大きく成長して花咲くかなというところになった」と評した。
一方、これからの1年間については「生活が便利になったよね、と感じてもらえるような、そろそろそういう時期にしていかないといけない」と国民に“目に見える成果”を挙げることが求められているとの認識を示した。

河野デジタル相は、早くも政策実現のスピードアップを図っている。
当初は2024年の通常国会からの開始を予定していた、他省庁の法案を提出前に点検しデジタル化を阻むアナログ規制の有無を確認する「デジタル法制審査チーム」を、1年以上前倒しして8月30日に設置したのだ。
河野デジタル相は今年の臨時国会に間に合わせるよう指示したという。
またマイナンバーカードについても、2022年度中にカードの機能をスマートフォンに搭載する意向を示している。
マイナポイントなどで普及を図る現在のやり方を「若干邪道」と評し、「マイナカードを持つことで世の中がこんなに便利になる、あなたの生活もこんなに便利になる、ああ、それはいいねと、みんなでやろうよというのがあくまでも王道」と述べた。
変化するデジタル庁
河野デジタル相を受け入れるデジタル庁も組織課題を解決しようと動いている。
デジタル庁では現在職員約750人が140近くのプロジェクトを並行して進めているが、これからはプロジェクトごとに目標数値を設定し、進捗を客観的に評価できる制度を作るとしている。
また、民間企業で経営管理経験のある人材を採用し、プロジェクト全体を俯瞰しながら優先順位を明確化、整理した上でリソースを集中させて事業を進めることで成果を挙げていく方針だ。
課題とされる広報機能の強化にも注力していく。人員不足解消のため民間人材の採用を積極的に進め、機能強化を図る。ツイッターのフォロワー数が約255万人と政界随一の発信力を誇る河野大臣と連携し、デジタル庁の成果を伝える。
伝家の宝刀「勧告権」
デジタル庁の今後を占うキーワードは「勧告権」だ。
デジタル庁が誕生する際、当時の菅首相は、新型コロナ禍で露呈した行政のデジタル化の遅れに危機感を抱き、霞が関の縦割打破を目指すため、デジタル庁に強力な権限を与えた。それが「勧告権」だ。
「勧告権」は、デジタル化の総合調整機能を持つデジタル庁が各省庁に対し、システム整備の関連予算や事業内容を指示することができる。
「お願い」ではない「指示」という強力な権限であり、いわば「伝家の宝刀」だ。
しかし、各省庁のほうが個別の政策に詳しい上、抵抗も強かったため、牧島かれん前デジタル大臣は、一度もこの伝家の宝刀を抜くことはなかった。

この「勧告権」について、河野デジタル相は9月4日、フジテレビの番組で「デジタル庁から他の役所にこういうことをやってくださいというのは、積極的に申し上げていこうと思っている。法律の権限としてあるのならば、積極的に使うのが当然だ」と表明した。
この強力な権限を持て余すのではなく、有効活用出来るのかに、今後のデジタル庁の行方がかかっているかもしれない。
(フジテレビ経済部 デジタル庁担当 高橋怜央奈)