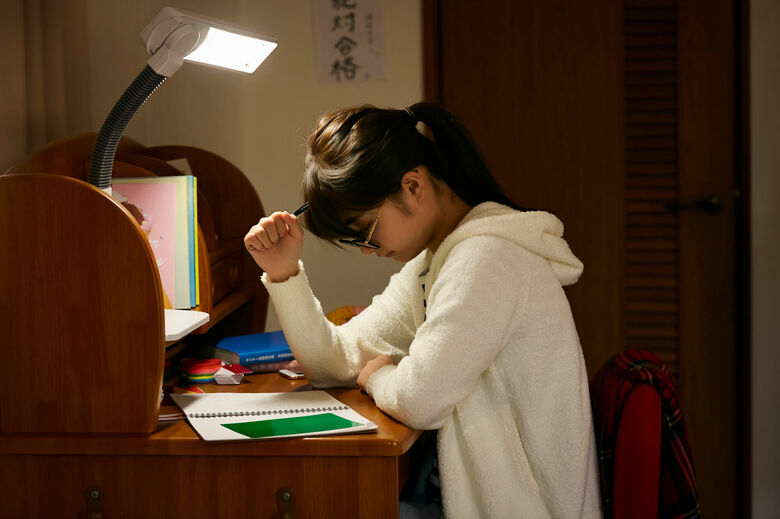「毒親」と言われる、子どもに悪影響を及ぼす親。
そういった親が、わが子の毒となる行為のひとつに「教育虐待」があるといわれている。
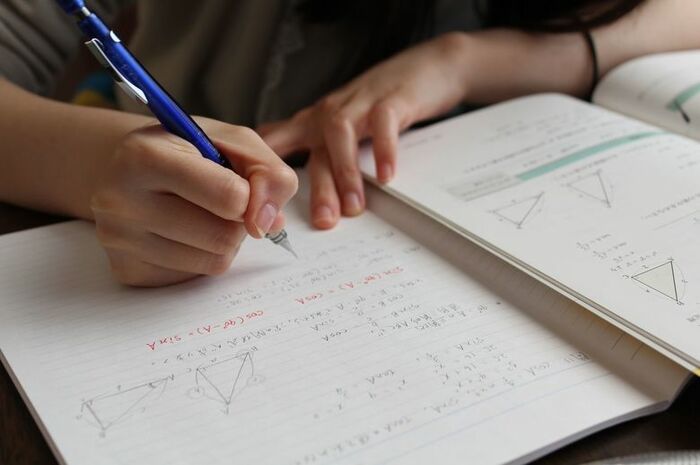
子どもに“しつけ”や“教育”をすることは、決して悪いことではないし、休校で子どもが家にいる時間が増える中、教育熱心な親ほど子どもの学力が心配になる気持ちもわかる。
しかし、どこまでの厳しさは許されて、どこからが虐待なのか? まずは、教育ジャーナリスト・おおたとしまささんに詳しく話を聞いた。
「あなたのため」と行き過ぎた“しつけ”や“教育”
ーー「教育虐待」とは何か?
教育虐待とは、「あなたのため」という大義名分のもとに、親が子に行う、行き過ぎた“しつけ”や“教育”のことです。
受忍限度を超えて勉強させるために、子どもに精神的あるいは肉体的な苦痛を与えている。勉強させる前提として、受験や進学について、本人の意思を親が軽視もしくは無視してしまっている状況があります。
例えば、「あなたは医学部に行くの」「東大に入りなさい」といったことを、子どもに強要し、親が主導権を握ってしまっていることです。
ーーいま増えているの?
増減を示すデータはないのですが、シェルターの人たちの話を聞くと、虐待の裾野が広がっているのを感じます。
昔は、ごく一部の教育熱心な家庭で起こっていたことが、現代ではよりカジュアルに起こっているのではないでしょうか。境目が難しくなり、教育虐待グレーゾーンみたいなものが、広がっているように感じます。
ーーその原因は?
以前は、「高学歴を得れば目的達成」といったように構造がシンプルだったものが、今は高学歴だけでは通用しない社会になっています。
これは、学歴が不要になったわけではなく、学歴だけではダメになってしまっている状況といえるでしょう。そのため、親が子どもに求めるものが、幅広くなってしまっていることが一因と思われます。
また、親向けの「コーチング」が関係している可能性があります。コーチングとは本来、その人が本当の力を発揮するのを支援するための技術です。しかし、悪用すれば、子どもを思い通りにコントロールするために使えなくもない。

親の期待通りにならなくても、「子どもの糧」には必ずなる
ーーでは、「教育虐待」になるラインは?
その日の勉強をやり終えた後に、子どもが達成感を感じているようなら大丈夫。しかし、勉強をやり終えたのに、子どもが死んだ目をしている場合は、すでに受忍限度を超えている可能性が高いでしょう。
言い換えれば、絶望の中で勉強しているということ。それは虐待にあたる可能性が高い。
ーー結局のところ、子どもは親の思った通りには育たない?
親になると、子どものためにあれもしてあげよう、これもしてあげようという気持ちに駆られますが、あれこれしたことが、そのまま親の期待通りの成果をもたらすとは限りません。むしろ、そうならないことのほうが圧倒的に多いでしょう。
しかし、やったことは必ず子どもの糧になります。親が自分の中で「これが正解だ」と思い描いているものに子どもがならなかったからといって、「この子はダメだ」と思ってしまうのは親の未熟さです。

以前、小学校受験を経験した母親たちを取材した際には、受験勉強が進んでいくうちに、親の方が「わが子を合格させてあげたい」と意地になってしまった…という体験談が聞かれた。
(参考記事:有名私立小の校内に学童保育も…共働き世帯の“小学校受験”は不利ではなくなりつつある)
しかし、最初は「子どものために」だった受験も、親が夢中になるあまり、親子関係に悪影響を及ぼしてしまっては意味がない。
では、子どもの教育で悩む親は、いったいどうすればいいのだろうか? 「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」著者でもある、慶応大学小児科教授・高橋孝雄さんに話を聞いた。
ほかの子どもとの“比べ方”が変わり、悩みが増えた
ーー子育ての悩みは多様化してる?
育児にしても、しつけにしても、時代が変わったからといって、悩みの種がそう変わるものではないと思います。ただ、核家族化や少子化により身近に相談相手がいなくなったことや、ネット情報が簡単に手に入るようになったことなど、子育てをめぐる状況は大きく変化しました。
中でも一番大きな変化は、ほかの子どもや家庭との“比べ方”が変わったことではないでしょうか。以前は、近所の子どもや同じ学校の生徒など、身近な存在が比較対象となって、育児の道しるべになっていたように思います。
今では、ネットから膨大な“役に立つ”情報が手に入るようになったので、自分がやっていることと、世間で“正しい”と言われていることを積極的に比べられるようになりました。その結果、「迷いが増えた」「悩みが深くなった」と感じているだけではないでしょうか。
他人と比べやすくなったがために、自分がやっていることに自信が持てなくなり、不安になっているだけだと感じます。
ーー受験がきっかけの精神疾患は多い?
例えば、拒食症や不登校などで入院してくる子どもたちの多くに共通している特徴は、受験の最中よりも、むしろ合格したあとに深刻な問題が生じていることです。
親子そろってがんばってきて、合格という成果にたどり着いた途端に、ちょっとしたことをきっかけに、それまでの育児や教育で積み重ねられた“ひずみ”が深刻化、表面化してくるのではないでしょうか。
受験勉強そのもので、子どもがどうにかなってしまうとは思いません。しかし、その過程で、全国模試での順位、目指す学校の偏差値などの“成果物”に親の関心が集中してしまうことが問題だと思います。結果第一主義が行き過ぎると、親子の関係にひずみを生じてしまうのではないでしょうか。

注意が必要な親の3つのタイプ
ーー毒親とそうでない親の違いは?
毒親という言葉はあまり好きではありませんね。すべての薬は毒にもなるように、要は程度問題かと。結果として自分の子から毒親と思われてしまう親は、愛情の“使い方”を間違っているだけなのでは。
教育やしつけの動機が知らず知らずのうちに「子どものため」ではなく「自分のため」になってしまえば、教育熱心も薬ではなく毒になってしまいかねません。
ーーどういうタイプの親、注意が必要?
3つのタイプが、考えられます。
1、がんばり屋さんタイプ
「自分ができたのだから、この子だってできるはず」「がんばってきたからこそ今の自分がある」という思いが強いため、薬(熱意)が毒(虐待)になってしまいます。このタイプは、子どもも自分自身も追い詰めてしまう傾向があります。
2、客観的評価を何よりも重視するタイプ
このタイプは父親に多く、結果第一主義とも言えます。教育の目的を具体的に設定しようとします。常にさらに上を目指すので、がんばり屋さんタイプと同じく、薬のはずが毒になってしまう可能性があります。
3、自分が努力しなかったことを後悔しているタイプ
自分にできなかったことを子どもにゆだねるタイプです。虐待に至る可能性は低いものの、そもそも自分にできなかったことを子どもに押しつけている以上、成果はあまり期待できません。

「悩んだ時に大切なことは、子ども自身に決めさせてしまうこと」
ーー子どもの教育で悩む親、どうすればいい?
教育の目的は、単に九九を覚えることではなく、「どんな人になってほしいか?」ということです。勉強やトレーニングは手段であって目的ではない、ということを見失わないことです。
育児や教育で悩んでおられるお母さん、お父さん、悩んでいることを否定する必要は全然ありません。子育てしていれば、悩みがない瞬間など…ないですよね。“悩む力”をお子さんにとっても、ご自身にとってもいい方向に活用するように工夫してはいかがでしょうか。
悩んだ時に特に大切なことは、子ども自身に決めさせてしまうことです。努力しなくてはならないのは、あなたではなくお子さん自身なのです。親が目的や手段を選ぶ必要はないし、義務もなければ、権利もありません。
ーーご自身の子育てを思い返してアドバイスがあれば教えてください。
学会の仕事で、かつての留学先であるボストンに出張する機会がありました。まったくの思いつきで、当時、高校2年生だった息子を一緒に連れていくことにしたのです。そこでの外国人医師との出会いがきっかけだったのでしょうか、帰国後、突然「医師を目指す」と言い出しました。スイッチが入った瞬間だったのかもしれません。
「浪人させる余裕はない」と条件を出しましたが、なんとか合格。その後に彼は名言を残しています。
「おれは勉強の仕方を知らなかった。もっと早く気がつけばよかった」
何かに打ち込んでみて、成果を上げてみて初めて、以前の自分に足りなかったものを見つけることは、すばらしいことだと思います。
決して、遅すぎるということはありません。むしろ、あとになって「ああ、そういうことだったのか!」と気づくほうが、感動は大きいのです。
自分から「勉強しようかな」と思わせるように、子どもが自分で考える“余白”を心の中に作ってあげるほうがうまくいくと思います。

外出自粛や休校を受けて、子どもの勉強について悩んでいる親は多いだろう。学習の遅れをつくらないことも大切だが、それがきっかけで子どもを勉強嫌いにしてしまっては、元も子もない。
自宅で家族と過ごす時間が増えている今だからこそ、わが子の話をじっくり聞いてみてはどうだろうか。
(執筆:清水智佳子)
【親子の距離感が悩ましい…あなたの「毒親」エピソード募集!】
「聞きコミ PRIME online」に、周囲と比べると何か違う、生きづらいと感じる原因はこれかも…あなたが体験した・もしくは聞いたことがある毒親エピソードを聞かせて下さい。
例
・「この子は私がいないとだめなのよ」が口癖で、実家を離れた今も、毎日電話でダメ出しをされ、電話に出ないと執拗にかけてくる
・親に人間関係の悩みを相談しても「お前が悪い」といつも人格を否定される
・子供の幸せに嫉妬する親、「ああいうタイプは信用できない」と難クセをつけ、恋人と強引に別れさせられた
・今、子育てをしているが、結局自分が親にされたのと同じことをやってしまっている
※入力された内容は記事で紹介させて頂くことがございます。
※改めて取材をさせて頂く場合もございます。