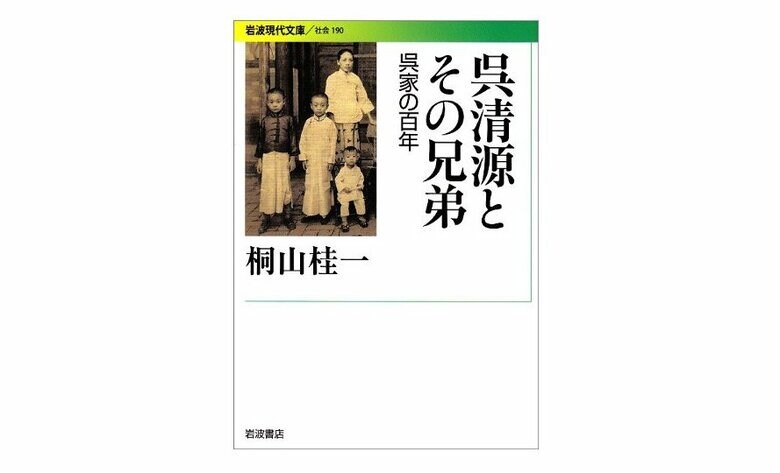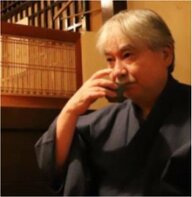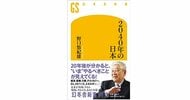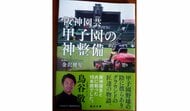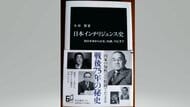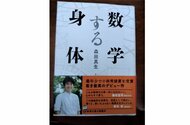将棋ブームの“お隣”でちょっと寂しい?囲碁界
将棋の藤井聡太棋士が登場してから、将棋はかつてなかったほどのブームを迎えることになった。数年前に14歳2カ月という史上最年少でプロ棋士四段になった時も騒がれたが、プロになって初戦から29連勝という連勝記録を打ち立ててまた騒がれたと思う間もなく、もう九段にして棋士序列一位、竜王・王位・叡王・棋聖・王将のこれまた羽生九段の最年少記録を抜いての五冠保持者。藤井五冠が対局中に食べたお菓子はバカ売れするわ、昼食・夜食に何を食べたかも写真入りで紹介されるわと、もうアイドルタレントどころの騒ぎではなくなっている。
将棋界での波及効果も「観る将」(将棋を観ること専門のファン)を生み出したり、キャラクターの濃い加藤一二三元名人(この人は若い頃「神武以来(このかた)の天才」と呼ばれていた)がさらにテレビ番組に引っ張りだこになったりと、とどまるところを知らない状態になっている。
一方、お隣の囲碁界はというと、ちょっと寂しい状況になっている。
まだあどけない仲邑菫さんが10歳0カ月で英才特別採用推薦棋士第1号として騒がれ、その後も好成績を残してすでに初段から二段に昇段しているが、やはり藤井四冠の破壊力にはかなわない。囲碁ファンの評者にとってまことに残念無念である。
そこで今回は、囲碁に関わる本を紹介しようと思う。
ただ、囲碁関連の本は、手筋だとか詰碁だとか、囲碁に興味のない人が読んでも意味のないものが大半で、一般の人が読むような本はほとんどない。棋譜がなく、囲碁をまったく知らない人が読んでも充実した読後感を得られる書籍を探し、やっと見つけ出したのが『呉清源とその兄弟―呉家の百年』( 桐山桂一 著・岩波書店 )である。
ただ、そういう事情で新刊本ではなく、というより10年ちょっと前の書籍であることはご了解願いたい。
昭和の最強棋士・呉清源
おそらく「呉清源(ご・せいげん)」と聞いても、その名を初めて耳にしたという人が大半だと思う。だが呉清源こそ、プロの囲碁棋士なら誰もが認める昭和の最強棋士で、映画『未完の対局』『呉清源 極みの棋譜』のモデルになった人なのである。
偉大な記録というのは、もちろんそれを打ち立てた人物の才能や努力が大前提だが、その人物を支えた人々の存在も忘れるわけにはいかない。呉清源もまた、多くの人々の支えや好意があって、呉清源となった。この本を読めば、それが実によく分かる。
中国の北京で囲碁が抜群に強い少年の呉と出会い、囲碁先進国の日本で活躍させようとした日本のプロ棋士、瀬越憲作(のちの日本棋院理事長)。その瀬越に呉少年の棋譜を郵送した美術商の山崎有民。当時、中国にはプロ棋士の制度がなく、プロ級の棋士は政官財や軍の高官などの囲碁の相手をして糊口をしのぐ生活を送っていた。山崎は、そういった環境のなかで呉少年の才能が埋もれてしまうのを惜しんだに違いない。
瀬越憲作は、その棋譜を見て驚愕した。
「完璧と称すべく、秀策少年時代を彷彿させるものがある」
日本の有力棋士・瀬越憲作八段から、山崎有民あてにこんな返事が届いた。
秀策とは当時最高の舞台であった「お城碁(将軍臨席の囲碁会)」で19戦19勝無敗の大記録を打ち立て、また秀策流布石にもその名を残す幕末の棋聖である。
「眼光紙背に徹す」とはこのことで、実は呉少年は、囲碁が趣味の父親が日本留学から持ち帰った本因坊秀策の棋譜を並べて独りで勉強していたのである。
父親が日本に留学していたぐらいだから、呉家は裕福な家庭だった。代々、塩専売を生業とする一族で、遺産分けを受けた清源の父は平政院の官僚で、7、8人の使用人を抱えていた。だが投機に失敗し、さらに肺結核でこの世を去ってしまった。その後、呉少年が囲碁会での賞品で一家を支えていたのだった。
呉少年に類いまれな才能を見いだした瀬越は、呉少年を日本に呼び寄せるために動き出す。
まず、犬養毅に相談をした。いうまでもなく、のちに首相になり、5.15事件で「話せばわかる」という言葉を残して凶弾に倒れた政治家である。
このとき犬養は「もし名人位を中国の少年に取られたらどうする」と訊いたとも伝えられる。それに対して、瀬越は「本望です。囲碁のためにも、日中親善のためにも本望です」と答えたという。
犬養は呉清源来日の手続きなどに便宜を図ることを約束した。犬養の女婿は当時、中国公使を務めていたのである。瀬越はさらに日本棋院の副総裁を務めていた大倉喜七郎宅に足を運んだ。大成建設やホテル・オークラの前身、大倉財閥の創業者、喜八郎の長男であるが、囲碁好きで知られていた。
呉少年をひとりで日本に来させるわけにはいかなかった。呉一家を支えているのは呉少年の賞品だけなのだ。呼ぶなら母親と兄弟姉妹の家族全員でなければならない。しかも来日しても、すぐにプロになれるわけではない。そしてプロになっても、低段位にうちは一家を養えるほどの収入があるかといえば、それも心もとなかった。ある程度の生活保証が必要だった。瀬越はそう考えたのだろう。
瀬越は呉少年の天才ぶりを熱心に語り、さらにその棋譜を広げて説明しようとした。
大倉は「それは君、(アマチュアの ※評者注)わしが棋譜を見たってわかりゃせんよ」と笑った。「君がそういうなら、その少年は強くなるに違いないから、よろしい、面倒を見ましょう。二カ年間、毎月二百円ずつでよろしいかな」
当時の数少なかった大学出の銀行員の月給が70円だった時代である。
他にも来日後、なかなか勝てなかったが、のちにライバルとなる木谷実。地獄谷温泉にこもって碁盤の中央とスピードを重視した「新布石」を2人あみだした。その考えは現在にも受け継がれている。また、それまで普通に打たれていた定石に疑問を投げかけ修正し、悪手とみられていた着手に新たな価値を見いだした。その中には、当時の専門棋士をして「いくら呉さんの着手でも、いい手には見えない」と敬遠した着手もあったらしい。
このように、呉清源来日に多くの人々が好意を持って関わり、また来日後もライバルたちと充実した日々を送った。
呉少年は彼らの有形無形の好意があって、のちの棋聖・呉清源となる。
その一方で、戦中、中国人が日本人に勝ちまくるのが気に入らないと、脅迫文を自宅に投げ込まれたり、母国の中国では「呉清源文化漢奸(売国奴)」と書かれた垂れ幕を、兄弟子である橋本宇太郎が目撃したりしている。その他、さまざまな嫌がらせがあったようだ。
いつの時代にもつまらない人間はいるものだが、それは呉清源の耳にもはいり、「2つの祖国」のはざまで、ずいぶんと思い悩んだという。
徹底取材で呉三兄弟を描いた秀作
さて、この本のタイトルは『呉清源とその兄弟―呉家の百年』である。
実は呉清源には自叙伝である『呉清源回想録 以文会友』(白水社)や『呉清源棋話―莫愁・呉清源棋談』(三一書房)、あるいは小説となった『呉清源』(江崎誠致 著・新潮社)など、数多くの関連書籍が刊行されている。
だが、『呉清源とその兄弟―呉家の百年』は清源のみならず、2人の兄のその後の人生を織り込んで、囲碁界という狭い世界から視野を拡大し、戦前・戦中・戦後の激動する東アジア情勢を背景に、歴史に翻弄されながらも、芯を通して生きた3兄弟を見事に描き切っているのである。
文庫版あとがきに記されているが、著者は生前の呉清源に2、30回にわたって聞き取りを行い、関連書籍に目を通すだけでなく、図書館にこもって、新聞、雑誌の関連記事を読みあさる。取材先も日本国内だけにとどまらない。新聞社で休みをとっては、訪中しては呉清源の兄である呉炎さんから聞き取りを行い、台湾にいた長兄・呉浣さんが取材時には亡くなられていたので、アメリカ在住の2人のご子息に会って、幼い頃の記憶を記録している。
また、空間の移動だけでなく、時間もできるかぎり遡り、呉家の先祖から書き起こしているのである。だからこそ、この緻密で重厚なドキュメンタリーができあがった。
当然、数多い登場人物が登場するが、著者は呉家・3兄弟の視座を通して歴史を描いているのだ。サブタイトルの「呉家の百年」の意味の重さが伝わってくる。
先に記した来日エピソードは、百年のほんの一場面に過ぎない。さらに読者は、巧みな構成と場面転換によって、まるで映画を見ているような錯覚を受けるはずだ。充実した読後感が得られるのは間違いない。著者の桐山桂一氏は執筆当時、東京・中日新聞の論説委員。さすがにノンフィクションを書く手腕はあざやかだ。
さて、清源とともに来日した長兄の呉浣は、早稲田と明治に学び、その後、帰国して満州国の官吏となる。そして次兄の呉炎は中国に残って天津の名門、南開大学西洋文学科の学生となった。侵略国日本に対する憎悪を募らせ、日本に対して弱腰の国民党政府を罵倒し、やがて毛沢東率いる中国共産党に傾倒していく。
そして終戦。日本軍撤退後の中国内戦のさなか、満州国の官吏だった呉浣一家は貨物船で台湾に逃げ延びた。出版社などに勤めていたが、仕事探しには苦労したようだ。「満州国官吏」と履歴書に書けなかったからである。
一方、次兄の呉炎は共産党員として中国本土に残ったが、文化大革命の過酷な試練が彼を待っていた。悲願の大学教授になったのは、文化大革命後のことである。これらの経緯も実に細かく書きこまれている。
一方、戦後になっても、呉清源は圧倒的な強さを見せつけた。読売新聞の専属棋士だったので、本因坊戦などには参加せず、本因坊位を獲得した棋士などが清源と番碁を打つという、いわば別格の存在として囲碁界に君臨する。
特筆されるのは高川秀格本因坊との本因坊対呉清源三番碁で、昭和27年から31年にかけて各年3勝0敗、9連勝を成し遂げているのである(28・29年は対局なし)。ただし、高川本因坊はその後、いくつかの勝利をあげている。
高川秀格本因坊はただの本因坊ではない。本因坊9連覇を達成し、二十二世本因坊の号を贈られ、さらに名人や十段のタイトルにも輝いた、昭和を代表する大棋士だ。呉清源が強すぎるのである。
しかし、やがて衰えが見え始め、昭和35年の交通事故が決定的となった。ひどい後遺症に悩まされ、盤上に集中できなくなったのである。そして対局から10年以上も遠ざかった昭和59年に70歳で引退。
引退式は、あの旧大倉財閥の流れをくむホテル・オークラで、囲碁界ばかりか政財界、文化芸術方面から800人以上を集めて開催されたという。
進化するAI…棋風が呉清源化?
最後に話を現在に戻そう。
AI(人工知能)が韓国の世界的トップ棋士、イ・セドルとの5番勝負に4勝1敗で勝ったのは2016年のことである。いまではAIに囲碁で勝てる人類はひとりもいない。そもそも思考過程が違うのである。
人間は長年の経験による「直観」で、いくつかの着手点候補を見つけ、その確認を読みに読んで最適と考えた地点に石を打ちおろす。AIは違う。光速のスピードで読めるので、すべての着手点から枝分かれする手順を何億手と読み、最も勝率の高い着手点を選ぶのである。
AIに「直観」を教えられないので当然のことだが、それがゆえにAIはその一手がなぜ良いのかを説明できない。それどころか、自分が囲碁を打っていることもわかっていない、単なる計算機械、木偶の棒なのだ。
しかしプロ棋士はそのAIの着手に意味を見出だそうと日夜、研究を重ねているのである。そして最近になってプロ棋士たちの間で、驚愕の声が上がりはじめた。進化するにつれ、AIが呉清源の打っていた特徴的な着手を次々に打ち始めたのである。依田紀基元名人は、「着手の流れの柔軟さや、人間離れした着想など、棋風が呉清源に似ている」という。
残念ながら、評者の知っているかぎり、呉清源がAIについて何かを語ったという話は聞かない。
呉清源は、AIがイ・セドルに勝った2年前の2014年に、満100歳という長寿を全うした。それでも、もう少し長く生きていればと思う。
AIと呉清源の天才が交わって、囲碁のもつ深奥幽玄な深い闇を解明できたかもしれないのである。呉清源亡き後は、それも、たぶん不可能になった。
【執筆:赤井三尋(作家)】
『呉清源とその兄弟―呉家の百年』( 桐山 桂一 著・岩波書店 )