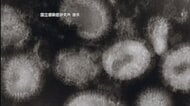変異ウイルスに置き換わった
「流行の主体が感染力の強い変異株に置き換わったと考えられます」
5月20日に開かれた東京都の新型コロナウイルスのモニタリング会議では、流行の主体が感染力の強い変異ウイルスに置き換わった、との分析が示された。
新規感染者数の7日間平均が、前回の840人から703人に減り、増加比も109%から84%に低下したが…
「新規陽性者数、高い値なのは間違いなくて。短期で再び増加に転ずるのではないかと、非常に心配してまして」

国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、さらに「連休の影響がほぼ取れてきた中で、同数が変わっていくのか非常に読みにくいところ」と、先行きの不透明さにも懸念を示した。
20代でも家庭内感染が増加
感染経路では、家庭内感染が59.4%と最も多く、20代でも家庭内感染が増加。
また、会食は4.7%となり、野外でも公園や路上での飲み会、バーベキューなどを含め、会食はマスクを外す機会が多いため、感染するリスクが高いことを繰り返し啓発する必要がある、との指摘も出された。
さらに、感染力の強いN501Yのスクリーニング検査では、5月3日の週に全体の74.9%がN501Yとなり、「流行の主体が感染力の強い変異ウイルス、N501Yに置き換わった」との分析が示された。

「ヒヤヒヤ…初めての状況」
「ヒヤヒヤしながらこのデータをみている。緊急事態宣言をしたのに(1人から何人に感染するかを表す再生産数が減少傾向を示す)1未満になるか、明確に分からないのは初めての状況でドキドキしている」
“8割おじさん”として知られる京都大学の西浦博教授は、モニタリング会議の前日、記者団の取材に応じ、感染状況の先行きを“読む”難しさを話し、今週後半から来週にかけてのデータをさらに注意して見ていく考えを示した。
「今月末までに国が示す感染状況のステージ2相当に到達するのは、到底難しいと考えている」
5月31日の緊急事態宣言の期限に向けて、西浦教授はこう話した。
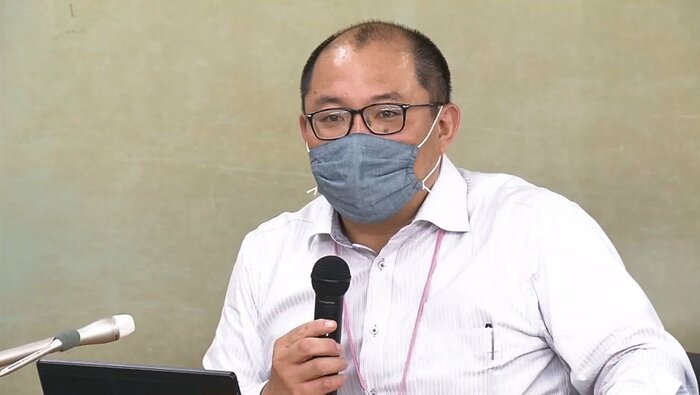
インド型の再生算数は…
そして、都の検査で新たにインド型変異ウイルスが2例確認され、全部で8例になった。
「インド株がどれだけ危険であるのか、もう少しカバーをしていただいて、みなさんと共有したい」
西浦教授は、インド型変異ウイルスについて強い危機感を記者と共有したい、とした上で「これはすさまじい話になる」と話した。
マスクの着用など感染対策を全く行わない場合に、再生産数は従来株で2.5倍、イギリス株はその1.5倍、インド株はさらにその1.5倍となり、インド型の再生算数は5.625くらいになるという。
つまり、インド型は1人から5人に感染することを表している。
これまで通りの対策で感染を制御するのは厳しい
「東京都でまん延防止等重点措置を早めに打つことができ、感染急増は避けられているが、減少傾向に向かっているわけではない。より感染力が強いとされるインド株がまん延すれば、これまで通りの対策で感染を制御するのは厳しい」
西浦教授はこう話した上で、「現行では(対策の)オプションが残っていない」とも指摘した。

従来よりもピークアウトが遅い
「変異株等の影響によって、人流抑制が感染者数減少に結びつくまでに従来よりも時間がかかっており、また、どの程度、感染者数が減少するかも不透明な状況」
東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターの西田淳志センター長は、感染状況の“先行指標”ともいえる繁華街の滞留人口について、緊急事態宣言2週目までは減少していたものの、3週目に入り増加、夜間は11.9%、昼間は7.6%増えている、とのデータを示した。
そして、2021年1月から3月の緊急事態宣言の際は、滞留人口が減ってから2週間で感染者数がピークアウトしたが、今回は4月24日に滞留人口が減少に転じたのに、3週間以上たってもピークアウトしていないことや、大阪では、3月27日に滞留人口減が確認されてからピークアウトまで5週間かかっている、とのデータも示された。

感染力の強い変異ウイルスの影響で、人流が減った後も感染者数減少に至るまで時間がかかっていて、これにより医療逼迫が深刻化する恐れがある、と指摘した。
若い世代へ警戒呼びかけ
「若いから大丈夫という保証は何もない」
小池知事は感染者の5割を20代、30代が占めていること、今週報告された死亡者38人にのうち、5人が40代、50代で比較的若い世代だったことを挙げ、改めて若者に感染予防対策を呼びかけた。
そして、ワクチンの遅れ、感染者数減少の遅さなどについてこう語った。
「いろんなタイムラグが生じていることが問題であり、課題である」

(執筆:フジテレビ都庁担当 小川美那記者)