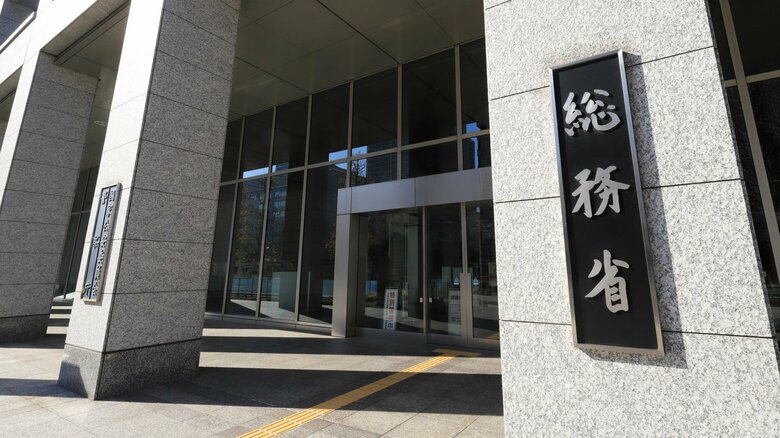ニセ・誤情報に接触した人のうち、4人に1人が何らかの形で情報を拡散させている実態が明らかになりました。
総務省は13日、全国15歳以上の男女に行った「ICTリテラシー(情報通信サービス等を適切に活用するための能力)」に関する実態調査の結果を公表しました。
過去にニセ情報や誤った情報を見聞きした人にその内容の真偽を尋ねた調査では、「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人があわせて47.7%と、半数近くにのぼりました。
また、こうした情報に接した人のうち、ほぼ4人に1人にあたる25.5%が、家族や友人など周囲に伝えたり不特定多数の第三者に発信したと答えました。
拡散させた理由を複数回答で聞いたところ、「情報が驚きの内容だったため」が27.1%で最も多く、「情報が話題になっていて流行に乗りたかった(22.7%)」、「話の種になると思った(21.0%)」と続きました。
自分の利益や承認欲求につなげることを目的とした「フォロワー数を増やすため(7.4%)」や「他者からの注目を集めるため(3.6%)」などの回答は1桁台にとどまった一方、ニセ・誤情報に「価値がある」と感じてしまった人が多く、「情報が興味深いと思ったため(20.9%)」「情報が重要だと感じたため(20.4%)」「他の人にとって有益だと思ったため(20.2%)」はそれぞれ20%を超えました。
拡散してしまったニセ・誤情報のジャンルは「医療・健康」が62.6%で最も多く、「経済」48.8%、「災害」39.3%と続きました。
拡散した情報が「ニセ・誤情報である」と気づいた経緯として最も多かった回答は、「テレビ・新聞(ネット版含む)で誤った情報と報じられていたから(39.6%)」でした。
閣議後の会見で、村上総務大臣は「利用者のICTリテラシーの向上に向けた取り組みの重要性が浮き彫りになった」と指摘したうえで、政府として今後、さらなる意識啓発の取り組みを進めていく考えを示しました。